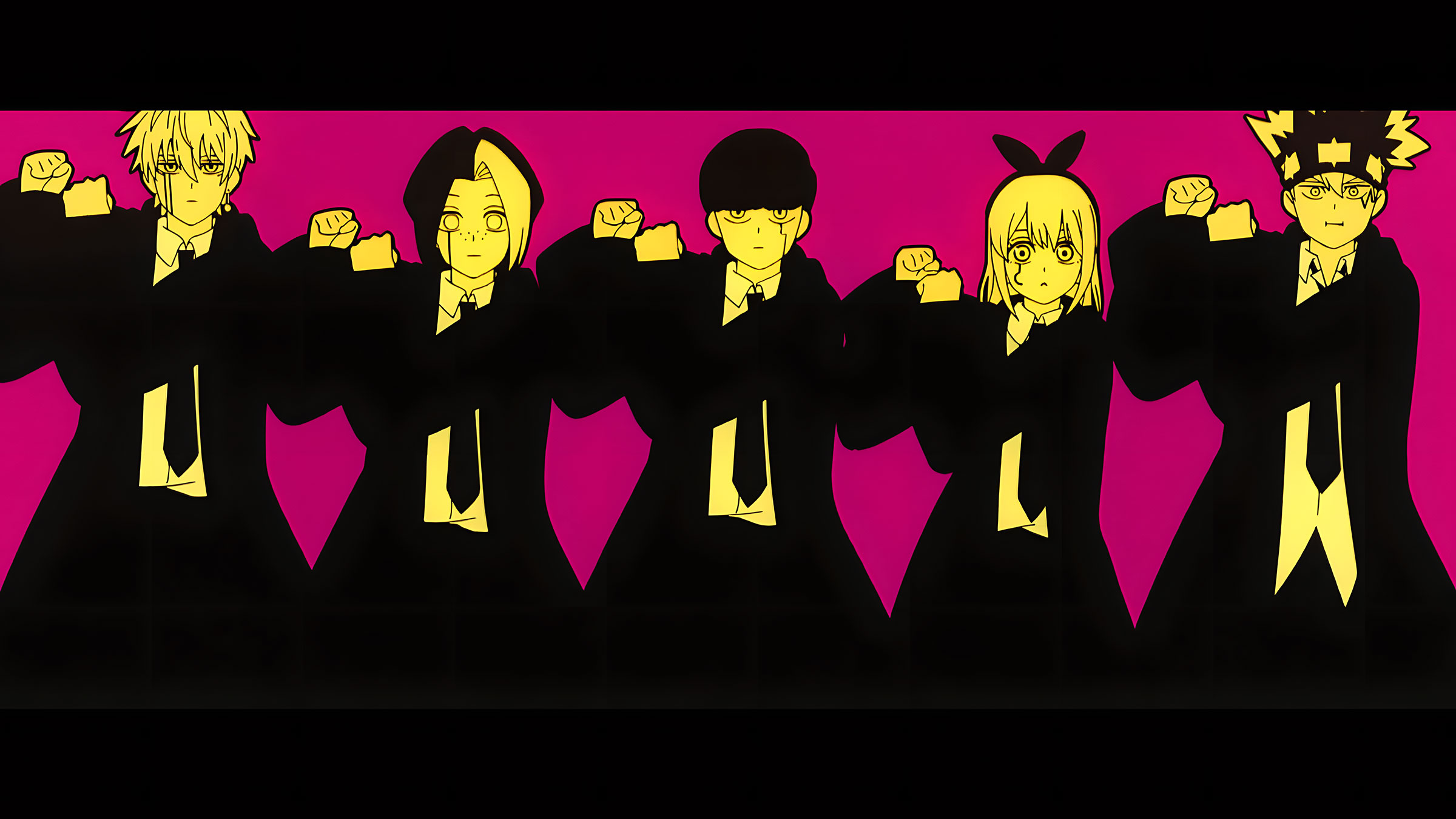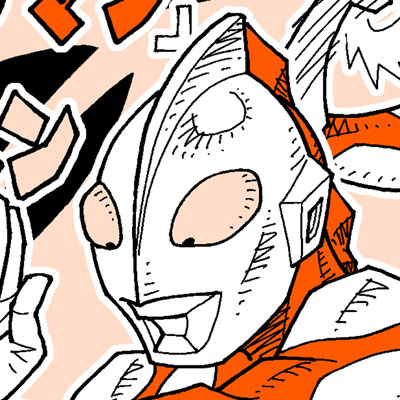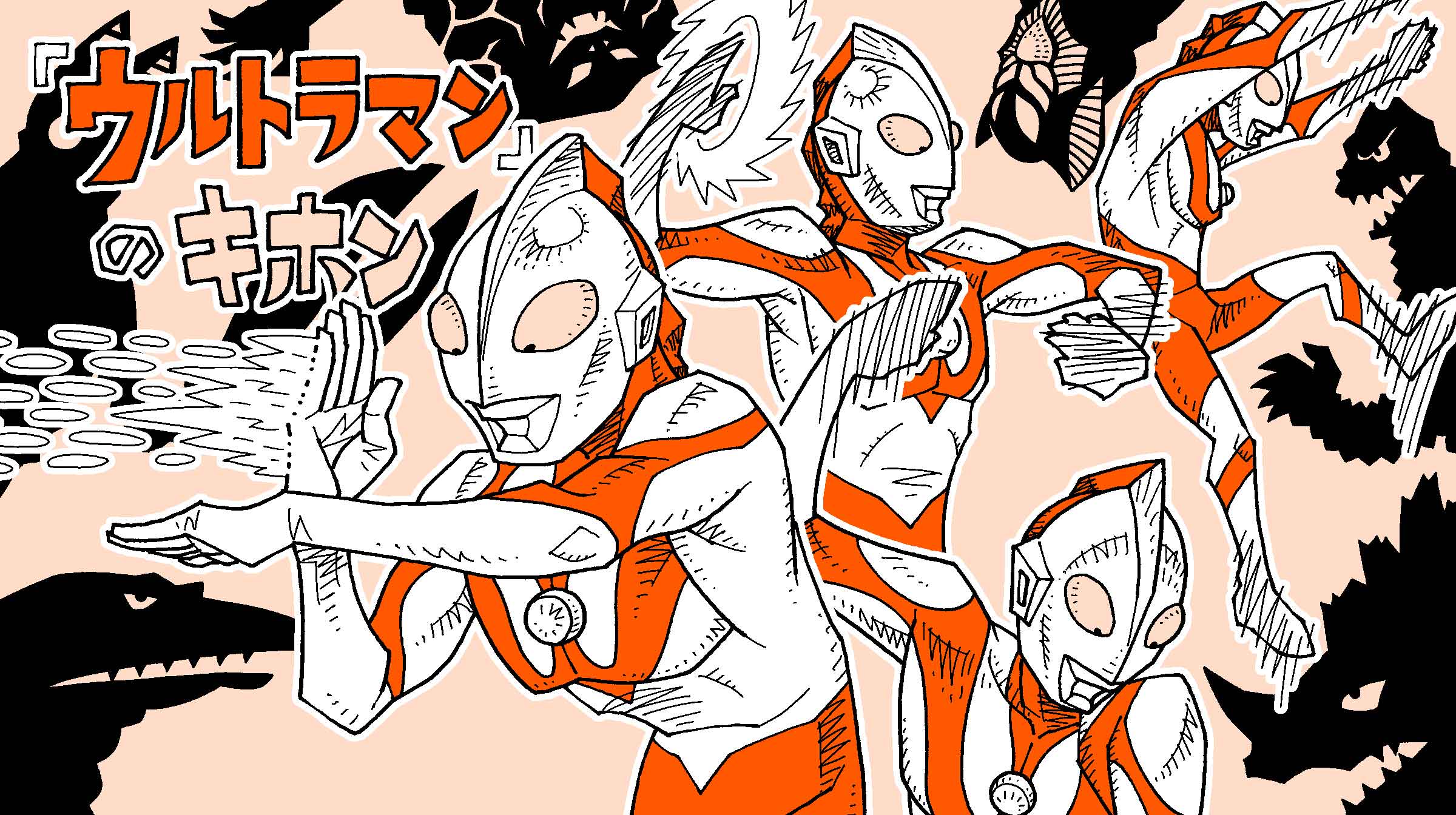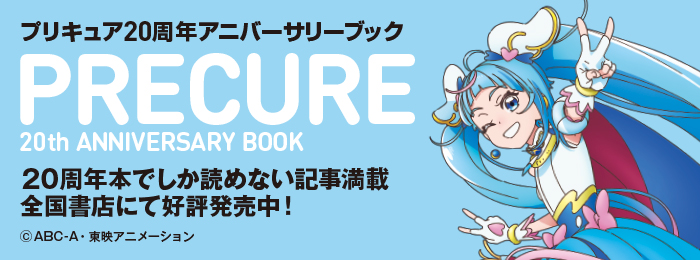シャガールの絵とアニメの絵
樋口 中学生のときに『機動戦士ガンダム』を見てから本当に尊敬しておりますし、憧れのアイドルでもある富野由悠季監督とこうして対談できるなんて、40年前の自分に自慢できます。関係者の皆様、本当にありがとうございます。
富野 尊敬されている富野という話は、今初めて聞きました(笑)。普段からそう言ってくれていれば、僕だってもう少しいいおじいちゃんになれていたし、自信だって持てたと感じています。
樋口 面と向かってなかなか言えないですよ(笑)。

富野 そういう尊敬を得られていると知れて、今、僕はとても感動しています。
樋口 私とキャラがかぶるので間違われる細田守という男がいまして(笑)、彼と一緒に福岡での展示を見ました。富野監督の圧倒的な人生を浴びるように体験するわけですが、『聖戦士ダンバイン』あたりで脳が固まってしまうんです。もうダメだと。博多ですから屋台でとりあえずこの情報の原液を消化しようと(笑)。それで2日かけて全部見て回りました。それは初見だったからなんでしょうけど、今回の青森の会場はとても見やすくて楽しめました。
富野 今回の展示はフロアがふたつに分かれていて、シャガールの「アレコ」という巨大な作品が展示してあるホールを通り抜ける構造になっているんです。これは自惚れだと自覚して言いますけれど、シャガールまでもが僕のスタッフだと気がついたのは本当にうれしかったんです(笑)。
樋口 あのシャガールは展示の一部になってましたね(笑)。
富野 九州から今回の青森まで全部の美術館に学芸員の方が付いてくれて、マンガとかアニメのような芸術性など皆無だと信じられていたものを、メッセージを発信できる媒体だと認識してくれた。そういうものであると、きちんと表現してくれた。それはアニメの仕事しかできなかった僕のような人間にとって、社会人として認められたといううれしみがあるんです。その反面、地方行政の公的な人々に認められるようになったら、それはアニメであろうがマンガ絵であろうが、もう少し社会性を持ったものでなくてはならないんじゃないか。つまり、好き勝手に作るなということをあらためて教えられたということなんです。

樋口 シャガールの絵とアニメーションの類似点というか、どちらも整理された情報を各々の心の目で見てほしいという点において似ているのではないかと感じるんです。
富野 要するに樋口監督が言いたいのは、シャガールのあの下手くそな絵がどうして世界中の人々が知るほどの評価を得ているのかということなんです。
樋口 下手くそとは言ってないです(笑)。
富野 印象付けられる作品がどういうものかというと、スーパーリアリズムのようなものでもなく、またモダンアートのように作家が価値を押し付けるようなものでもない。それは全部ウソです。シャガールの作品がこれほど評価されるのは、その作家の人生が作品を通して象徴的に表現されているからなんです。我々は本能的にそういうものを好きになってしまう。皆さんも、魂のこもった絵というのを知っているはずです。たとえば、浮世絵というものを我々日本人は江戸時代から好きでいますが、あんな変な顔に描かれた人物画を部屋に飾っていてもムカッとしないのはなぜなのか。それは表現されているものに技巧が見えているからです。アートの語源は技巧、つまり工芸なんです。浮世絵には日本の風土、日本人というものがシンボリックにシンプル化して描かれている。それはアニメやマンガも同様だということです。

もっと面倒くさい話をしますと、ミロのヴィーナスという像があります。この像は両腕がないんですが、あれは腕がないから現在まで残っているんです。ヴィーナスと言えば女神だ、美しい、かわいい、というようにイメージがパッパッと湧いてくる。あの力は何だろうかというのが僕にとっては命題でもあるんですね。シャガールの絵が下手くそだっていいんです。なぜかと言えば、あの絵の背後にはシャガールという作家が見えるからです。たとえば、最近ではタブレットで絵を描く作家も多いと思いますが、あれで描かれる電気的な信号に変換された「線」は、本当にその作家の「線」なのかどうかという疑問もある。だからこそ、手描きのアニメが持っている記号性がどれだけ大切なもので、我々の感覚に寄り添っているものなのか、ということを……ああ。
樋口 どうしました?
富野 ごめんねえ(笑)。どうしてこういう話になるのか自分でもわからないんです。
樋口 いやいや、まさに今のがペン先の話じゃないですか。

富野 そう、その話にしましょう。僕は中学2年生のときに手塚治虫先生からお葉書をいただいたんです。
手塚治虫からの手紙
樋口 本当はいちばん展示したかったけれど、どうしても見つからないという葉書ですね。
富野 そうです。
樋口 でも、ほかのメモ書きや文書、資料はものすごくきちんと整理保管されているじゃないですか。よくこれだけのものが残っているなと驚愕します。
富野 片づけられなかったから残っているの(笑)。いちばん大切にしていた手塚先生の葉書がなぜかなくなっているということに人生の無常を感じるんです。
樋口 富野監督から手塚先生に手紙を書かれたんですよね?
富野 手塚治虫先生のような線が描けないから「どういうペン先を使っているんですか?」というファンレターを書いたんです。そうしたら1か月後くらいに返事があって、それには「カブラペンを使っていますよ」とあった。
樋口 中学2年生がファンレターに技術的な質問を書くというのも珍しいと思いますし、返事を書いてくださる手塚先生も偉大です。
富野 当時の小田原の町で買えるペン先では、手塚治虫のキャラクターを同じように描けないんです。Gペンというのが売っていたからそれも試したけれどダメで、これは本人に聞くのが手っ取り早いと思った。返事をもらったとき僕はガキだったから、マンガ家というのは暇なんだと思っていた(笑)。あとから知ったけれど、その当時の手塚先生は『リボンの騎士』などの連載作品が最盛期で、そんな暇は到底なかったはずです。

樋口 質問が良かったからなんでしょうか。
富野 そうは思えないな……。ただ、この坊やには返事を書いてもいいなと思ったんだろうね。僕はその後、虫プロに入社して手塚先生ご本人にもお会いしているし、その書き文字も絵も目の前で見ているから、あの葉書が直筆だったことはたしかなんです。でも、虫プロに入社してからの僕は手塚先生のことを社長と呼んで一線を引いていたから、ご本人にその話題を振ることはなかった。本当に大事にしたいものというのは、どこかに整理したくなるでしょう。それで中途半端に整理してしまうから、どこかに紛れてしまう。だから展示されているものは、整理し損なった残りものばかりなんです。
樋口 いやいや(笑)、貴重な資料ばかりだし、当時積み重ねていた想いに触れることもできて圧倒されます。![]()
- 富野由悠季
- とみのよしゆき アニメーション監督、演出家。原作となる小説あるいは脚本を執筆することもある。主題歌などの作詞を手がけることもあり、多方面での活躍が知られる。代表作に『機動戦士ガンダム』や『伝説巨神イデオン』などがある。現在は『Gのレコンギスタ』の劇場版の制作に携わっており、シリーズ第3作目となる 劇場版『Gのレコンギスタ Ⅲ』「宇宙からの遺産」の公開が控えている。
- 樋口真嗣
- ひぐちしんじ 映画監督、特技監督、映像作家。実写映画畑の監督として知られるが、アニメーション演出(絵コンテ)も手がけるなど表現手法に固執せず広く活躍している。代表作に『シン・ゴジラ』『ガメラ 大怪獣空中決戦』などがあり、自身の監督作である『ローレライ』や『日本沈没』では富野由悠季を端役として出演させてもいる。