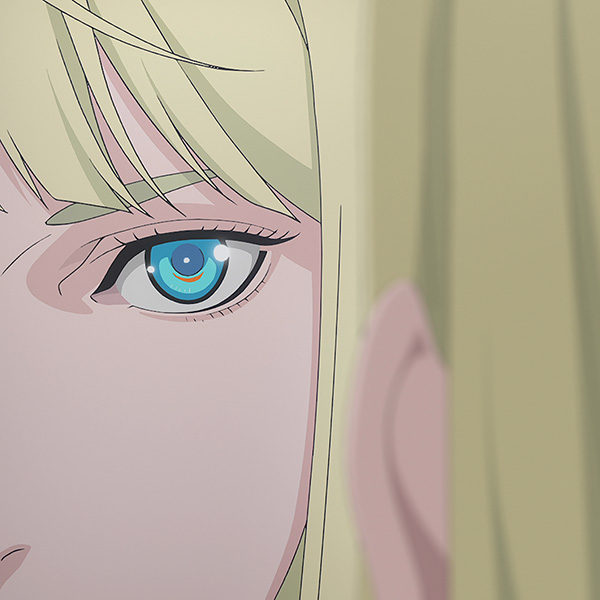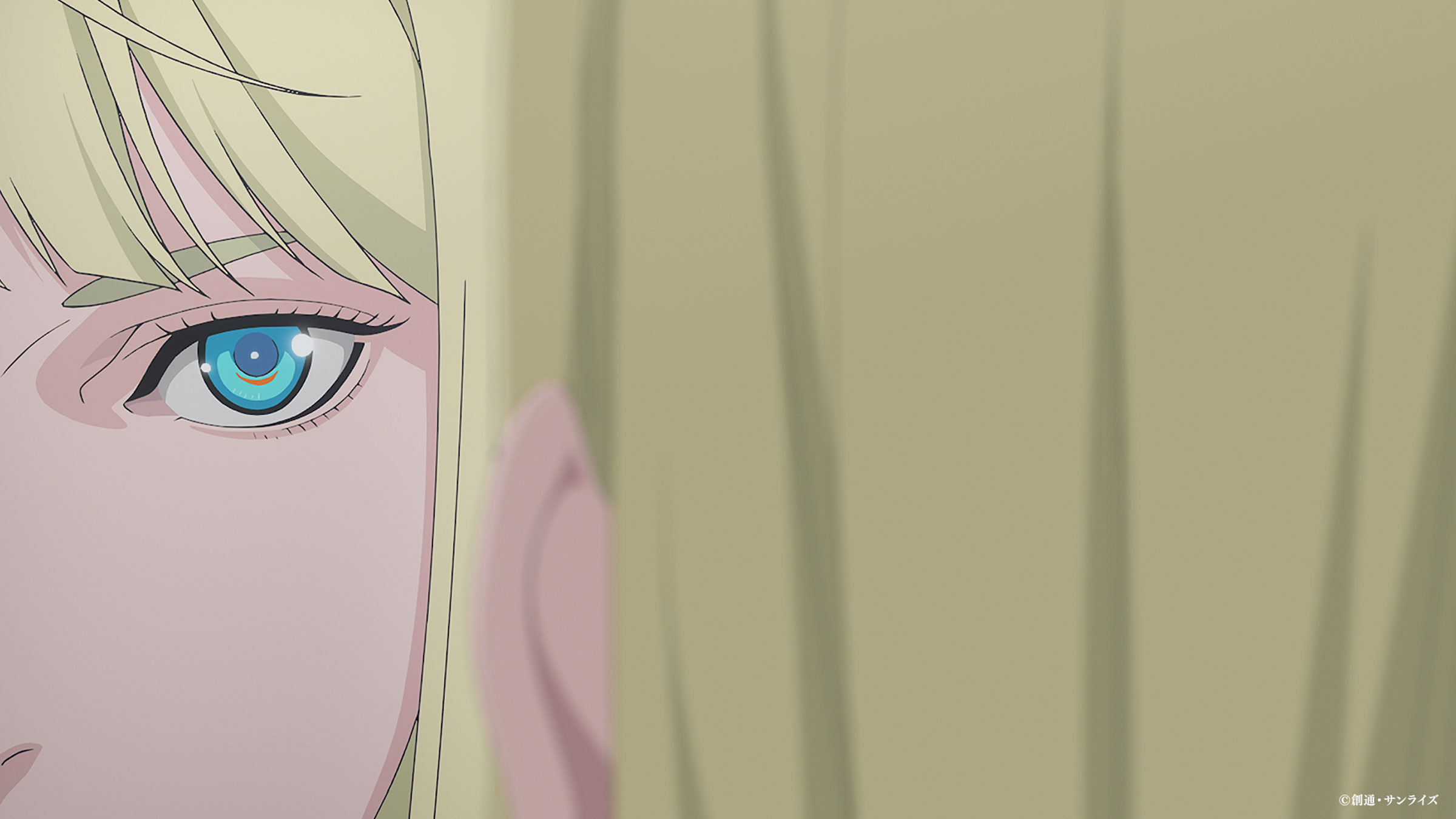「合成の誤謬(ごびゅう)」というテーマ
――今回の『唐傘』では舞台を大奥に据え、組織における個人の葛藤のようなものに焦点を当てて物語が進みます。こういうテーマを扱おうと思ったきっかけがあったのでしょうか?
中村 じつは制作当初、「同調圧力を扱ったらどうか」という提案をいただいたんです。ただ、「今、同調圧力と言われてもなあ」という気持ちがあって。というのも、コロナ禍で同調圧力の話がずいぶん出たと思うんですね。すでに現実で体感しているものを、わざわざ映画で見なくてもいいんじゃないだろうか、と。そこで考えたのが「合成の誤謬(ごびゅう)」というテーマでした。
――個人の視点では合理的な行動であっても、社会全体では同じ行動をしたときに必ずしも好ましい結果が得られるわけではない、個人の合理性と集団の合理性は合致しない、という経済用語のひとつですね。
中村 そうです。それこそネットやSNSを見ていると、毎日誰かが何かに対して怒っているのを目にするんです。それもひとりやふたりじゃなくて、大勢の人がそれぞれに怒っていて、しかもそれがとても大きな声として現れてくる。「この状況は何なんだろう?」と思ったのが、最初のきっかけでした。というのも、僕自身はあまり――まったくのゼロではないにせよ、ネットで見るような温度感では怒らないんですよ。なぜかというと、自分の中でそういうことに対して線を引いているところがある。「これは社会的な問題だから、みんなで大事に考えなきゃね」というのと「それは個人が思っただけだろう」というのを分けて考えているところがあるんです。組織を作っているのも人間だし、怒っているのも人間だから、一見、わかりあえそうな気がしちゃうんですけど、なかなかわかりあえない。そのときに「合成の誤謬」という言葉を思い出して、僕自身、「ああ、なるほど」と腑に落ちたところがあったんですね。個人と組織の利害は絶対に一致しないし、それをなんとかしようとこだわり続けるのは、ちょっとマズくないっすか?という。

――なるほど。
中村 もちろん、犯罪とかはダメですよ。組織が個人に圧をかけて、最終的に死んじゃったとか、逆に個人が組織に対してテロみたいなことをして迷惑をかけるとか、そういうのはよくないと思うんですけど、でも普通に生きていくなかでは、あまり社会や集団と自分自身の合致にこだわらないほうがいいよね、と。そして『モノノ怪』のいいところは、個人の辛さに寄り添えるところだと思うんです。まわりからするとどんなにくだらなかったり、甘っちょろいことをある個人が言っているとしても、その人自身にとっては本当に辛くて、苦しいことはリアルなはずで。そこにはやっぱり情念があって、放っておくとモノノ怪になってしまうかもしれない。であれば、薬売りくらいはその辛さに寄り添ってあげて、斬ってあげてもいいんじゃないのか、と。

TVシリーズの薬売りと今回の薬売りは別人
――今回の薬売りの魅力は、個人の気持ちに寄り添えるところだと。
中村 TVシリーズのときは、個人の隠された辛さを掘り起こして、みんなに見せるという方向だったんです。でも、今の世の中を踏まえたら、問題を騒ぎたてるような方向ではなくて「みんなで落としどころを探しませんか?」という作り方のほうがいいのかなと思ったんですね。そのうえで、そこにはやはり犠牲になる人がいて、そういう人はモノノ怪になってしまう。なので、形・真・理――要するに怪異となった理由を開いてあげて、理解したうえで斬らせてくださいね、と。そういう感覚なんです。
――そこは微妙に違っているわけですね。
中村 今の話に付随して言うと、TVシリーズの薬売りと今回の薬売りは違うんですよ。前の薬売りが1号だとすると、今回は2号なんです。
――仮面ライダーですか!(笑)
中村 そうなんですよ(笑)。どちらの薬売りも、モノノ怪に寄り添うところは同じなんですけど、今回のほうがより動的で、積極的に人を守ろうとする。1号と比べると、人間にもうちょっと重心が残っているというか。そこはそれぞれの薬売りのスタンスの違いなんですね。

――なるほど……。
中村 じつは、モノノ怪を斬ることができる退魔の剣は64本あって、薬売りは時の脅威に応じて最大で剣と同じ数だけ、この世に同時に存在できるんです。セリフの中に「我ら64卦(け)」という言葉が出てくるのですが、この「卦」というのは薬売りを数える単位で。TVシリーズのときにこの設定を作っていたんですが、公開するタイミングが全然なくて(笑)。今回、劇場版を公開するにあたって、少しずつ出していこうかなと思っています。
――そんな設定があったんですね! しかも本編を最後まで見ると、続編の予告が流れたので驚かされました。
中村 じつは続くんです(笑)。キャスティング的にはきっと重要な役のはずなのに、今回全然活躍しないな、って人がいると思うんですけど……。その人はのちのち主役的な活躍をする予定です。続編も引き続き「合成の誤謬」をテーマに、それをより深く追求していく感じになると思うのですが……。僕自身、「どうなるんでしょうね?」と思っています(笑)。今ちょうど、深めていくところと仕上げていくところを並行して作業していて。『唐傘』をご覧になって「先が気になった」「映っていた『あれ』には意味があるのか?」「『あれ』については説明されるのか?」という方がいらっしゃったら、ぜひ続きを見ていただけるととてもうれしいです。

――なるほど。では最後に、17年ぶりの『モノノ怪』になりましたが、あらためて新しい発見はありましたか?
中村 発見は多かったですね。アニメーション現場の環境の違いもそうですし、自分に対しても「ああ、今はこういうコンテを書くんだ」みたいな発見がありました。あとやっぱり『モノノ怪』というタイトル自体、とても好きな人が多いんですよね。自分が思っている以上に、観客はもちろん、参加してくれたスタッフの中にも『モノノ怪』を愛してくれている人が多くて。「じつは大好きで……」ってよく言われるんですけど自分自身は恐縮しちゃいます(笑)。17年というと、当時TVシリーズを見ていた人たちがプロとなって業界に入ってきて実力もつけちゃうだけの年月が経っていて、そういう人たちが今回の『唐傘』に参加しているのを見ると、とても素敵だなと思います。もちろん、ずっと同じ人たちが作り続けるよさもあると思うんですけど、その一方で、新しい人たちが入って、前のものを受け継ぎながら新しいものをつくるよさもあるな、と。そこはとてもいいことだなと思いますね。![]()
- 中村健治
- なかむらけんじ 1970年生まれ。岐阜県出身。2006年に放送された『怪~ayakashi~』内の一篇「化猫」が大きな反響を呼び、その後は人気演出家のひとりに。これまでの監督作に『モノノ怪』『空中ブランコ』『C』『つり球』『ガッチャマン クラウズ』などがある。