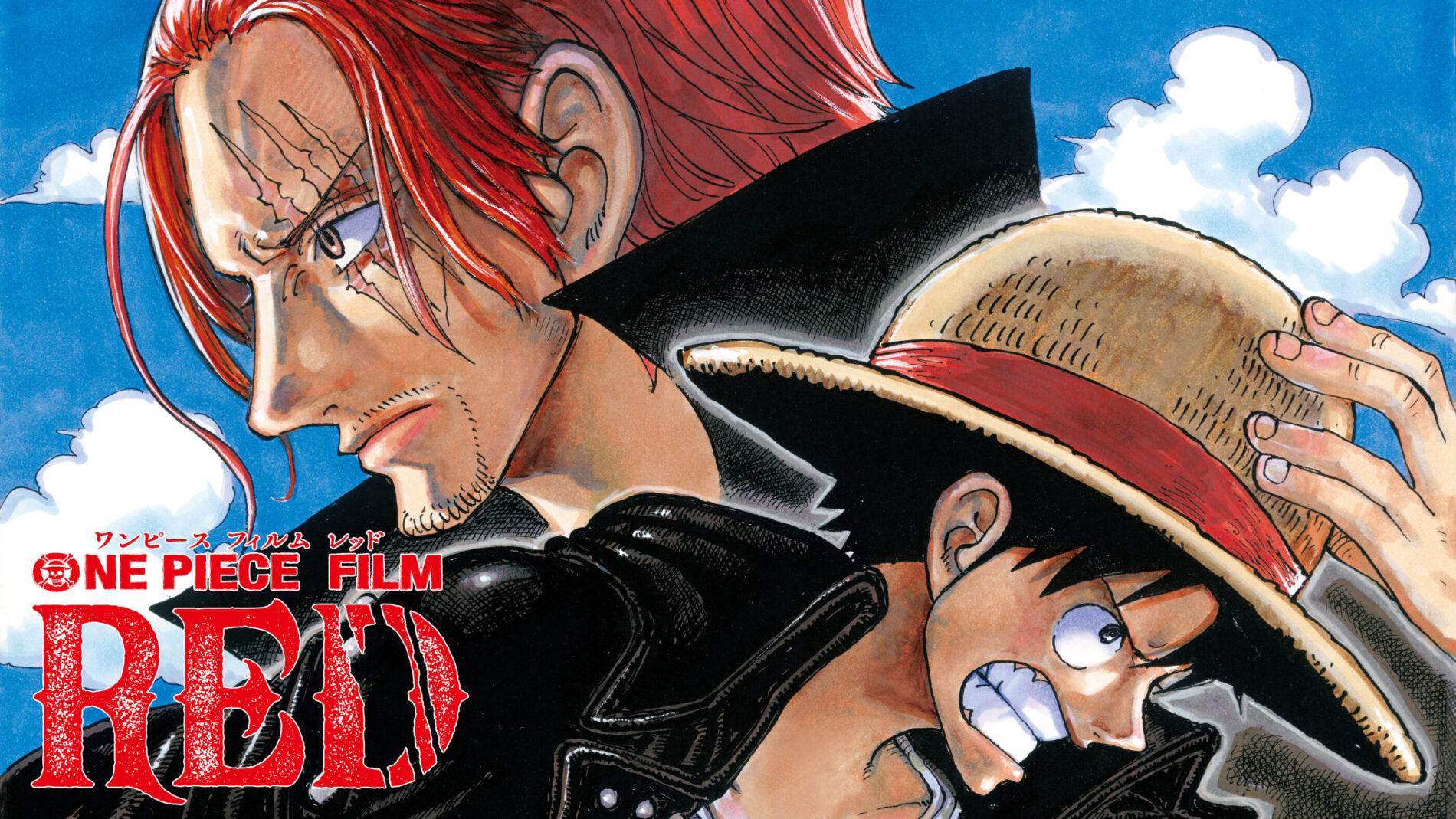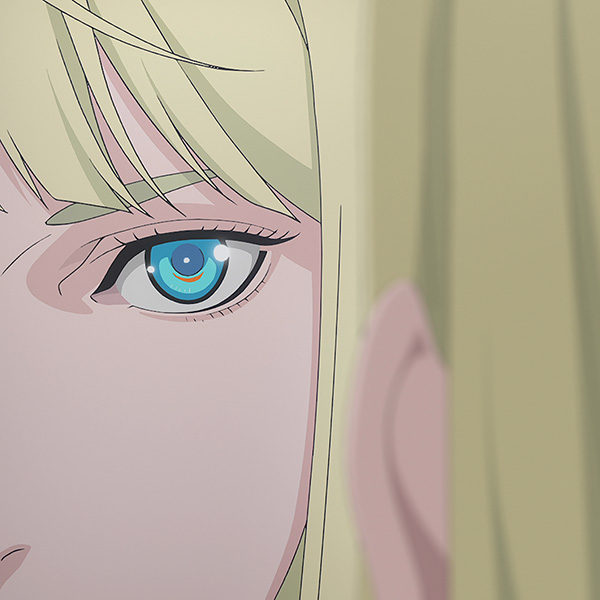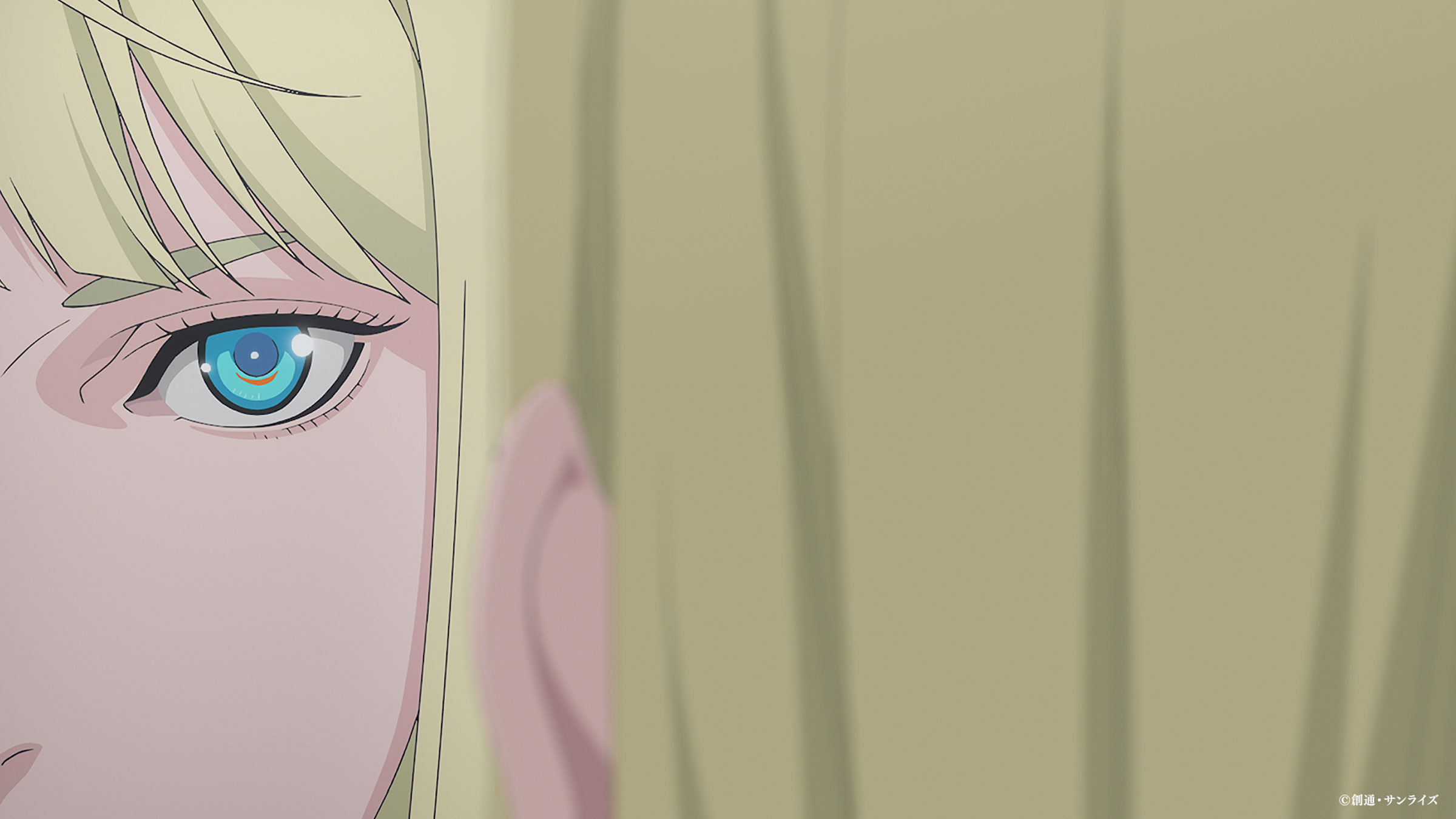縁のあるスタッフに支えられて実現した3DCGと作画の完全なハイブリッド
――ライブシーンは作画と3DCGの融合がシームレスな印象でした。
谷口 今回のダンスはポイントになるかなりの部分が作画なんです。ウタの動きに関しては、3DCGで連番データを叩き出してもらって、それをもとに作画する、というスタイルなので、完成した映像そのものが新たな技術というわけではないんです。モニターに映ったり、かなりロング(引き)の構図だったりするとウタのCGはそのまま使えたんですけど、腰から上の構図(ミディアムショット)以上になると、表情や関節の柔らかさを表現するにはやっぱり作画のほうが上なんです。だから3DCGはあくまで参考で、それとモーションキャプチャー収録時に撮影した参考動画をもとに、作画の皆さんに整理していただいています。だから作画さんがよりよい動きに見えると判断したら、連番で出てきた絵から作画を起こす際に絵を変形させてもらっています。言ってしまえば、作画と3DCGの完全なハイブリッドですね。それができたのは、先ほど少しお話しした私と以前の仕事で縁があったスタッフのおかげなんです。3DCG絡みの部署にその人がたまたまいてくれたことで、こちらのやりたいことが即座に伝わって、やりやすかったのも大きかったですね。

――アニメと音楽は、ディズニーの『ファンタジア』であるとか『マクロス』シリーズのように、相性が非常にいい、映像表現としての歴史の蓄積がある組み合わせです。監督はそうした歴史的な流れの中に、今回のフィルムを位置付ける意識はあったのでしょうか?
谷口 おっしゃるとおり、アニメと音楽というのは切っても切り離せないぐらい相性がいいものです。アニメは音楽だと言ってもいい。今回、その前提は意識したうえで、アニメだけに限らず、実写映画のことも意識していました。映画と歌というと、昔はアメリカ映画の印象が強い古いタイプと認識していたんですよね。でも、最近、歌の要素が絡んだ作品を明るく、楽しく見る……つまり、アトラクションとして楽しむ観客が増えてきたのかなぁと感じていたんです。個人的にはトム・フーパー監督の『レ・ミゼラブル』ぐらいが始まりかな?と感じているのですが。あの映画を見ていると「全部歌詞で説明して、何が楽しいんだ?」と頭のどこかで思いながらも、やはり歌が流れると聞き入ってしまう。それが歌の強さだと思わされました。そのあとも『グレイテスト・ショーマン』だったり、『ラ・ラ・ランド』もありましたしね。
――『ボヘミアン・ラプソディ』など、たしかに歌もの映画はヒットしている印象です。
谷口 映画の歴史を振り返ると、もともと映像だけだったものに活弁士などが音をつけるようになり、やがては映画そのものに音がつき……という歴史があった。音がついてからも、スピーカー数が次第に増えていったりして4D的な楽しみ方もできるようになった。音と映像をセットに完全な仮想世界を楽しんでいこうというのが、映画の発展の大きな流れだとするなら、最近の傾向もそんなおかしなことではないわけで、なら、一度くらいそこに乗ってみるか。やるなら派手にいこうと考えたのは大きいですかね。
シャンクスとルフィが会えない状況を逆手に取った脚本
――そうした流れで『ONE PIECE』の映画にウタの歌という要素が持ち込まれ、さらにそれが「ウタの夢によって作られた虚構の世界」という大きな設定を今作に導入します。今作の現実と虚構の世界の二重構造はどのような形で生まれたものだったのでしょう?
谷口 これは脚本の黒岩さんの発案なんです。すばらしいアイデアでした。というのも、お話の展開上、シャンクスとルフィは会うことができないんですよ。
――そうですよね。ふたりが出会うのは、原作の展開でも最重要トピックのひとつです。
谷口 しかし、今回の映画にはシャンクスをどうしても出したかったんです。そうすることで、大人がこの作品を見ることができる、大人の目線を重ねられるキャラクターが登場させられる。それによって、作品の厚みがまったく変わってくる。尾田さんからも快く許可がいただけて、出せることにはなったけれども、設定はどうクリアするか。決定的なアイデアが出る前に、いくつか考えてみたんですよ。たとえば、ルフィが寝ている間にシャンクスが活動して、逆にシャンクスが寝るとルフィが起き上がる……とか。でも、変じゃないですか、どう考えたって(笑)。なんかいかにも「ふたりを会わせないためにやっています」みたいな。

――ご都合主義っぽさはありますよね。
谷口 で、どうしよう?と思っていたら、黒岩さんから「世界を分けましょう」と言われて、これによって一気にやりやすくなった。画作りに関しても、ウタウタの実の能力によって作られた世界は、ウタの夢が全部詰まっているようなカラフルなものにして、対して現実側では、どこか色を抜いたトーンの、生活感を感じさせる画作りにすることで対比ができる。「現実はあくまで現実なのだ」という見え方にできるのは、助かりました。
――テーマ性というよりは、設定上の難しいところをクリアするためのアイデアだった。
谷口 そうですね。その方法で設定面の難しい点をクリアしたことにより、結果的にテーマがより明確になった、というべきでしょうか。
――虚構や理想、夢と現実のぶつかりあいは、谷口監督の作品らしいテーマだなと感じました。
谷口 違うことやっているつもりなんですけどね(笑)。

――ちょっと『うる星やつら2 ビューティフル・ドリーマー』への意識も感じました。
谷口 うーん、そこはないですかね。テーマが違うので。まぁ、あるとしたら音楽の参考として中田ヤスタカさんに『ビューティフル・ドリーマー』の曲を聞いてもらったことですかね。でも、他に細野晴臣さんの「銀河鉄道の夜」とかエリック・サティや坂本龍一さんなども参考にさせてもらっています。やはりね、私は虚構ではなく現実に行きついてしまいますので。
――そもそも『ONE PIECE』自体に、「海賊王」という壮大な夢を掲げるルフィという主人公が、現実の厳しさを叩きつけてくる相手と戦い続ける物語としての側面がありませんか?
谷口 そうですね。そして、手に入れようとするときに、ルフィは常に勝つわけじゃなく、負けることもあれば、仲間といさかいを起こすこともある。けれども、その夢だけは絶対に忘れていない。そこはやはり「少年マンガ」なんだと思います。男の子が昔持ったひとつの大きな夢、その夢に対してどう向かっていくのか。途中で挫折することもあるかもしれないけど、人生を使ってでも最後まで向かっていく。これが「少年マンガ」というジャンルそのものにある、大きな柱のひとつなのでしょうね。
「シャンクスとルフィの物語」を描きたい気持ちが噴出した
――今作はキャラが成長していく過程に、さらに親子関係も関わってきます。ウタとシャンクスはまさにですが、ウソップとヤソップなど、周囲にもそのモチーフが点在しています。
谷口 今回はどれも、かなりいびつな親子関係なんです。シャンクスからしてみれば、ウタとの関係は彼女が幼い頃、別れた段階で止まっているんですよ。「大きくなっているかな」とか考えたかもしれないけれども、彼女の精神性がどうなっているのかまではわからない。で、実際に会ってみてどうだったのか? 彼女は彼女なりに考えていることがあって、結局は彼女の自立を認めて、送り出すことしかできない。要するにこの映画では、親はほとんど無力なんです。ウソップがゴードンに対して投げかける言葉も、ゴードンのウタに対する後悔をフォローしてあげているんですが、事実としては「ウチも親父にろくに育てられていません」みたいなことを言っているだけで(笑)。

――ああ、たしかに! 見ているときは感動するやりとりですが……。
谷口 今回出てきている人たちは皆、生物学上の親、もしくは親的な立場にある人たちとは関係なく、自分たちで人生を選んできているんですよね。それでも親と子の情や絆と呼べるようなものはあるかもしれないけれど、それはもしかしたら、どちらかの一方的な「情」かもしれないし、それによって何が救われるのかっていうと、たぶん何も救われないのかもしれない……と。放り投げている、と言ってしまえばそれまでだけど、でも世の中ってそういうものでしょう、と思うわけです。それは私自身にとっても……。じつは私の作品には親がほとんど出てこないんですよ。もしくは出てきても、どこか邪魔だったり、敵だったりする。要するに「親子仲良く」というのができない。
――そうですね。
谷口 なので、そうした考え方の根っこにあるものが、今作にも多分に反映されてしまったかな、と思います。親子だから仲良くしなければならないとも、別に思わないし。敬う気持ちくらいはあるかもしれないけど、それだって限度があるし……と。
――シャンクスとルフィの関係も疑似的な父子の側面がありますが、そこはどうですか?
谷口 そうですね。今回はもともと私が「今回はシャンクスとルフィの話をやりたい」といって始めたのですが、それが自分の中に残っていて、作っているうちに噴出しちゃったのかもしれないです。

――えっ、そうなんですか?
谷口 今回の作品をつくるにあたって、最初に私が言ったのは「原作の第1話の内容をそのまま再現したい」だったんです。シャンクスが腕を失い、麦わら帽子をルフィに預けて去り、そして少年は旅立つ……というのを、あらためて映像化したい、と。それを組み込んだ映画にすることで、もう1回自分の中で、この作品の根底にあるものを踏まえたかったんです。で、そこから考え始めると、結果的にシャンクスとルフィのあいだに疑似父子的な関係性が発生してしまって、なおかつシャンクスの「娘」であるウタも出すことが決まると、もう、そこを突き詰めることから逃げられなくなってきた。それが作品全体を最終的にパッケージングしたのではないかなと。これは自分自身も作り終わってから発見した要素でした。
――クリエイティブの不思議ですね。自分でも気づかなかった、無意識の部分が作品に滲(にじ)み出ていた。
谷口 やっぱりね、ものづくりって、自分で自分を発見する作業でもあるんですよ。だから、もしかしたら今回私がもっともやりたったこと、表現したかったものは、そこだったのかもしれないですね。![]()
- 谷口悟朗
- たにぐちごろう 1966年生まれ。愛知県出身。日本映画学校からJ.C.STAFFに制作として入社。サンライズで演出家としての、Production I.Gで監督としてのキャリアをスタートさせる。『スケートリーディング☆スターズ』『バック・アロウ』他。