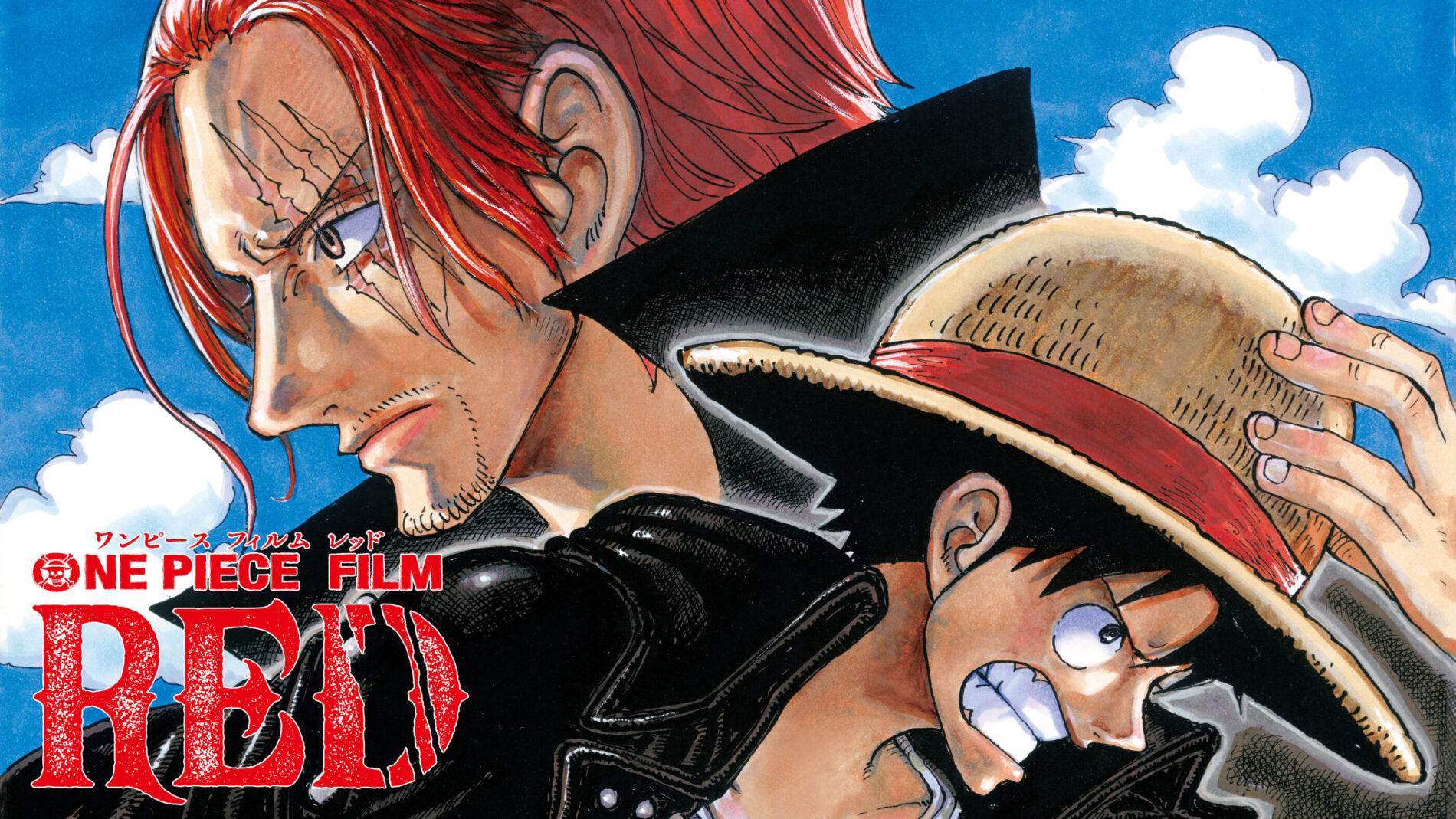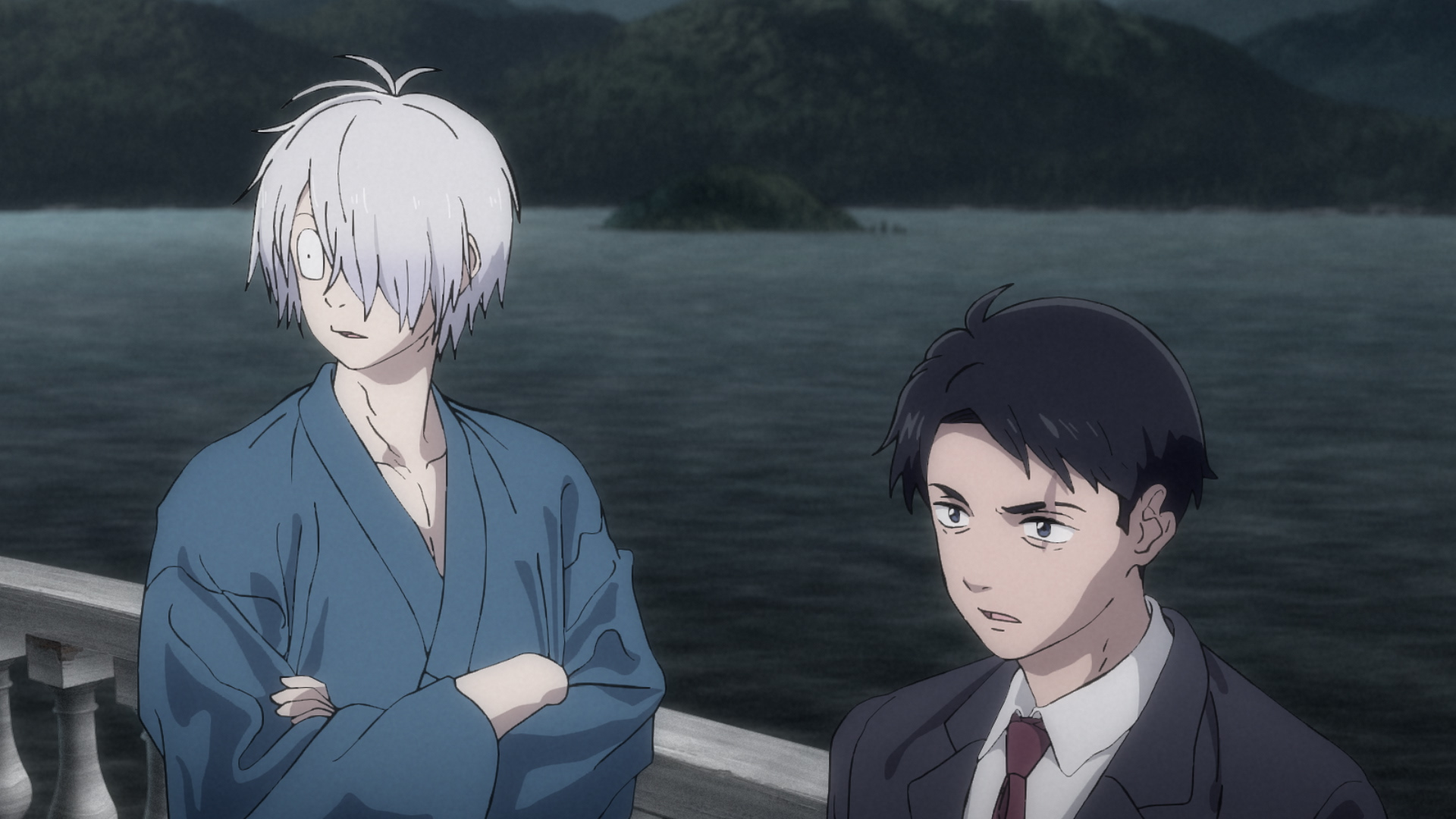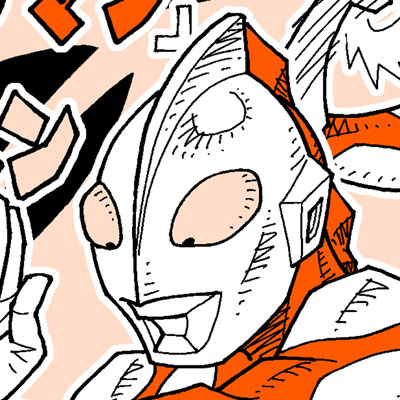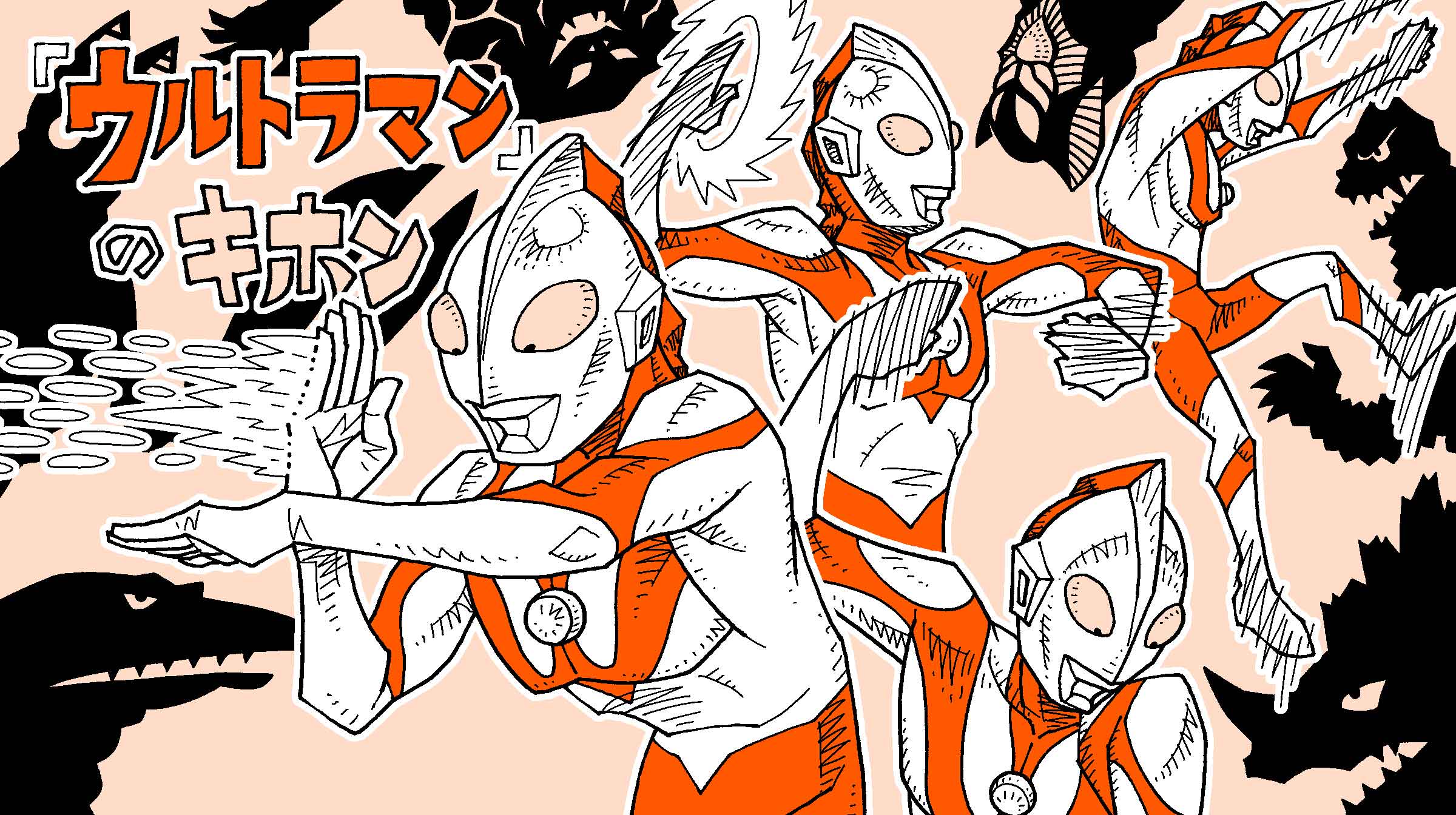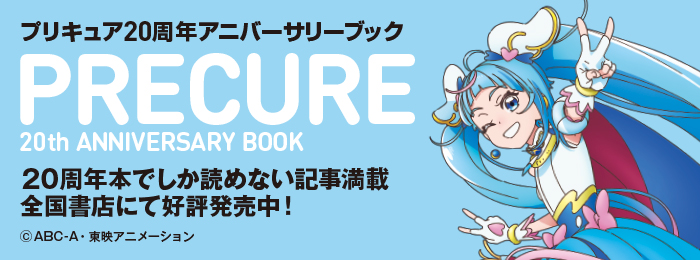ウタのイメージにぴったりだったAdoさんの歌声
――『ONE PIECE』の原作はコミックスの全世界累計発行部数が5億部を超す、名実ともに今の日本のエンターテインメントを代表する一作です。今回、監督としてそうした作品と向き合って、あらためて感じたすごみはありましたか?
谷口 プレッシャーという意味ではあまりないですね。初めて関わるわけでもないし、売れていく過程をはたから見ているわけですから。あえていうと、エンドロールに並んだ声優さんの名前くらい。ベテランばっかりじゃないですか(笑)。
――強烈ですよね。麦わらの一味を筆頭に、ひとりで作品を背負えてしまうほどの重鎮揃い。
谷口 赤髪海賊団だっておかしいでしょ(笑)。

――ですね(笑)。普通の作品でしたら、あのわずかなセリフではお声がけするのもためらってしまうような、大重鎮の皆さんが参加しています。
谷口 本当に、音響制作費どうなってんだ?って思いますよ(笑)。これができるのは『ONE PIECE』か『アンパンマン』だけじゃないですかねぇ(笑)。
――今回の映画で、いきなりそんな現場にメインキャラとして飛び込み、見事に大役を果たした名塚佳織さんとAdoさんのすごさを、今のお話であらためて感じました。このおふたりの起用の経緯は、どのようなものだったのでしょう?
谷口 ウタの歌唱を担当してくれたAdoさんに関しては、最初に原作者の尾田栄一郎さんから名前が出たんです。ただ、じつはそれ以前から、スタッフの間でもチラチラと「Adoさんにお願いできないかな」みたいな声はあったんですよ。そこに尾田さんからも彼女の名前が出たので「それでいこう!」と。やっぱり、なによりもウタというキャラクターに必要だったのは歌唱力。それもただきれいなだけではなくて、力強さがあって、なんとなく情念も感じられる……でも、いちばん核のところはピュアである歌声が必要だった。Adoさんの歌は、まさにそのイメージにピッタリだったんです。で、名塚さんはオーディションでした。

――オーディションではお芝居もですが、Adoさんの声質との近さも重視したのでしょうか? 歌としゃべりがとても自然につながっている印象でした。
谷口 声質が近い方を選んだというより、名塚さんと相談したうえで、できるだけ“Adoさんのクセ“を確認してもらったんです。物真似という意味じゃないですよ。Adoさんの生の声をそのまま再現すると、今度はルフィたちの芝居と合わなくなってくる。だから、ルフィたちの世界観とも合うように、名塚さんに芝居を調整してもらったんです。だからこれはもう、名塚さんの持っている技術の力ですね。彼女じゃないと、あそこまで合わせられなかったでしょう。それ以外で私がキャスティングで強く意識したのは、モブのキャラクター(羊飼いの少年・ヨルエカ役)を、梶(裕貴)君にやってもらおうかってことぐらい(笑)。
――ヨルエカが梶さんなのは谷口監督の意向なんですか?
谷口 基本は、それ以外もこちらの意向で組ませてもらっています。赤髪海賊団だけは今後のこともあるからテレビ班にお願いしましたが。で、ヨルエカの話ですが、モブとはいえ、尾田さんが描いて名前も決めたキャラなんですよね。新人を当てるわけにはいかないなと。で、「そういえば梶くん、『ONE PIECE』好きだったよな」と思い出して、お願いしました。あと、彼ならモブでキャスティングしても怒らないだろうと。でも、まさか事務所が受けてくれるとは思わなかったんです。あんなに主演作があるのにモブ役でもいいって(笑)。
――それもまた『ONE PIECE』だからこそできる破格のキャスティングですね(笑)。モブといえば、ロミィ役の新津ちせさんはどうだったんですか?
谷口 新津さんに関しては「子役がほしい」とプロデューサーにお願いしたんですよ。そうしたら、いろいろな条件を加味して新津さんを紹介してもらいました。彼女にやってもらえてよかったです。これからもっと伸びる、素養がある方だと感じました。
『ONE PIECE』の監督の依頼が来たのは3回目
――そもそも今回、谷口監督が東映アニメーションで仕事をすることが発表されたとき、大変驚きました。
谷口 そうなんですか? ここ数年、東映アニメーションは外部の監督さんをたまに呼ぶ流れがあって、たとえば、本郷みつる監督が『ワールドトリガー』でシリーズディレクターをされたりしていますよね。そうしたことを思えば、私としてはそこまで異例ではないのかなと。それに、じつは私のところに『ONE PIECE』の監督の依頼が来たのは、これで3回目なんですよ。

――そうなんですか。
谷口 さすがに3回目となると、これはもう明確にプロジェクトとしての目的があるのだろう、と。『ONE PIECE』という作品を、ここからさらに前に進めるために、何かを壊し、何かを足す……みたいな。そういった必要があって、また私に声をかけてくださったのではないか。プロデューサーと話をしていても、そうした決意が感じられたんです。だとしたら、私としてはお受けする前にとにかく尾田さんの許可をもらってほしい、と。私はTVシリーズが始まる前に一度、『ONE PIECE』の監督をやっている人間ですからね(※注:谷口はイベント「ジャンプ・スーパー・アニメツアー’98」用に、テレビアニメ化以前に制作されたアニメ『ONE PIECE 倒せ! 海賊ギャンザック』で監督を務めている)。そのときに何か失礼があって、「あいつとは二度と仕事では会いたくない」と思われているかもしれない(笑)。
――またまた(笑)。
谷口 そうしたら、すんなりとOKが出ました。それなら、もう問題は何もないわけです。あと、これは作業に入ってからわかったことで、どちらかというと結果論なんですけど、過去に私と縁のあった制作スタッフが近年、東映アニメーションさんにかなり合流していたんです。それもあって、監督として仕事をするうえでやりやすい環境であったのも、仕事を進めるうえでは大きかったですね。
監督として何を「壊し」何を「足す」のか
――「何かを壊し、何かを足す」というお話がありましたが、今回の『ONE PIECE FILM RED』では具体的にはどのような形で「何かを壊し、何かを足す」ことを実現しようとしたのでしょう?
谷口 まずいちばん大きかったのは、TVシリーズの『ONE PIECE』の歴史があまりにも長いことです。1000話を超えている。そうなると当然、今関わっているスタッフの大半は途中から参加しているわけです。すると「以前からこういう形でやっているので」というような「なんとなく」で進んでいる部分がどうしてもあるので、それを「壊す」。おそらく、そうしたルールは、作られた当時の事情に沿った何らかの理由があったと思うんです。でも、それが今でも通用するのかどうか。
――作品にも、それを取り巻く時代の空気にも変化はありますものね。
谷口 そうなったときにルールを疑うのは、作品の内部にいる人間だとなかなか難しい。やっぱり先輩方がずっとやってこられたことですから。そこで「これ、おかしくない? 変えちゃおうよ」みたいなことを気軽に言える人が必要になる。それがまず、私に求められたことでした。ただ、そうやって「壊す」だけでは、そのあとに作り上げられるものが、あくまでこれまでのやり方のバージョンアップになってしまうんですね。

――谷口監督のようなクリエイティブの力がある方ではなくても、ただ外部の人間であるだけで「壊す」ことはできますものね。
谷口 プロデューサーの目的が「壊す」だけなら、誰かが壊したあと、またそのまま東映アニメーションの方々が監督をやればいい。でも、今回は違う。つまり「足す」ことが必要なんですね。じつはそれが『ONE PIECE FILM RED』の、黒岩(勉)さんを交えた脚本打ち合わせの大きな議題でした。そこから「ウタ」という女の子を中心とした、歌を大きな軸に持った『ONE PIECE』の映画を作る流れになったんです。
――谷口監督が『ONE PIECE』を手がけるにあたって、シリーズの変えるべき点を「壊す」だけではなく、新たな魅力を「足す」うえで、やはりウタと歌の要素が大きかった。
谷口 とはいえ、歌をうたうキャラクターが今まで『ONE PIECE』にいなかったわけではないんですよ。だから、やるんだったらかなり派手に、ドーン!とやらないといけない。中途半端にこれまでの歌の要素とかぶってはいけないと考えて、『ONE PIECE FILM RED』のような仕込みになりました。ただ、これを提案するのは、切り札を出した感が強かったです。
――「切り札」ですか?
谷口 もともと尾田さんは歌が大好きなんですよ。だから、並々ならぬこだわりを持っている。その歌を提案するということは、尾田さんのすさまじいこだわりを受け止めることなんですね。黒岩さんと相談しながら「トータルで何曲ぐらい必要になるのか」「映画の何分の時点で曲が来れば、この展開が成立しうるのか」など、プロット作成と音楽を入れるタイミングの計算を同時並行で進めて、音楽の要素を映画の中に組み込んでいきました。その結果、脚本がフィックスして、絵コンテから映像が完成するまでも、かなり変則的な作業になりましたね。

――通常とは違う段取りだった?
谷口 今回は、映像を作っている最中にそのシーンの楽曲制作者にオファーして、曲を発注して……という流れで進めました。普通の作り方だと、ウタのライブシーンのようなパートは、曲を先にあげてもらって、それに合わせて映像を作るのですが、音楽と映像の作業が同時進行なんですよ。
――それは驚きです。
谷口 私もびっくりです(笑)。だからプロットの段階で、そのシーンで流れる楽曲の歌詞に必要な要素をまとめてもらいました。それをもとにシーンの絵のイメージを作りながら、尾田さんと音楽に詳しい集英社の原作メディア担当・高野健さんとで打ち合わせをしてもらって、どのアーティストがどのシーンを担当するのがいいのかを決めてもらい、私のほうに報告を入れてもらいながら割り振りを正式に決める。そして、それをもとにして、私のほうで映像の大きな流れをもとに楽曲発注の打ち合わせをアーティストサイドの方とさせてもらう……という流れを組みました。さらに楽曲の発注をしながら並行して、振り付け家のMIKIKOさんにも「こういうコンセプトの曲があがってくるので、それに合った振り付けをお願いしたい」と事前に下準備しておきました。

――混乱しそうなくらい複雑な工程だったんですね。
谷口 制作がそれに対して、きちんと応えてくれるだけの粘り腰がないとやれないことでした。東映アニメーションではない制作会社だったら、これは破綻したかもしれないですね。あまりにもイレギュラーな作り方なので。![]()
- 谷口悟朗
- たにぐちごろう 1966年生まれ。愛知県出身。日本映画学校からJ.C.STAFFに制作として入社。サンライズで演出家としての、Production I.Gで監督としてのキャリアをスタートさせる。『スケートリーディング☆スターズ』『バック・アロウ』他。