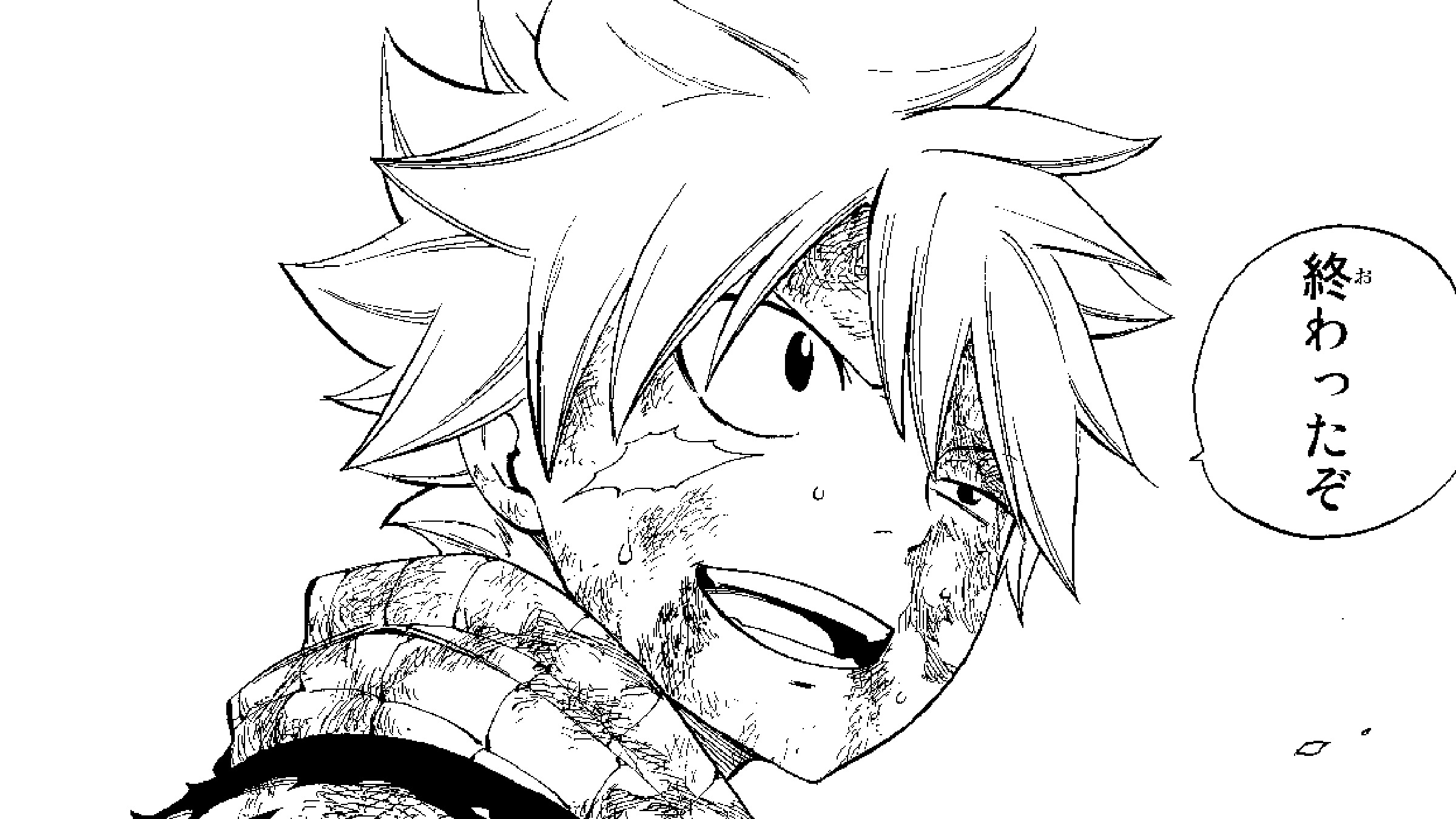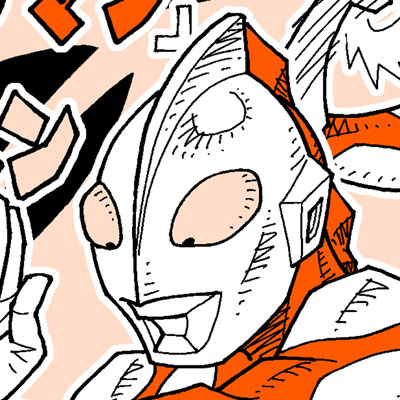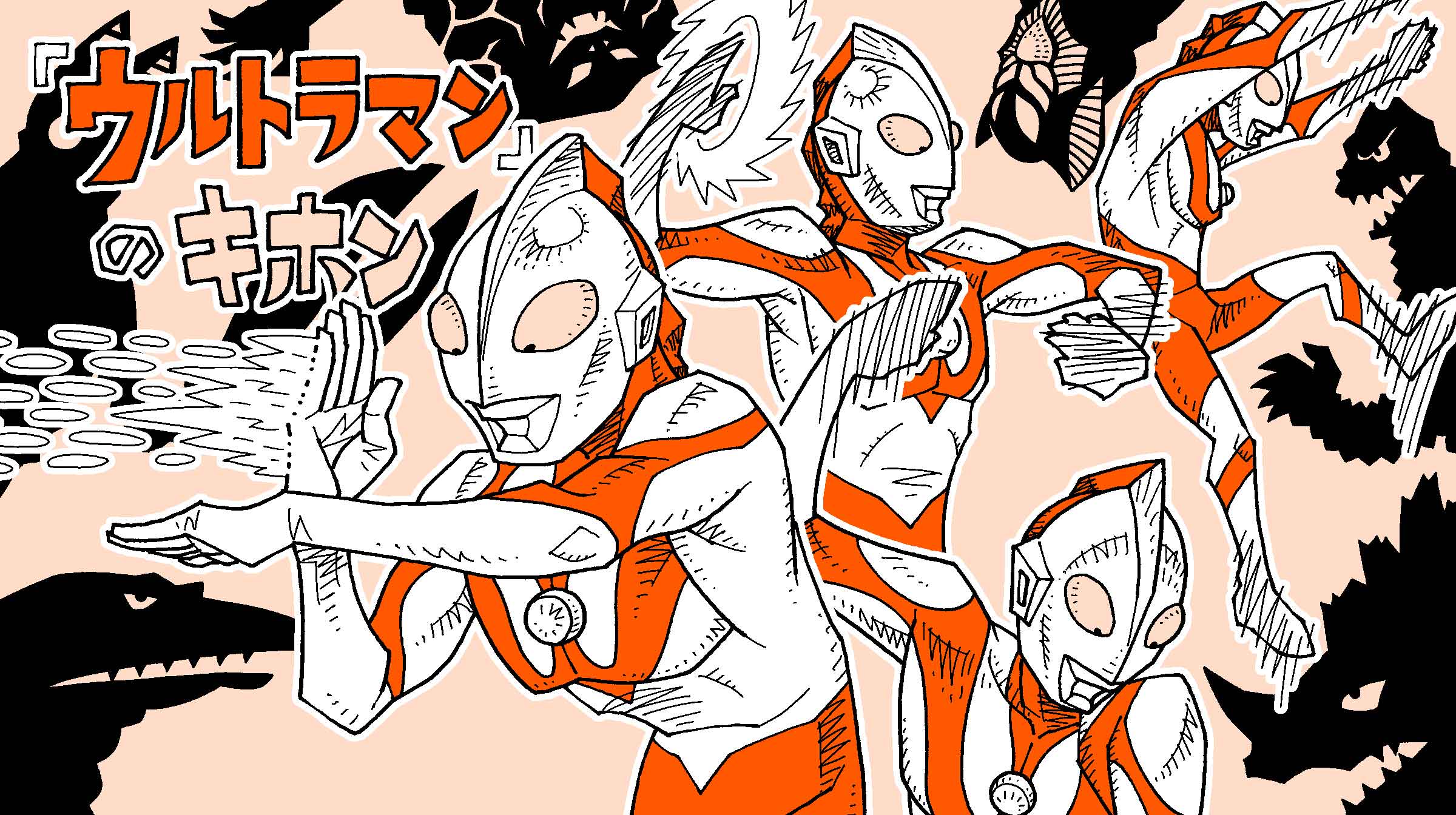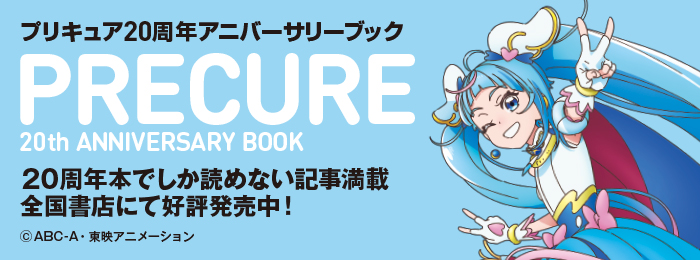小学生の頃からマンガ家になりたかった
――『FAIRY TAIL』完結、おめでとうございます! 足かけ11年の長期連載になりましたね。
真島 まさかこんなに長くなるとは、という感じです。その前の『RAVE』が6年続いたので、『FAIRY TAIL』は10巻くらいで完結すればいいなと思っていたんです。なので、当初考えていたよりも続いてしまったな、と(笑)。
――長いマラソンを走り抜けたあと、みたいな感じなんでしょうか?
真島 いや、全然そんなことはないです。毎週、思いつきでツギハギしていた世界観がいつの間にか大きくなって、それがようやく自分の中でまとまって完結を迎えたわけで、最初からマラソンをしようと思っていたわけではないですし、終わってみても「走り切った」という感覚はないですね。
――『FAIRY TAIL』についてはまた後ほど伺いたいのですが、まずは、真島先生とマンガとの出会いから聞いていきたいと思います。おじいちゃんが山で拾ってきたマンガを読んだのが、最初の出会いだそうですね。
真島 そうです。僕も祖父も長野県に住んでいたんですが、祖父が住んでいたのは本当に山の麓なんです。子供のときは何とも思わなかったんですけど、大人になってから訪ねてみたら、ビックリするくらい何もなかった(笑)。で、どういうわけか、おじいちゃんが山に捨ててある『週刊少年ジャンプ』を拾っては家に持って帰ってきて。しかも、定期的に捨てる人がいるのか、毎週続きが読めたんです(笑)。
――その頃、読んでいた作品で印象に残っているものというと?
真島 「おおっ!」と思ったのは『キン肉マン』です。最初に模写したのも『キン肉マン』。チラシの裏にコマを割って、同じように描いてみたり、「この超人とあの超人が戦うと、どっちが強いんだろう?」という、子供の妄想を絵にしていました。
――以来ずっと絵は描き続けていた?
真島 ずっと描いていました。友達があまりいなくて、ひとりで遊ぶのが好きだったんです。思春期に入ると、友達が増えたり恋人ができたりして交友関係は広がっていくんですけど、でも描くことだけはやめられなかったです。ノートにコマを割って連載みたいなものを作って、誰が読むわけでもないのに「続く」とか書いたりして。当時はゲームの『ドラゴンクエスト』が好きだったので、冒険ものばかり描いていました。
――マンガ家になろうと思ったのは、いつ頃のことなんでしょうか?
真島 小学生くらいのときには、既に「マンガ家になろう」と思っていました。何かターニングポイントがあったというより、気づいたらそう思い込んでいた感じで。あとは、中学か高校の進路相談のときですかね。改めて「マンガ家になる」と。
――なるほど。それで高校を卒業してから上京して専門学校に入るわけですね。
真島 高校の成績が悪かったので、大学に行くという選択肢は全くなくて。しかも、当時は専門学校を出ないとマンガ家になれないと思い込んでいて、それで誰にも相談せずに雑誌に載っていた専門学校に応募してしまったんです。
――ええっ、親にも相談せずに?
真島 はい(笑)。ウチはそんなに裕福じゃないんですけど、親に「東京に行きたいから、何とかお金を出してくれ」と頼み込んで。今思い返すと、親にはすごく迷惑をかけましたね。学校の先生も「マンガの専門学校に行く」と聞いたときには、さすがにキョトンとしていましたし(笑)。高校ではかなりの問題児だったので、まさかそいつの進路が最初に決まるとは、みたいな(笑)。
マンガを描くために東京へ
――『ましまえん』を読むと、そうして入った専門学校にもすぐに行かなくなってしまったそうですね。
真島 はい。田舎者にとって東京は楽しくて、毎日どこに出かけても新しい何かがある、みたいな感じで。新宿の夜の街にも感動しました。長野だったら、その時間には電気も何もついていないのに、この街はひと晩中遊べるのか!と(笑)。とはいえ、お金がないのでコマ劇場の前で夜中に弾き語りをしたり、友達とひと晩中しゃべっていたり。
――とにかく遊びまくっていた(笑)。
真島 ただ、そのとき付き合っていた彼女にフラれて、そこで初めて「何のために東京にきたのか?」と思ったんです。それが19歳の後半くらいの時期で。「そうだ、マンガを描くために東京にきたんじゃないか」と気持ちを入れ替えて、そのときに描いたものを『週刊少年マガジン』に持ち込むんです。
――原稿を完成させたのは、そのときが初めてですか?
真島 原稿自体は専門学校の課題などで描いたことはあったんですけど、30ページのマンガを描いたのは、そのときが初めてです。持ち込む先は絶対に少年誌だと思っていたんですけど、『週刊少年ジャンプ』にしようか、『週刊少年マガジン』にしようかで悩んでいて—確か『ジャンプ』には31ページという規定があって、一方の『マガジン』はページ数が自由なんですよ。それで、どちらでもいけるように31ページで描いた記憶があります。
――そのときの編集部の反応は……。
真島 舞台がファンタジー世界で、賞金稼ぎの話だったと思うんですけど、ボコボコに言われました(笑)。担当編集の松木さんは、口調は柔らかいんですけど、ズバズバ鋭いところを突いてくるんです。ただ、それが僕にはすごくよかった。新鮮だったんです。今までマンガを描いても、他人に批判されるということがなくて、友達に見せても「面白かった」「絵が上手い」としか言われない。だから、持ち込みで初めて自分の欠点という欠点を全部指摘してもらえて—例えば「女の子が可愛くない」って言われるんですけど、自分としては「ウソだろ!?俺の描く女の子は可愛いだろ!?」と思っているわけです。それが本当に悔しくて、言われたことを全部直して、もう一回持っていってやる、と。
――悔しさがバネになった。
真島 そう。それで、2日で新しいネームを作って、すぐに打ち合わせをしたいと電話を入れたのを覚えています。あとから聞くと、当時はあまりそういうことをする人がいなかったらしいんですけど。そのとき持っていったのが『MAGICIAN』のネームでした。
追い詰められて生まれた『RAVE』
――2本目のネームがデビュー作になったわけですね。
真島 きっと、打ち合わせで言われたことがすぐに吸収できたんだと思うんです。「マンガはこういう風に作ったほうがいい」「キャラクターはこんな風に立てたほうがいい」とか。若さもあったんでしょうけど、勢いでバーッと描いて。当時と比べると今のほうがマンガの技術は上がっているはずなのに、あんな風にはもう描けないですね。
――初連載作の『RAVE』は、それから約1年後に始まりました。
真島 『MAGICIAN』で新人賞をいただいてから、すぐ準備に入ったんですけど、ネームをやっていたのは半年くらいかな。とにかくその半年間は、ネームを描いていた記憶しかないです。僕はファンタジーをやりたかったんですが、『マガジン』編集部からOKが出ないだろうと思って、自分の中でブレーキをかけていました。
――確かに、当時の『マガジン』は、長期連載のファンタジーものがほとんどなかったですよね。
真島 とりあえず連載できれば何でもよかったので、現代ものの企画を出してみたりもするんですけど、なかなかOKが出ない。それで、あるとき試しに「ファンタジーをやってみたい」と言ってみたら、「いいね、真島くんはそういうのじゃないと」と。今の『マガジン』にはないことが、逆に武器になるんじゃないか、という話になったんです。
――『RAVE』は、どのあたりから企画を固めていったのでしょうか?
真島 錬金術師の話をやろうというところから始まって、確かそのときには既に〝石〟というアイデアがありました。『RAVE』に限らず、僕の作品にはよく出てくるんですが、石とか宝石のようなキラキラしたものになぜか惹かれるんです。ただ、ネームに関しては、描いて提出してはダメ、担当の言われた通りに直してもダメ、というのを半年間繰り返していて。何度も何度も直しているうちに、だんだん何が面白いのか僕も担当も、よくわからなくなってきた。
――新人作家あるあるですね。
真島 それで一度、企画を全部崩して、組み立て直しているんです。そのときに最終的に残したのは、「プルー」「ハル」「島」という3つの要素だけで(笑)。それで、改めて描き直したネームを担当に見せたら「すごく面白い!」と言ってもらえて、そこから連載につながりました。
――まさに追い詰められたところから、『RAVE』は出てきたわけですね。
真島 ナカジマは、その描き直しのときにわけがわからなさすぎて、勢いで付け足しちゃったキャラクターなんです。ネームを見てもらったときに、向こうのほうから担当の笑い声が聞こえてきて。なので、ナカジマにはすごく感謝しています(笑)。
面白いと思うところから描く
――基本的にはハルの成長を追いかけていくという、王道なスタイルのファンタジーになっていますね。
真島 そこもすごく気を使ったところで、当時『マガジン』にはファンタジーものの連載があまりなかったんです。つまり、読者がファンタジーに対して耐性がない。担当に「『ジャンプ』ならOKでしょう」と詰め寄ったこともありますし、「『ジャンプ』ではOKかもしれないけど『マガジン』ではダメだ」と言われたことも何度もありました。要するに、これまでバトルファンタジーを読んだことがない人を意識して描かなきゃダメだ、と。そこはすごく苦労したところだったんですけど、でも苦労した分、今の自分のマンガ技術の基礎になっていると思います。
――読者からの反応はいかがでしたか?
真島 始まったばかりのときは苦戦しました。手応えを感じるようになったのは、ジークハルトが出てきたあたりからです。あのあたりからだんだんと盛り返してきて、とにかくそのときに皆で話していたのは、出し惜しみするのは止めよう、と。後半の展開のために取っておいた伏線とか盛り上げようと思っていたシーンを、とにかく先に全部やる。面白いと思うシーンから突っ込んでいかないと、待っていたら連載が終わってしまう、と。
――相当な危機感があった。
真島 思いついているシーンをどんどん入れるようになってから、だんだんと調子がよくなってきたんです。なので、そのやり方は今でも続けています。面白いところから描くし、空っぽになったら、そのときにまた考えればいいや、と。今ではちょっと、自分の座右の銘っぽくなっています。