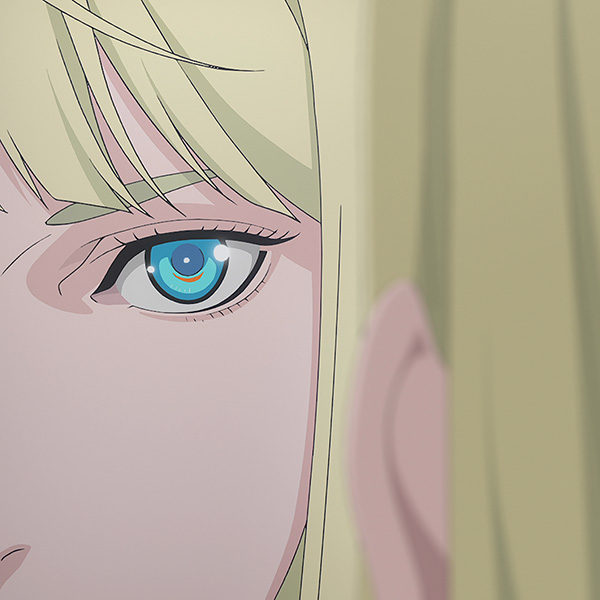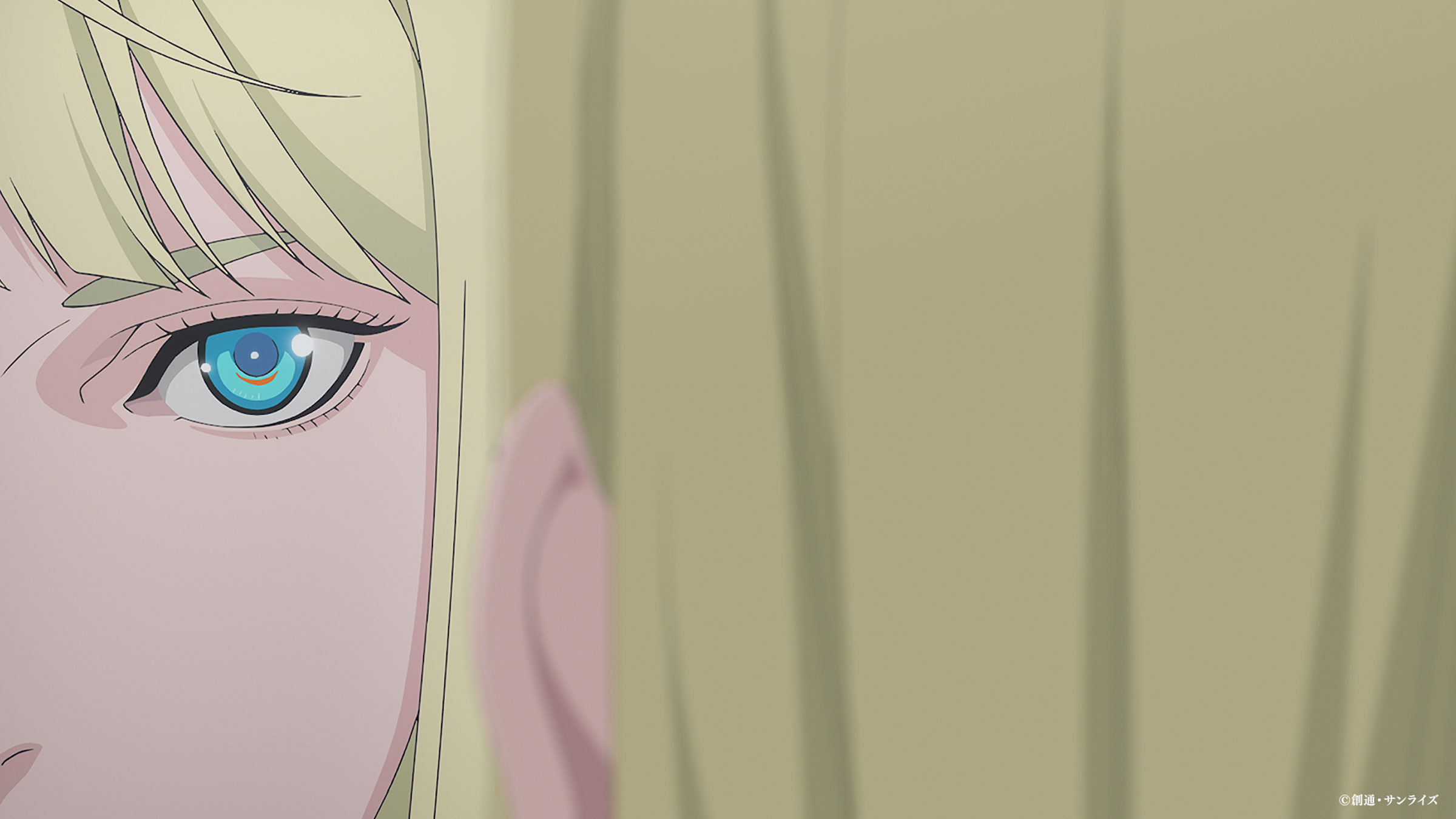飛雄馬の呪縛とそこからの脱却
――星飛雄馬を演じるための役作りとして、実際にキャッチボールをしたとのことですが、これはどういう効果があるのでしょうか。
古谷 そうした役作りをするのは、僕が経験主義だというところが大きいと思います。飛雄馬のときは弟とキャッチボールをすることで、ボールを投げるときの息遣いや身体の動かし方をおぼえようとしました。子役のときから顔出しで演技をしていたこともあって、身体で表現することに慣れていたのもあるでしょう。実際に俳優さんは自分の身体を使って演技をするわけで、頭で考えなくても身体を動かせば自然な息遣いが表現できる。それが声の演技だけになったときでも、求められるニュアンスや息遣いというのは、実際に自分が身体を動かした結果として出るものが正しいはずですよね。だから実際にやってみて、耳でおぼえて、アフレコで再現することをしていたんです。身体を動かさなくても再現できるように、まずは身体を動かすということですね。僕は2回ほど肋骨を骨折しているんですが、その痛みから出るうめき声ですら「これだ!」と思っておぼえるようにしていました。『聖闘士星矢』ではよく殴られていましたから(笑)、そういうときに使えると思ったんです。僕は日常生活の体験すべてが勉強になる、声優の芝居には役に立つと思います。たとえば、本を読んで感動したときの嗚咽、胸の苦しさ、または恐怖を感じたときには足から震えが来るなどの経験は、すべて仕事に置き換えられる。だから、僕は感情表現だけでなく、痛みや恐怖も含めて経験主義であると言えますね。また、『機動戦士ガンダム』くらいから、作品や役柄の情報を収集するようにもなりました。80年代はアニメブームだったこともあり、アニメ雑誌が多数出版されていましたから、そういった情報を入手したり、設定資料集や原作本などからも情報収集をして、キャラクターを把握していく。頭の中でそれらの情報を整理してから、こういう声やしゃべり方がいいのではないかという、緻密な役作りをするようになりました。入手可能な情報はなるべく目を通すようにしているので、現在のようにインターネットが発達している世の中は便利ですね。

――古谷さんのキャリアの中で大きな位置を占める星飛雄馬ですが、その影響力が大きすぎたということはなかったのでしょうか。
古谷 あまりにも人気が出て国民的に知られるようになったこともあって、星飛雄馬のイメージが自分の中でも大きくなったのは間違いありません。学業優先のために一時的に声優業から離れましたが、復帰してからも熱血キャラやロボットアニメの主人公を演じることが多くなっていました。熱血ヒーローや正義感の強いロボットアニメの主人公は、どうしてもセリフ自体が似通ることが多いわけで、それは飛雄馬のしゃべり方に似てしまう。違う声を出さなければならない、違うキャラクターを演じなければならないというジレンマに陥りながらも、セリフの言い回しは飛雄馬に似てしまう。日常会話の演技では差別化できても、敵に立ち向かうシーンや声を張るシーンでどうしても似てしまうのが自分でも不満でした。ちょうどその頃、加藤精三さんが仕事仲間を集めて民話の朗読会というのを開いていました。『巨人の星』からの縁で、僕も加藤さんのもとで勉強をしたくてその会に入りました。民話の語りというのは、たとえば、お爺ちゃんお婆ちゃんが孫に聞かせるようなイメージで、普通の朗読とは違って地の文にも表情をつけてしゃべる必要があるんです。さらに登場人物もすべて演じ分けなければならないから、普段のアニメの仕事なら僕には絶対に来ないであろう役柄も演じなければならない。ここでさまざまなキャラクターを演じ分ける勉強をさせていただいたことが、その後の声優の芝居に大きな影響があったと思っています。この経験がなかったら、アムロは演じられなかったかもしれないです。
アムロ・レイとの出会い
――『機動戦士ガンダム』の主人公、アムロ・レイ役に選ばれたのはどういう経緯だったのでしょうか?
古谷 やはり音響監督の松浦典良さんの影響が大きいです。松浦さんとは『おれは鉄兵』(1977年)からのお付き合いで、スタッフ間のチームワークをとても大事にする方でした。当時のTVシリーズ作品では、スタッフとキャスト総勢で旅行することが多かったのですが、松浦さんはその旅行中に声優たちの普段の姿を観察していたそうです。日常の様子を見ながら、この声優にはどういう役が適任かを考えていた。そんなときに『機動戦士ガンダム』のオーディションに呼んでいただいたのが最初です。そこは松浦さんの仕事場で、すでにキャラクター表やシナリオもできていたし、第1話の「ガンダム大地に立つ!!」の映像も見ました。そこでアムロのセリフをいくつか収録して、オーディションになったという流れですね。余談ですけど、このときに池田秀一さんもアムロのオーディションを受けていたそうです。