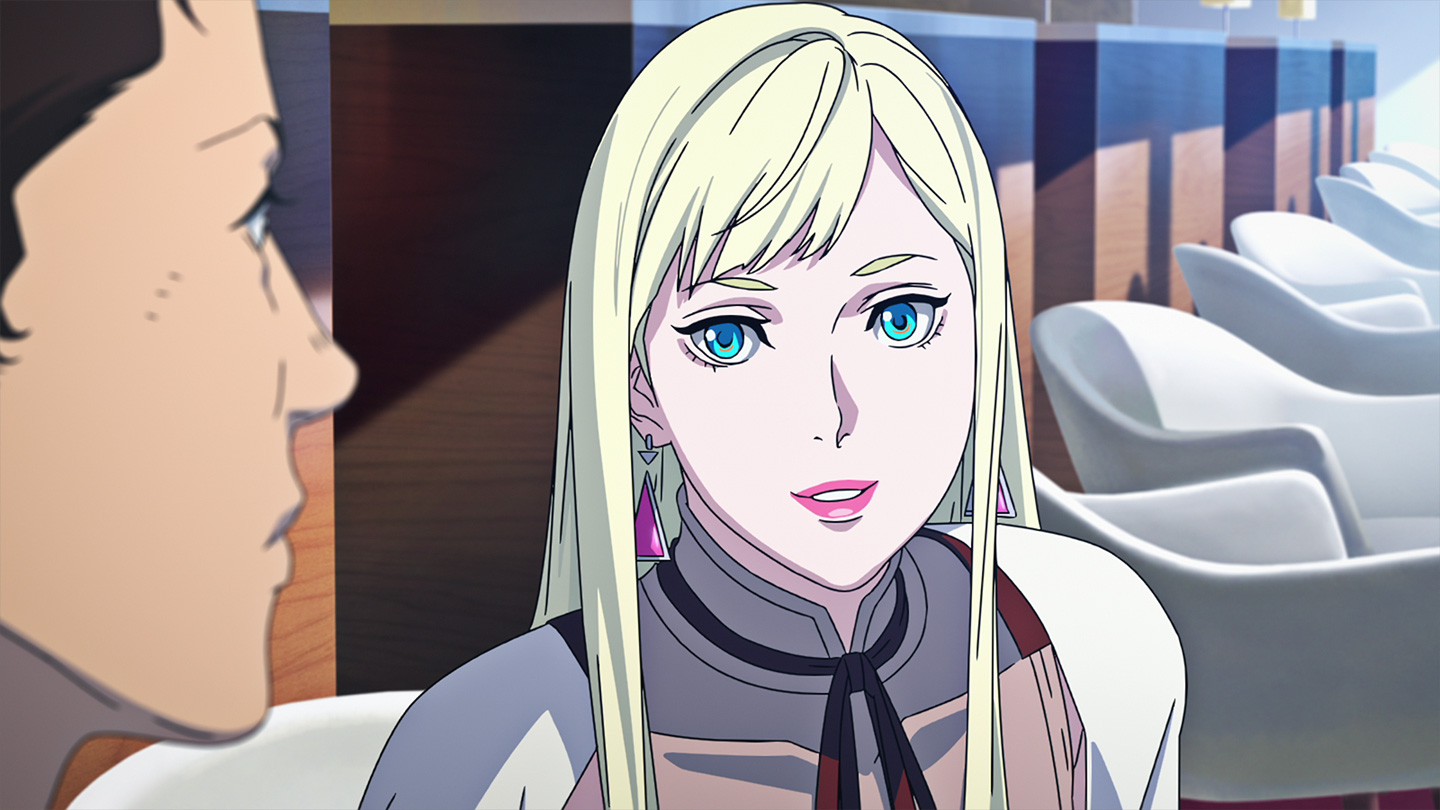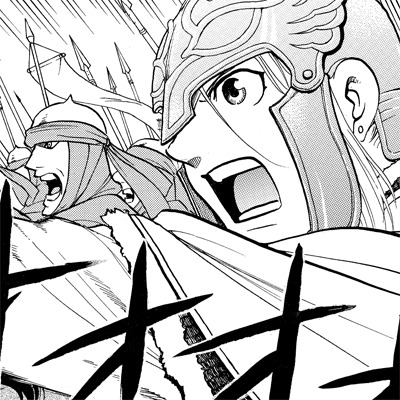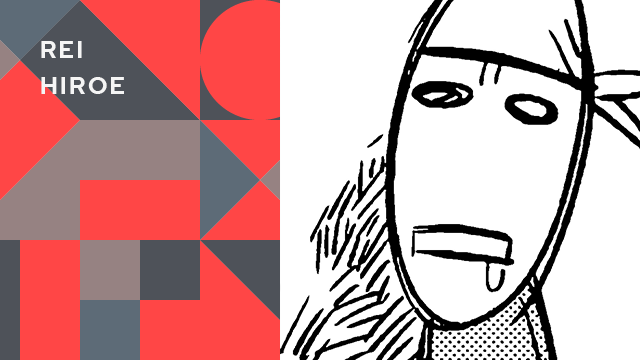マンガ家に惹かれるも、学校卒業後は海外へ
――最初に買ったマンガが何だったか、おぼえていますか?
雲田 マンガを初めて親に買ってもらったのは、小学生くらいのときですね。お姫様が出てくるような往年の少女マンガを古本屋で買ってもらった記憶があります。今となっては、なぜそれが欲しかったのかおぼえていないのですが、でもいまだに取ってあります。それから、小学校の高学年になると『りぼん』や『なかよし』を読むようになって。中学生のときに萩尾望都先生を読んで、そこから「過去のマンガが面白いな」と思って、いろいろと読み始めました。その頃はまだ、普通の書店で萩尾先生の全集が手に入りましたし、『トーマの心臓』もフラワーコミックス版が置いてあって。あとは手塚治虫先生など、トキワ荘の先生がたの作品を読んで、素直に「いいものだなあ」と楽しんでいました。
――その影響で、マンガを描き始めるように?
雲田 コマを割ってマンガを描き始めるのはずいぶん遅くて、20歳を過ぎてからなんです。ただ、絵を描くこと自体は好きで、子供の頃からオリジナルのキャラクターを描いたり、あとは芸能人の似顔絵を描いたりしていました。
――その頃、ハマっていた芸能人というと誰でしょう?
雲田 そのとき流行っていたアイドルの似顔絵を描いて友達にあげると喜ばれるんですよ(笑)。小学生の頃だとジャニーズのアイドルとか。中学校に入ったら、ユニコーンやTM NETWORK、あと小室哲哉さんを聞いている友達が多かったので、その人たちを描いたりとか。喜んでもらえることがうれしくて描いていました。
――当時、「マンガ家になりたい」という気持ちはあったのでしょうか?
雲田 読者としてマンガは大好きなので、なんとなく「憧れだな」という気持ちはあったんですけど、その時点でまだ一度もマンガを描いたことがなかったので(笑)。そもそもどうやって描けばいいのかもわからないし、今みたいにネットが発達していたわけでもなかったですしね。なので、高校を卒業したあとは東京にある美術の専門学校に進んで、デザインの勉強をしていました。
――では、そのときに地元の栃木から上京して来たんですね。
雲田 その専門学校の時代だけ、東京にいました。ただ、その学校にはいわゆる「オタク」な人がまったくいなくて、私がマンガっぽいイラストを描いて提出すると「なんでマンガの絵なの?」ってよく聞かれていました(笑)。今のようにオタクの市民権があったわけではないですから、私も細々と……(笑)。マンガ読みの人も、オタクというよりはむしろサブカルっぽい人が多かったですね。
――当時だと『月刊漫画ガロ』とか?
雲田 そうですね。で、そんな学生時代が終わり、今度はニュージーランドに行きました。専門学校を卒業して、なんとなく、外の世界を見ておいたほうがよさそうだなと思って、ワーキングホリデーで。
――就職をしようとは思わなかった?
雲田 いわゆる就職氷河期で、イヤになっちゃったんです(笑)。まわりの友人も苦労している人が多かったので、仕方ないかなと思って。ニュージーランド行きも「なんとかなる気がする」という、それだけで決断しました(笑)。
――(笑)。では、その後、専門学校を卒業してすぐに海外へ?
雲田 実際は、ニュージーランドに行くまでにお金を貯めなきゃいけなかったりもして、出発までにけっこう時間がかかったんですけど、最終的にあちらで1年暮らしました。そのときに、これまで身近にあった日本の文化が、きっぱりと断たれるんです。行く前はゲームでよく遊んでいたんですけど、もちろん向こうではやれませんし、マンガもまったく売っていないので、読まなくても平気になって、アウトドア活動などをしていました。それはそれで、まあ楽しかったんですよ。結局、日本に戻ってからマンガ読みだけは復活しました。
帰国後に出会った落語に衝撃を受けた
――ニュージーランドに行って得たものはありましたか?
雲田 自分は日本の文化をまったく知らなかったな、と。そのことに気づかされたんですよ。「日本ってどんな国なの?」とか「日本は、何が面白いの?」って聞かれても、答えられなかったんですよね。それがきっかけなのか、帰国してから江戸時代のモノだったり、日本の昔のことに興味が向くようになったんです。ちょうどその頃、大河ドラマの『新選組!』が放送されていたので、それにハマったり。あとは、みなもと太郎先生の『風雲児たち』を読んで江戸時代のことを学んだり。
――海外に出たことで、逆に日本的なモノに興味を抱くようになった。
雲田 そうなんです。で、江戸時代のモノや文化をいろいろと見ているうちに、落語と出会って衝撃を受けて……。だから意外とふわっと、今につながっているんですよね。
――ニュージーランドから帰国したあとは、何をしていたんでしょうか?
雲田 もう23〜24歳になっていたと思うんですけど、地元の栃木に戻っても、デザイン系の仕事があるわけもなく。「どうしたらいいんだろうな」と思いつつ、アルバイトをしながら遊んでいましたね(笑)。ただ、その頃からようやくインターネットが普及してきて、同じ趣味の友達ができ始めたんです。相変わらず、好きな芸能人の似顔絵を描くことが多かったんですが、そこからつながって、友達もできて、同人誌を始めて。
――ああ、なるほど。
雲田 描いた絵をファックスで送りあったり、当時はまだそんな時代だったんですけど(笑)。そうするとただのイラストよりも、4コマみたいにコマ割りをして、セリフを付けたもののほうがウケがいいんです。原始人が初めて絵を描き始めた、みたいな感じでマンガを描き始めて、そこから徐々にページを増やしてマンガに慣れていきました。
現場での経験をすべて同人誌に注いでいた
――そうやって同人活動をしているなかで、マンガ家のアシスタントの声がかかったんですね。
雲田 そうです。同人活動で知り合った友達のマンガ家さんが『BE・LOVE』で描いていらして、そのツテで石塚夢見先生のアシスタントをさせてもらうことになったんです。当時、自分のマンガは鉛筆で描いていて、丸ペンを使ったこともなかったので、それを教わるような極初歩的なところから始めさせていただきました。そうして、だんだんとマンガが身近になってきて、マンガ家になる夢も現実的になってきたんです。
――アシスタントはどれくらい続けていたんでしょう?
雲田 商業誌でデビューしたのが2008年なので、その前の3〜4年ですかね。アシスタントをしながら「投稿しなきゃなあ」と思いつつ、でも同人誌が楽しくて、そっちが忙しくてなかなか……(笑)。最初の頃はパースも何もわからないし、得意だと思っていた絵がプロの世界ではまったく通用しなかったので、かなりペシャンコになりました。でも、現場に行けば勉強になるし、描けるようになることが楽しかったので「絶対に何かつかめるはずだ」とも思っていて。それでやっと、ストーリーものの描き方をなんとなくつかんでいって、それらすべてを同人活動に注いでいました。投稿作を描けよっていう(笑)。
――(笑)。そこから、最初の短編集『窓辺の君』にまとめられるような初期短編につながっていくんでしょうか?
雲田 東京漫画社の編集さんが同人誌を読んでくださって、運良くお声がけいただきました。デビューはBLのアンソロジーで、毎回テーマが設けられていたんです。「職業カタログ」「リーマンカタログ」みたいな感じで縛りがあったので、最初はとてもありがたかったです。
――とはいえ、いきなり24ページを描くのは大変な気もするんですが……。
雲田 その頃は、ネタが膨れすぎて削るほうが大変でした。同人誌で鍛えすぎましたね(笑)。最初の短編(『窓辺の君』)を読んでいただければわかるんですけど、ギュウギュウなんですよ。今考えると、70ページくらいのボリュームがあるお話をギュッと圧縮して。雑誌に掲載されるとダメな点がよく見えるので、気づいたところをノートに書いて、研究していました。
リアルな話よりも、ロマンを感じる世界を描きたい
――ひとつ共通していると思ったのは、雲田先生の作品は、舞台設定が少し前というか、現代そのままという感じではないですよね。
雲田 現代が舞台なんですけど、少しロマンを取り入れて描く、というのは意識してやっているところですね。リアルな現実が反映されているものよりも、少しファンタジーなくらいが私にはちょうどいいんです。
――なぜなんでしょう?
雲田 そのほうが性に合っているといいますか、現実的な話よりも、自分が「いいな」と思う世界を描きたい。そういう気持ちが強いんだと思います。現実にありそうな話は、読む分には楽しいんですけど、いざ自分が描くとなると楽しくなくなってしまうんです。マンガ作業は大変なので、せめて楽しく描きたいといいますか。それと、作品の世界観から全部作りたいという気持ちがあって、だからちょっとロマンチックすぎるくらいのものが好きなんでしょうね。
――絵柄的に影響を受けた作家さんはいるんでしょうか?
雲田 マンガの文法みたいなものは、石塚先生の影響をたっぷり受けていると思います。絵柄そのものは、特定の作家さんの影響というよりは、友達に描いていた似顔絵の経験のほうが大きいのかな、と思います。実在する人を観察して、デフォルメするっていう。生身の人間を見ていると「ここがいいな」と思う部分があって――その髪質だったり体型の違いを描き分けたくなるんですよね。その結果、こういう絵になっていったのかな、って。