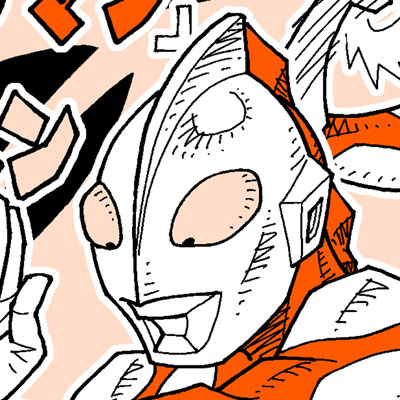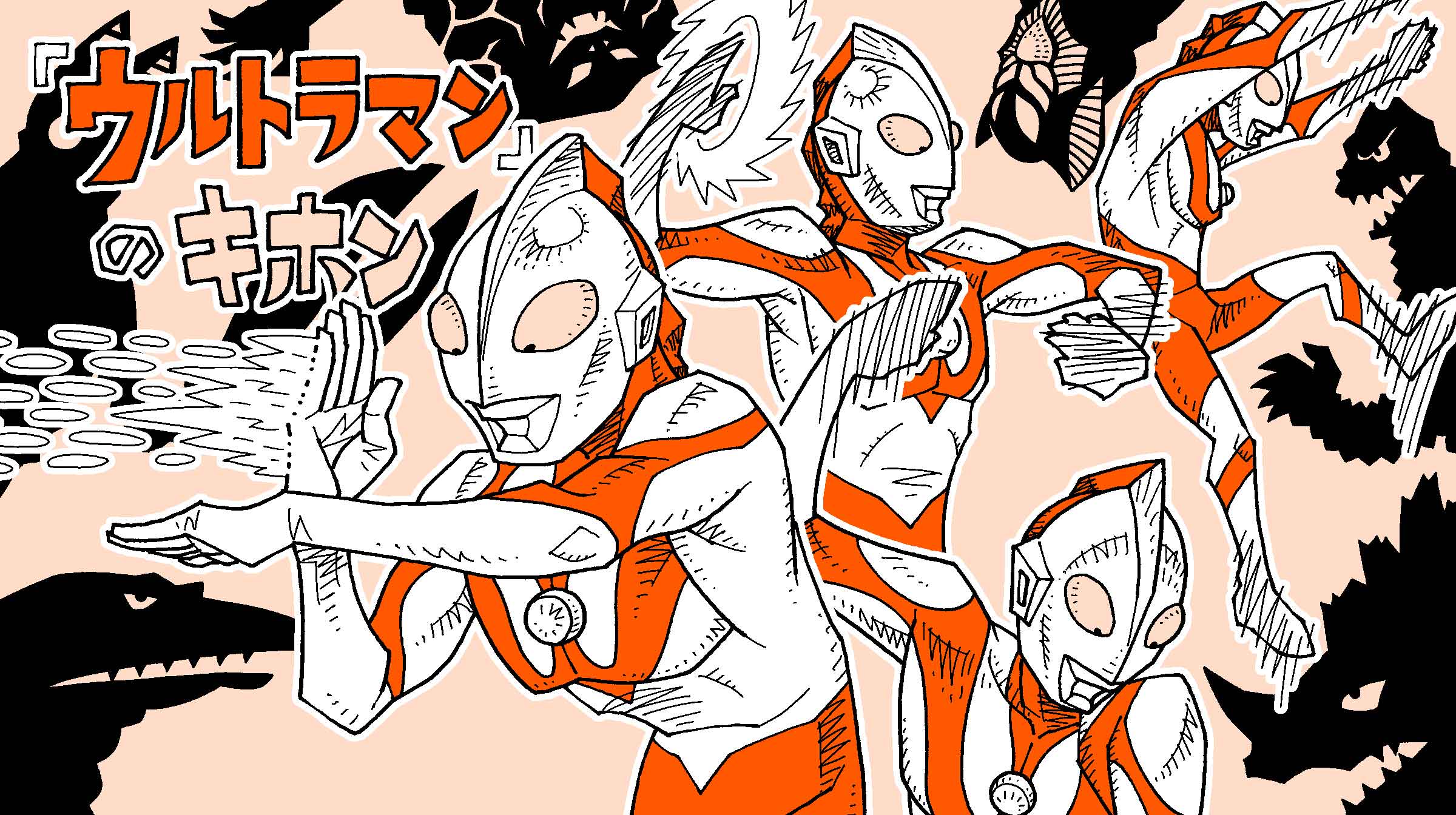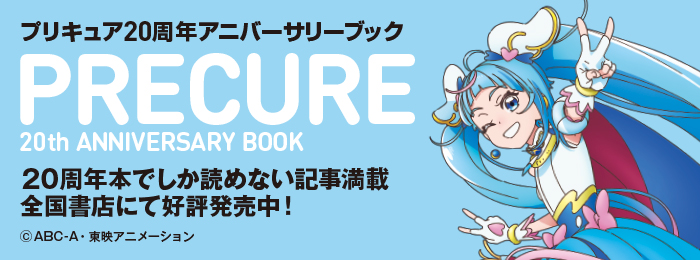物語と寄り添うのではなく、あえて距離を取った音楽を作る
――3本目は、フル3DCGで制作されたアニメ『宝石の国』です。藤澤さんが劇伴を担当している作品でもありますね。
藤澤 これまでの2本で話してきたように、僕はずっと「物語やキャラクターに寄り添うかたちで音楽が存在するのがいい劇伴」という価値観で仕事をしてきました。ただ、『宝石の国』はの劇伴は異質で、物語やキャラクターから距離をとって制作することになりました。これまで人の生き様に引っ張られて音楽を生み出してきたのに、『宝石の国』のキャラクターは人ではなく人型の生命体であり、生き様とは異なる別の何かを抱えているんです。
――それを踏まえて、価値観を転換する必要があったと。
藤澤 当初はそれまでと同じ感覚で作業を進めていたのですが、京極(尚彦)監督やスタッフと話し合うなかで、この作品の世界観を表現するには根本的に作り方を変えなければいけないのではないかという結論に至って、劇伴も2回ほど、まるまる作り直しています。物語から離れて音楽を作るとはどういうことかを考えていくなかで、自分の内面から何かを導き出さねば、という事実に気がつきました。
――自身の内面をさらけ出さないと、物語との距離が保てなくなる。
藤澤 そうです。『宝石の国』の世界観を情報としては取り入れつつ、音楽が距離を取って対峙するためには、それしか方法がありませんでした。例外として、ストーリーのキーポイントとなるアンタークチサイトがさらわれるパートは感情に寄せましたが、それ以外は客観的な視点で作ることを意識しました。
――自分の内面と向き合う作業は難しかったですか?
藤澤 物語に添わせるのではなく、作品の世界からヒントをもらいながら自分の内側をさらけ出す作業は、まるで自分と戦っているかのようで消耗しました。そういう意味でも、すごく印象に残っている仕事ですね。後に『少女☆歌劇 レヴュースタァライト』の劇伴を作ったときにも似たような感覚を味わいました。あの作品も残酷さと美しさを持ち合わせていましたし、『宝石の国』での取り組み方がかなり参考になりましたね。
――そのあたりは『ラブライブ!』で一緒に仕事をした京極監督や音響監督の長崎行男さんとの仕事だったからこそできた面もあったのでしょうか?
藤澤 そうですね。『宝石の国』では、京極さんも長崎さんもこちらがやりたい音楽を許容してくださったように思います。その他では東宝の小林(健樹)プロデューサーも手厚くサポートしてくださって、いろいろアイデアを出していただきました。
映像の質感と音楽の関係を考えるきっかけになった
――音楽的にはストリングスとピアノがメインにありながら、非西洋的なパーカッションが導入されているなど、サウンド面からもチャレンジ精神がうかがえます。
藤澤 『宝石の国』の世界は、人間社会が崩壊してから何千年と時間が経過していて、その間に文明もめちゃくちゃになっているわけです。宝石である彼らが使う道具などは人間が生み出した文明のものですが、だからといって人間と同じように使えるかと言えばそうじゃない。そうした存在のいびつさや混濁した文化を、ガムラン(インドネシアの民族音楽)と弦楽器を混ぜたり、西洋楽器にジャンベ(西アフリカの打楽器)を混ぜたりすることで表現できればと思っていました。ガムランと弦はキーとピッチ(音程)の問題でとても相性が悪いのですが(笑)。
――録音では、フィルムスコアリング(映像に合わせて音を録音する手法)も採り入れられたと聞きました。
藤澤 最初はすべての曲をそうしようという話もあったのですが、レコ―ディグやアニメ制作の都合もあって30曲程度をメニュー(音楽の発注表)に合わせて制作しています。それらの楽曲は編集しやすいようにパラデータになっていて、必要になれば曲と曲をつなぐ部分をさらに追加でレコーディングするような体制でした。なので、通常の作品のように「この曲をこの場面まで使う」といった方式ではなく、曲の中から映像に必要な部分を抽出して編集していく、手間がかかるやり方でした。エディット自体は小林さんが行っていて、それを僕が監修してダビングに持ち込んでいますね。フィルムスコアリングはシリーズの後半で実現して、アンタークチサイトがさらわれるシーンやラストシーンでは、動きと尺が把握できる映像をいただいて、そこに合わせて書き下ろしました。『宝石の国』はプレスコ(先にキャストの声を収録する方式)だったので、セリフも入っていましたね。
――なるほど。そういう意味では、かなり手間のかかる難解な作業であったと。
藤澤 今でも、アニメのあとの物語に音楽を付けるなら――と考えることもあるくらい、思い入れも深いです。これまでと同様、あの世界をずっと外から見続けるのか、フォスフォフィライトにフォーカスを当てていくのか。音楽を制作する上で作品を見ていく視点は『宝石の国』以降、間違いなく増えました。音と映像の関係性を考えるきっかけにもなって。『宝石の国』のCGで作られた映像は、あれだけ滑らかに動きつつも硬さがきちんと出ていますよね。じゃあ、音楽的にはハードな音を付けることで硬さを補完しよう、とか。キャラクターや世界観からは距離を置くけど、映像の質感には合わせるといったことも考えていました。
――映像と音と物語の根本的な関係性をあらためて突き詰める作業だったんですね。
藤澤 とくにアニメーションの音楽の場合、実写映画と比べて情報の補完性を高める必要があるのですが、だからといって、サイバーなSFならシンセサイザーで、ハートフルならオーケストラで、とセオリー通りに収めなくてもいいんです。その補完性を高める手法は他にもある、ということは、『宝石の国』の現場を経験したから意識できたことだと思います。![]()
KATARIBE Profile

藤澤慶昌
作曲家
ふじさわよしあき 1981年生まれ。福岡県出身。ファイブエイス所属の作曲・編曲家。2006年から作家事務所に所属し、音楽家として本格的に始動。『電波女と青春男』で劇伴デビュー。2012年に現事務所へと移籍し、多くのアニメ作品に劇伴作家として参加している。近作に『連盟空軍航空魔法音楽隊ルミナスウィッチーズ』『スパイ教室』など。