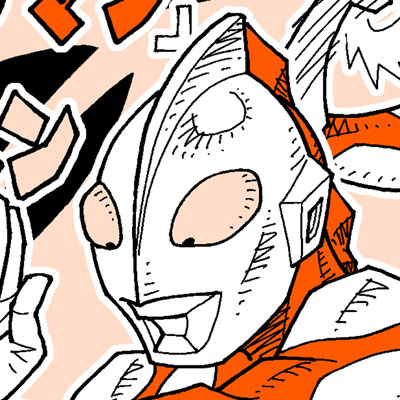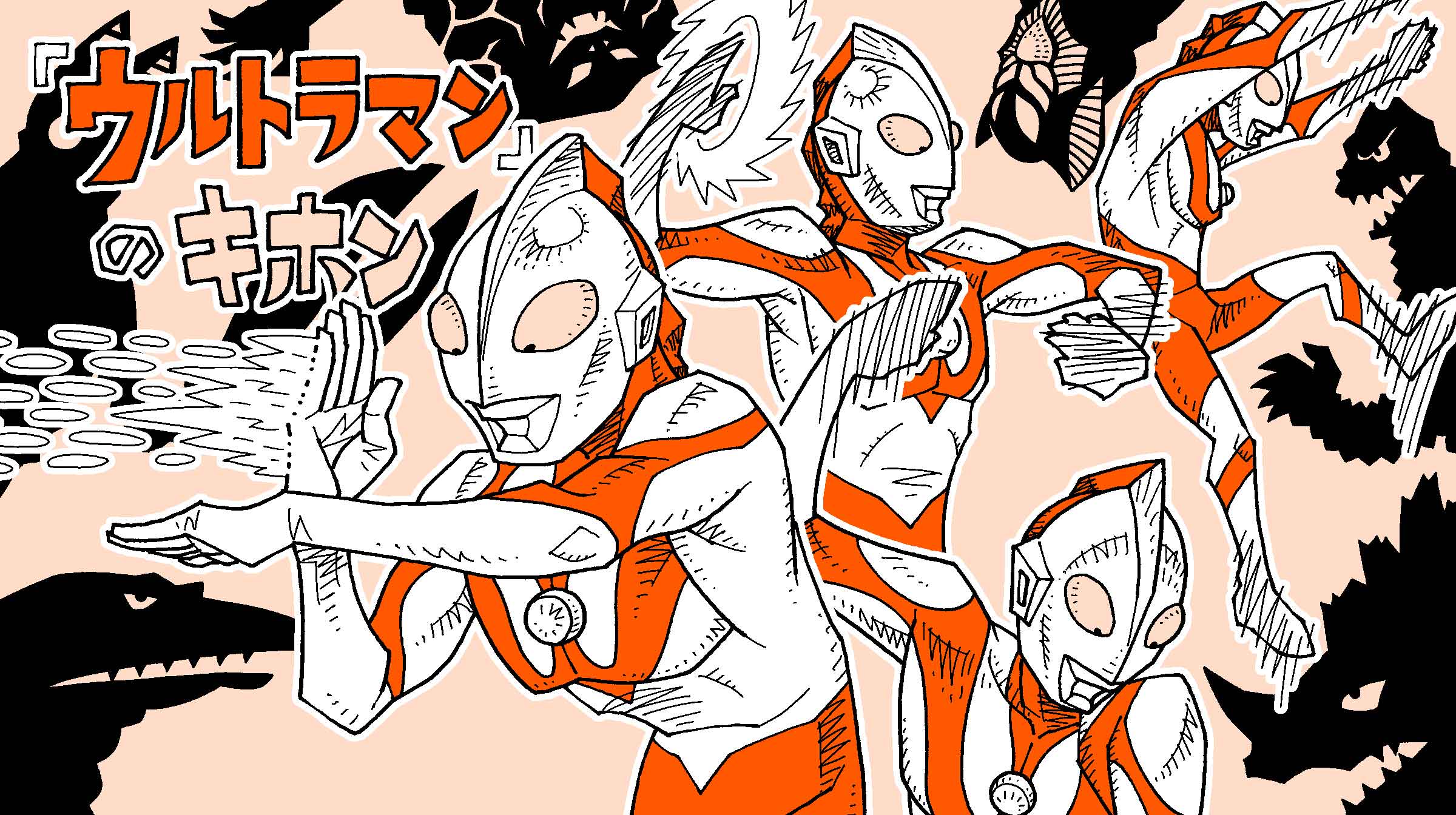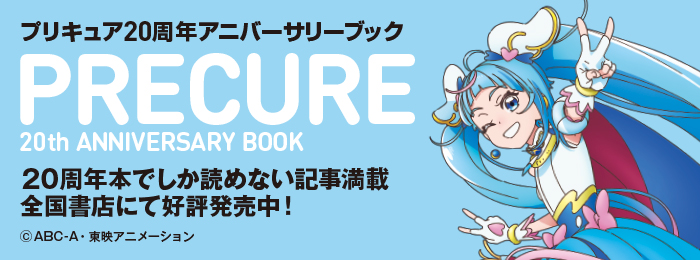借金返済のため、賞金狙いでマンガ賞に応募
――最初に触れたマンガは何でしたか?
大暮 『ジャンプ』作品です。いつも行っていた理髪店に『週刊少年ジャンプ』が置いてあって、それを読むのが最大の楽しみでした。『キン肉マン』や『こちら葛飾区亀有公園前派出所』、あとは『リングにかけろ』『キャッツ・アイ』『ストップ!!ひばりくん!』とか。最初に自分でマンガを買ったのは中学生のときで、たぶん、士郎正宗さんの作品だったと思います。『ドミニオン』が好きだったんですよ。その頃から急速に、マニアックな方向に振れていった記憶があります。
――なかでも強く影響を受けたと思う作品を挙げるとするなら?
大暮 『ジャンプ』作品だと『リングにかけろ』と『北斗の拳』、あとは先ほども名前を挙げましたが、士郎正宗さんの作品と『デビルマン』。最初に読んだ永井豪先生の作品は小学校のときの『凄ノ王』なんですけど、そこからさかのぼって『デビルマン』にたどり着きました。『デビルマン』はやっぱりラストがすごいじゃないですか。あれが軽いトラウマになって……。そこで受けた影響はかなり大きいと思います。
――マンガを描き始めたきっかけは?
大暮 幼稚園ぐらいのときから、家にある黒板に毎日、落書きをしていて。それが習慣になって、落書き自体はずっとしていました。中学生あたりからはマンガの真似事のようなものを描き始めるんですけど、初めて最後まで描き切ったのはデビュー作になった投稿作品。19歳くらいのときですね。
――高校卒業後、大暮先生は一旦、就職しているんですよね。
大暮 高校生の頃は画家になりたかったのですが、経済的な理由もあって断念して、画材屋に就職しました。ただ、その頃にパチンコにハマって借金が膨らんでしまい……。その返済のため、賞金狙いでマンガ賞に応募したのが「マンガ家になる」タイミングだったのかな(笑)。言葉にすると舐めていますけど、当時の貧乏っぷりは本当にハンパなかったんです。給与はパチンコに吸い取られていっさい手元に残らない。で、お金がないから空いた時間にやることがなくて、それで仕方なく絵を描いていたという現実もありました。
――なんというか、スタートラインの状況がすさまじいですね(笑)。
大暮 当時の貧乏エピソードなら死ぬほどあります。カーテンを買うお金がなくて、しかも部屋が1階だったのでずっと外から丸見えだったり(笑)、毎日70円のうどん一杯だけで半月生き延びたり、牛乳だけでひと月過ごしたり。そのときは流石に体調を壊しまして、「これはまずい」ということでパチンコからスロットに移行して(笑)。スロットの解析とか勝ち方を猛勉強して、最低限の生活ができる程度くらいは勝てるようになりました。
11日間で115ページを描き下ろした『BURN–UP W』
――(笑)。そして、最初の連載となったのが『BURN–UP W』でした。これは同名アニメのコミカライズですね。
大暮 白夜書房の担当編集経由で声をかけていただきました。掲載誌だった『月刊少年キャプテン』は『強殖装甲ガイバー』とか『トライガン』が掲載されている雑誌なので、同じ本に載れるなんてスゴい!と。ただ、最初に「好きにしていい」と言われてこちらから出したものがわりとシリアスな内容で。そうしたら「もっとコミカライズらしい方向で」と言われて、今の方向性のものに描き直したんです。そのことがかなりストレスで、連載自体、雑誌の休刊にともなって2回で打ち切りになったのですが、そうでなくても長くは続けられなかったんじゃないかな、と思いますね。
――連載分と描き下ろしを加えた単行本が、すぐあとに発売されていますね。
大暮 連載分だけだと単行本の規定枚数に130ページほど足りなくて。しかも「単行本を来月出す」という話がいきなりきて、締め切りまで2週間もない。結局、11日間で115ページを描き下ろすことになったのですが、これがあとにも先にも僕の最速記録です。
――まさに突貫作業だった。
大暮 単純な話、1時間でペン入れをして、次の1時間で形にしなきゃいけない。しかも、アシスタントさんを使いながら自分の作業も並行してやること自体、初めての経験で。同じことを今やれと言われても絶対にできないです。逆に言えば、自分の上限を試すことができた仕事で「ここでちょっとでもつまずくとダメだ」という、レッドラインがわかったというか。
――もう少し具体的に伺えますか?
大暮 紙って最初は真っ白で、360度どこにでもいける。でも、方向を一度間違えると戻ってくるのにすごく時間がかかってしまいます。だから、ある程度の早さで正解の場所にたどり着く必要があって、紙に向かって「何を描こうかな」なんて考えていたら絶対に間に合いません。実際にペンを取る前から「360度自由に」ではなく45度くらいに絞ったうえで描き始めなきゃいけないんだな、と。このときにそういうことを初めて考えたんですけど、その経験があったからこそ、のちに週刊連載ができたのかなという気もします。
アクションシーンは決め技から作る
――なるほど。キャリアとしては、そのすぐあとに『天上天下』の連載が始まります。
大暮 最初に出した単行本を、当時の『ウルトラジャンプ』の編集長が気に入ってくれて声をかけていただいたのがきっかけです。ただ、当時はアシスタントがいなかったので、全部ひとりで描くのは大変だなあ、と。連載が決まってうれしいというよりは、かなり冷静に受け止めていた気がします。あと『天上天下』の1話目は、途中までまったく別のネームを切っていたんですよ。完全なファンタジーもので。それがどうもピンとこなくて、現実をベースにした話にネームを切り直したんです。
――アクションシーンの構成は、何かお手本にしていたものがあったのでしょうか?
大暮 当時はアーケードゲームにハマっていたので、その影響が大きかったかな、と思います。アクションシーンの構成を考えるとき、いちばん多いのはキャラクターのカッコいいポーズや決め技から決めるパターン。「この構図でいこう」と固めてから、そのシーンにたどり着くまでを逆回しで構成していきます。だから、キメのコマの前のページまでは真っさらだったりします。
――決めゴマ以外の部分は、ネームで煮詰めていくのですか?
大暮 いや、原稿です。今やっている『化物語』などは原作があるのでそこまでネームと原稿の差はないと思うのですが、オリジナルのときは作画作業中に突然、演出や展開がひらめくことも多くて。このキャラクターは、この状況ならこう言うんじゃないか、こんな行動を取るんじゃないかと気がつくと、いてもたってもいられなくなってしまう。正確に言うと、そのキャラが一度そう言い出したら、僕は言うことを聞かざるをえない、というのが近いかな。それまで考えていた内容が急にウソっぽく、作り物のように感じるんです。