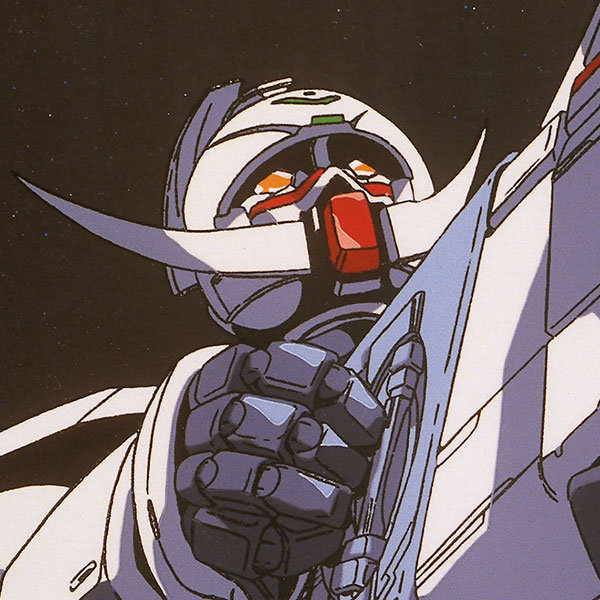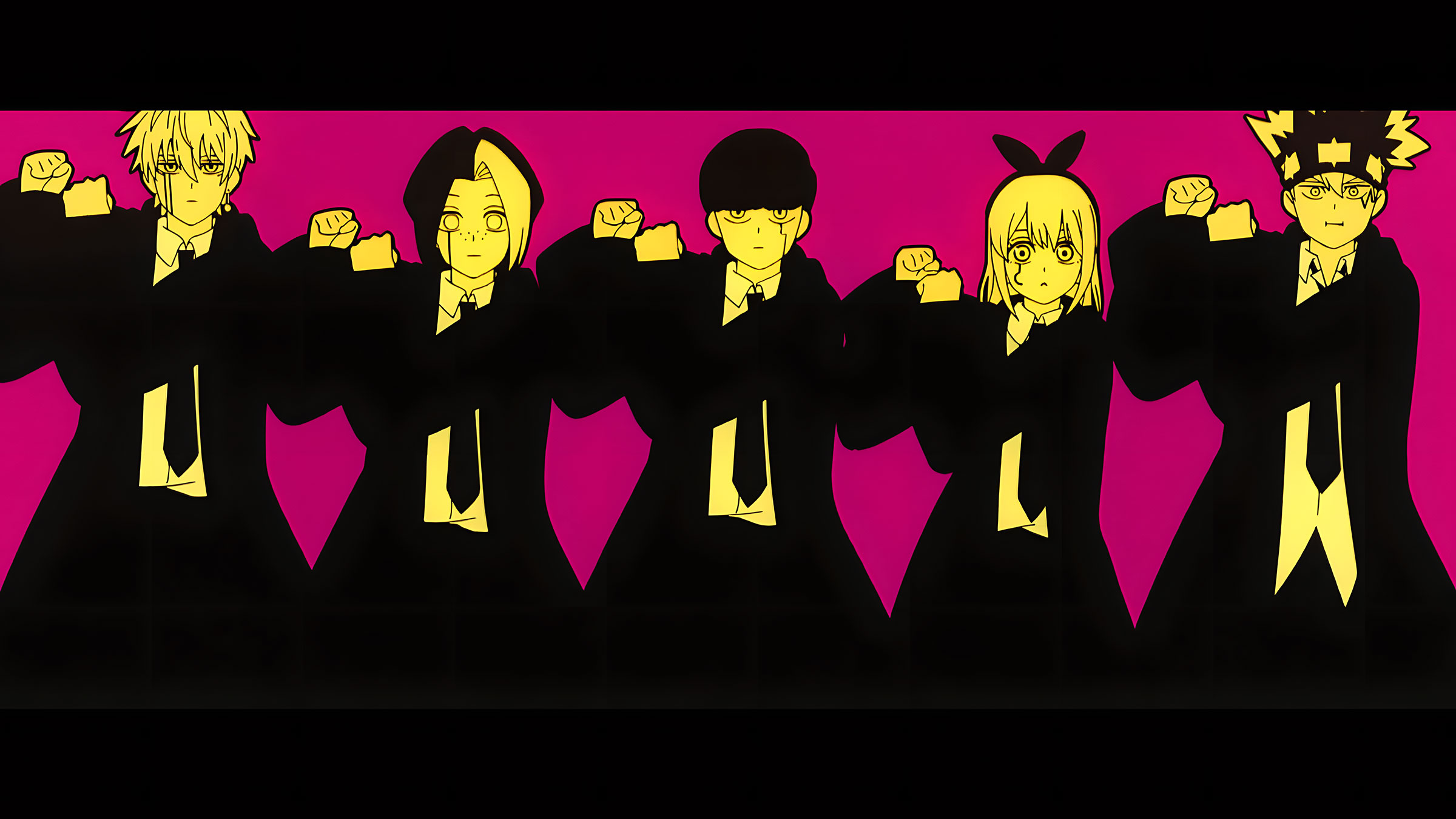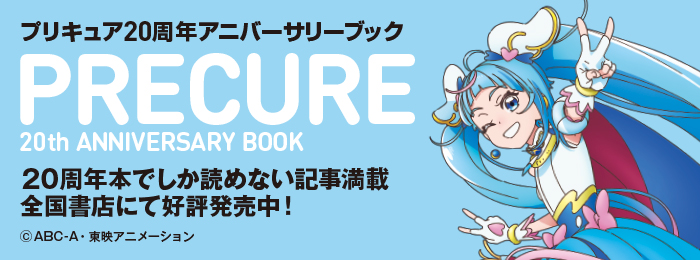夏芽の気持ちを救ってあげたかった
――まずは映画が完成した今の、率直な心境をお聞かせください。
石田 正直なところ、ほぼ休みなしで作業をしていて、完成してからもまだ1週間ほどしか経っていないんです(笑)。なので、まだ冷静な状態じゃないですね。映像的な部分でいえば、ある程度手応えはありますし、自分も会社的にも技術は向上しているな、と思います。あと、これまで一緒にやって来たスタッフに加えて、新しい人たちにも参加していただけたので、全体の体制という部分でも、より広がりと可能性を持って作れたのでは、と。ただ、肝心の内容については、まだちょっとわからない……というのが本音です(笑)。
――『雨を告げる漂流団地(以下、漂流団地)』は、石田監督にとって初めてのオリジナル長編作品になりました。そもそもどういう経緯で制作が始まったのでしょうか?
石田 もともと、ツインエンジンの山本(幸治)プロデューサーから「オリジナルをやってほしい」というお話をいただいていたんです。実際、「こういうのをやってみたらどう?」といくつか企画書もいただいていたのですが、それと同時に自分でも何か考えてほしいと言われていて。そのときに僕から提出したのが『漂流団地』で、海の上に浮かんでいる団地の絵も一緒に出していたんです。

――企画の最初の段階で、イメージボードみたいなものがあったわけですね。
石田 そうなんです。そこから企画が動き出したんですけど、すぐその後には今の映画の形に近いストーリーラインができていました。誰にでも、忘れがたい場所やお世話になった場所というものがあると思うんです。たとえば、実家に帰ったときに昔の遊び場がなくなっていたみたいな、そういうものの象徴として、今回の映画では「団地」が存在しています。
――思い出がいっぱい詰まっている場所ということですね。
石田 じつはその時点では、まだのっぽくんのキャラクターは存在していなかったんですけど、団地が主人公のふたり(夏芽と航祐)にすごく執着していて、彼らと離れたくないあまりに、いろいろな思い出を見せてくるといった話を考えていたんです。

――なるほど、そうだったんですね!
石田 そういう「団地」という場所に対する思いと同時に、このふたりをめぐって描きたかったこともありました。もう少し突っ込んで話すと、忘れがたいものとか、あきらめたくないと思っていること、そういったものと人はどうやって折り合いをつけるのか、というところです。夏芽というキャラクターはある意味、自分でいろいろなものを抱え込んでしまうキャラクターなんですけど、そういう子に対して、どう寄り添ってあげれば、彼女の気持ちを救うことができるのか。「こういうことを考えているのかな」というところを、シンプルに突き詰めて考えた結果が、この作品になっていると思います。
自分自身を偽らずに作り上げた作品
――夏芽や航祐たちを描くうえで、石田監督はどんなことを心がけたのでしょうか?
石田 ひとつ鍵になっていたのは、やっぱり夏芽の気持ちです。その描き方にはいろいろな可能性があって、もっと勝気な性格として描く方法もあっただろうし、あるいは下手をするとのっぽに対して「それはもう恋愛なんじゃないか?」というレベルで執着する……みたいな描き方もあり得ました。それこそ最初は、夏芽や航祐もおばけ団地に立てこもる、みたいな展開も考えていたんです。
――彼女の団地に対する執着が、ひとつ物語の軸になる、と。
石田 ただ、作劇の技術としてこちらが正攻法だろう、みたいなことよりも「自分が登場人物の立場だったらどうするかな?」というところに素直になって、キャラクターのリアクションや受け止め方を決めていきました。夏芽の言動にしても「自分だったら、そんなに強く出られないな」と思って、抑えめにしたりとか……。

――むしろ監督自身の気持ちだったり、主観みたいなものを作品に落とし込んでいったわけですね。
石田 そうですね。そういう部分があるんじゃないかなと思います。僕にとって初めての長編オリジナルということもありましたし、自分自身の気持ちにあまり嘘をつきたくなかった。ある意味、当たって砕けろ、みたいなところがあったかもしれません。もちろん、監督が「これが自分だと思う」というものをあまりにも突き詰めた結果、他の人がなかなか理解しづらいものになってしまうこともあるでしょうし。自分の中には合理的でない部分や、理解されづらいネガティブな感情の部分があるはずで、それが行き過ぎると商業作品にならなくなってしまうかもしれませんし。ただ、いろいろな人の意見に助けてもらいバランスをとりながら、どこまで自分のそういう非合理的で感情的な部分を描くことができるか。そうやって作ったところはありますね。

――夏芽たちの気持ちの揺れが生々しく感じられるのは、監督のそういう苦闘が反映されているのかもしれないですね。
石田 僕自身、物語を語る技術をたくさん持っているわけではないのですが、今回の映画を作ったことによって、「物語を作る」というのはこういうことなのかな?……と体感したところはありましたね。![]()
- 石田祐康
- いしだひろやす 1988年生まれ、愛知県出身。大学在学中に制作した短編「フミコの告白」で数々の賞を受賞。大学卒業後、新設されたスタジオコロリドに参加し、2018年に森見登美彦の同名小説をもとにした初の長編監督作『ペンギン・ハイウェイ』を公開。こちらも大きな話題を呼んだ。