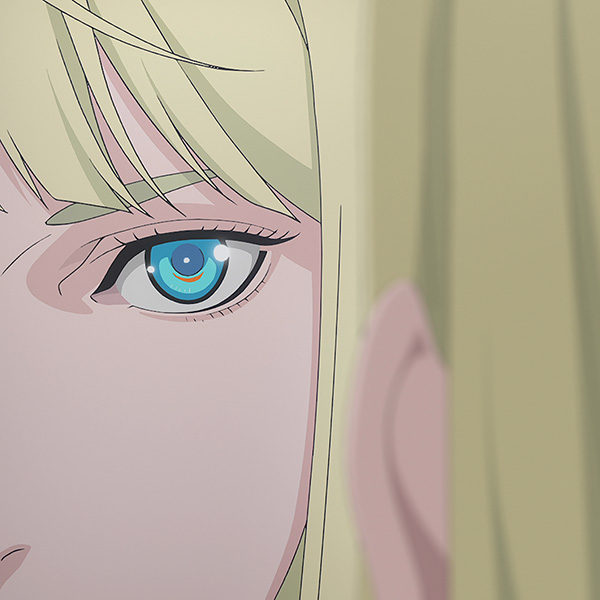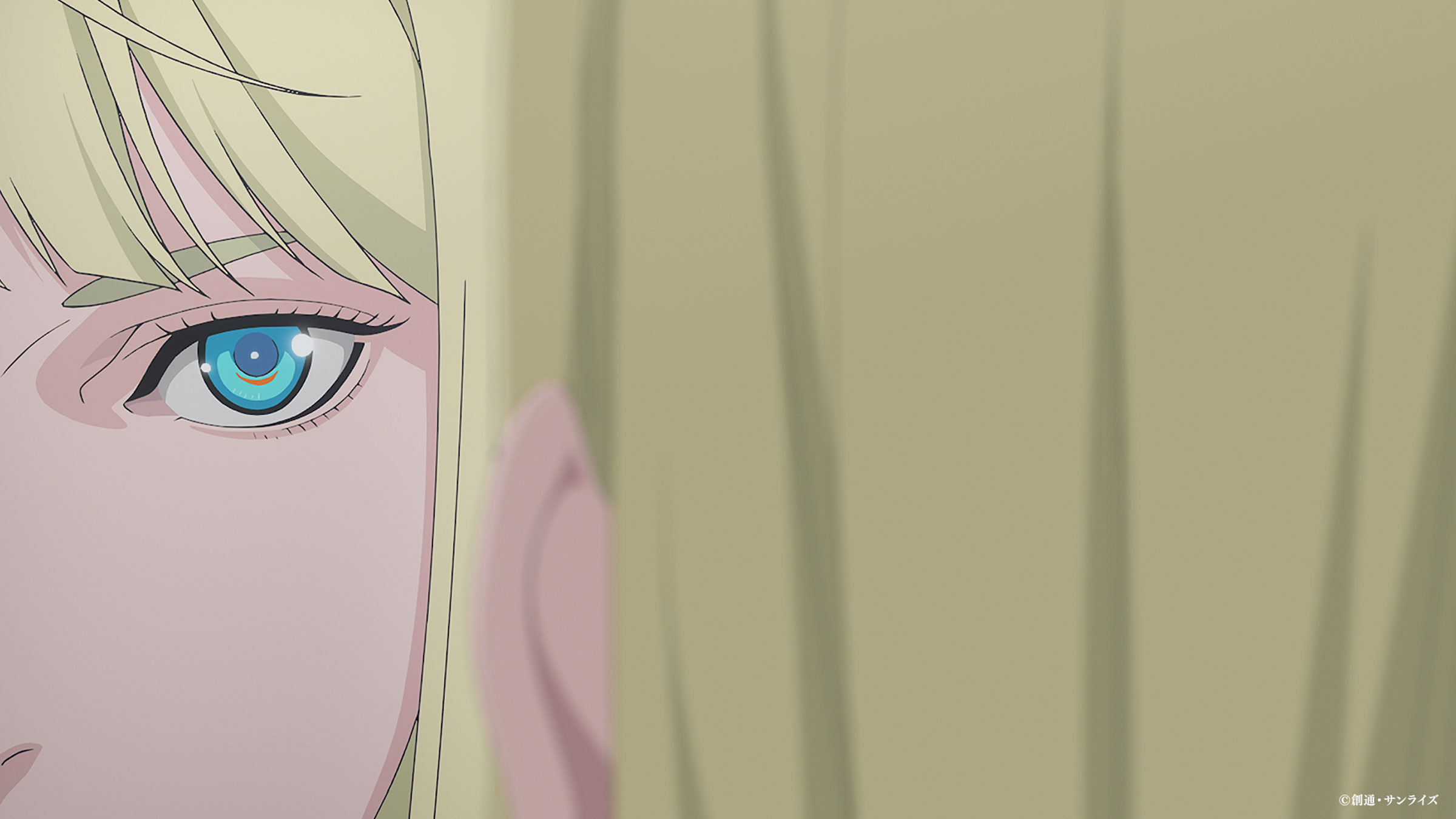総集編でありながら、まったく新しい作品を
――2011年のTVシリーズから10周年を迎えた『輪るピングドラム(以下、ピングドラム)』が、劇場版として帰ってきました。今回のプロジェクトのきっかけはどんなものだったのでしょうか?
幾原 TVシリーズの『ピングドラム』が終わってから、もう一回サルベージできないかとずっと考えていたんです。10周年が近づいたところで、プロデューサーの池田(慎一)さんと食事をしていて、「もうすぐ10周年だけど、『ピングドラム』って(新しい展開は)ありえるだろうか?」という意見交換をしたのが最初です。この10周年というタイミングでサルベージしなければ、『ピングドラム』はTVシリーズのライブラリとして流れていってしまうという思いがありました。

――最初から「映画にしよう」と決まっていたんですか?
幾原 いえ、最初は予算やメディアは全然決まっていなかったんです。制作スタッフや会社に向けて探るところから始まりました。でも、TVシリーズ全24話を今から見てもらうというのは、けっこうしんどい。なので「今の映画」として2本作って、それを若い人たちに見てもらいたいという気持ちが大きかったです。
――本作はクラウドファンディングで支援を募り、1000%のストレッチゴール、1億円が集まりました。
幾原 最初はクラウドファンディングなしで作ろうと思っていたんですが、いろいろ考えていくなかで少し欲が出まして……(笑)。いただいた支援の結果は予想をはるかに超えていて、おかげで本作を映画として作ることができました。
――幾原監督の劇場版というと、TVシリーズとテーマは一貫しつつも、印象が大きく違う『劇場版少女革命ウテナ アドゥレセンス黙示録』を想起するファンも多いと思います。本作『劇場版ピンドラ』も、一般的な総集編映画とは印象がかなり異なる作品になっていますね。
幾原 単なる総集編だったら面白くないので、今までにないタイプのものにしたい――という思いは最初からありました。つまり、総集編でありながらまったく新しい作品のように見えるかたちを目指したいと。TVシリーズの話と話の間をつなぐような新規カットがある総集編ではなく、まったく別の物語が始まるような導入で、それでいて見たことがある風景が展開されるような、そういうのがいいよねというところから始まって、行き着いたのが現在の『劇場版ピンドラ』です。

――池袋の街を子供の姿の冠葉(かんば)と晶馬(しょうま)が歩いているところから始まって……。本作は、TVシリーズ最終回のあとの話ということなのでしょうか?
幾原 はい。TVシリーズの最終回で、子供の姿になった冠葉と晶馬が旅立っていく。『劇場版ピンドラ』ではそのふたりが突然池袋の水族館にやって来て、「一体僕たちは誰だったんだ?」と記憶のないところから始まるお話です。彼らが「自分は何者か」と探るなかで、TVシリーズと映画の話が合流する。運がいいことに桃果というキャラクターがいた。だから、お姉さんと子供たちが何かやりとりするような話を進めていけました。
作品と観客との距離を縮めたかった実写パート
――TVシリーズを見ていたので、冒頭から「新作が始まった!」という感覚でした。
幾原 TVシリーズを見ていた人でも、ハッとするような発見がある作りをしているつもりです。もともとは「初見の若い人が見ても普通に楽しめる、独立した映画」を心がけたのですが、それによってTVシリーズを見ている人にとっても見たことがないディテールが生まれて楽しんでもらえるんじゃないかなと。「総集編を見せられると思っていたのに、まさか新作を見せられるとは」という衝撃も与えられたらと思っていたので、そういう感想を聞けるとうれしいです。

――「このシーンって、こういう意味のシーンだったっけ?」と既存のシーンに対してあらためて感じられたのも印象的でした。
幾原 それは映画のために整え直しているからですね。前編だけで6カ月以上はかかったんじゃないかな。とても大変でした。ストーリーの面白いところだけをつなぐと緩急がなくなってしまう……というのが、総集編が陥りやすいところ。そこを映画的なリズムを意識しながら、冠葉、晶馬、苹果(りんご)を中心にしてキャラクターの気持ちでつないでいったのが前編です。
――映画的なリズム……TVシリーズと映画とではかなり違うものですか?
幾原 違いますね。TVシリーズはAパートとBパートがあって、嫌でもそこでフィルムが切れます。だからTVシリーズのリズムは、パート内の約10分の中で整えるものになるけれど、映画は基本的には2時間ずっと椅子に縛り付けられるもの。意識的に気を抜くシーン、いわゆる「ダレ場」を作っていく必要がありますよね。そこが案外難しい。息を抜けるシーンを作ってしまうと、そこから浮上してこないで観客の気持ちが切れちゃうこともある。かといって、ずーっとバトルシーンみたいなものが続くとインフレを起こして、あんまり気持ちが動かなくなったりもする。飽きない映画というのは、そこがうまく作られているんですよ。

――前編でいうと、ちょうど真ん中くらいにも実写パートがありました。
幾原 そこは意識的に真ん中に入れました。ストーリーを追ってきて、あそこでいったん休憩してもらう。後編にもそういったシーンを入れています。
――実写とアニメを融合させた表現というと、ファンは『さらざんまい』(2019)のエンディング映像を思い出すと思います。
幾原 『さらざんまい』のエンディングを担当してくれた映像クリエイター田島太雄(たじまたお)さんに、本作でも実写パートをお願いしています。「現実を出したい」と思ったんですよね。池袋や荻窪の実景が映ることで、キャラクターがいる世界と、僕たちが普段暮らしている世界がつながっていると感じてもらえて、作品と観客の距離が縮まるんじゃないかなと。田島さんならそういうスケールの大きさを出してくれるという信頼もありました。
10年目の再集結
――新キャラクターのプリンチュペンギンや、プリンセス・オブ・ザ・クリスタルの姿をした桃果など、劇場版に向けた星野リリィさんの新規キャラクターデザインもありました。
幾原 星野リリィさんには「赤ちゃんペンギンが出ます」「桃果がプリンセス姿になって登場します」ということしかお伝えしていなかったですね。リクエストとしては陽毬(ひまり)のプリンセス・オブ・ザ・クリスタル姿とは印象を変えてほしいという話をしたことと、桃果が帽子を脱いだときに、頭に飾り物をつけてもらったぐらいで、ほとんどそのままOKだったかな。

――『ピングドラム』はTVシリーズ放送当時、ARBの歌をカバーしているのが話題でした。前編では「ROCK OVER JAPAN」はもとより、新たなカバーもありましたね! どういった選曲なのでしょうか。
幾原 もともと好きな歌を入れています。「YELLOW BLOOD」は「ジャパンイズナンバーワン」と言われていた時代、日本が元気だった頃のサラリーマンの歌。「俺たちイエローモンキーだけど、世界を股にかけているビジネスマンだぜ」という歌で、かっこよさがすごくいい。もうひとつの「ファクトリー」は父親と息子の歌。歌詞が強くて、聞くと絵が頭に浮かんできます。曲の最後、主人公はきっと悲しい顔をしているんだろうなと。

――こうした新しいカバーがTVシリーズのシーンにかかることで、かなり違うシーンに見えました。なおかつ、まるで曲がテーマソングのように合っている感じがして楽しかったです! ところで、キャストの皆さんと10年ぶりに集結していかがでしたか?
幾原 いろいろなところで話していますが、当時のメインキャストは木村良平くん以外はほぼ新人だったんです。だからうまくはないんだけど、ピュアさはある。今回のアフレコは、みんな10年間でキャリアを積んでいるので、うまくはなったけど逆にピュアさがなくなっている。どこを残してどこを収録し直すのかというのは考えどころでした。
――キャストの皆さんも本作の構成に驚いたのではないでしょうか。
幾原 アフレコ時はテスト用の映像だったのですが、みんな好意的な反応だったと思います。(木村)昴は「完全新作じゃないですか!」とテンションを上げていましたね(笑)。![]()
- 幾原邦彦
- いくはらくにひこ 1964年生まれ。東映動画(現東映アニメーション)に入社後、『美少女戦士セーラームーンR』のシリーズディレクターや『劇場版美少女戦士セーラームーンR』の監督を務める。独立後『少女革命ウテナ』『輪るピングドラム』『ユリ熊嵐』『さらざんまい』を制作。幾原ワールドに老若男女を引き込んでいる。




![劇場版『RE:cycle of the PENGUINDRUM』 [前編]君の列車は生存戦略 幾原邦彦監督インタビュー②](https://febri.jp/wp/wp-content/uploads/2022/04/mainbn2-e1650613963911.jpg)