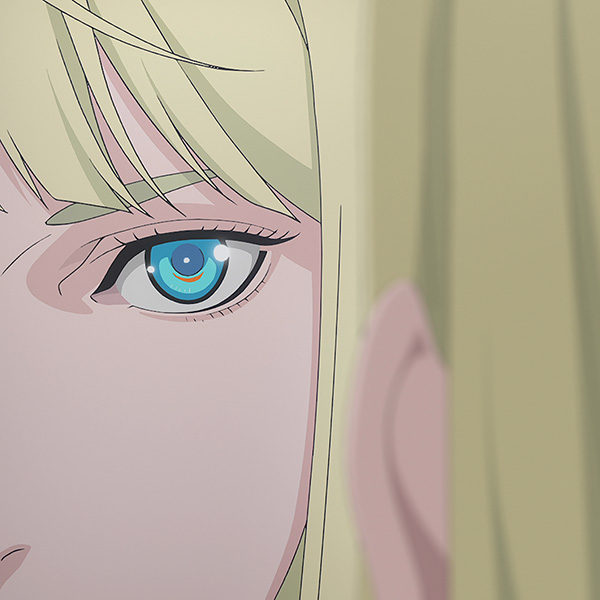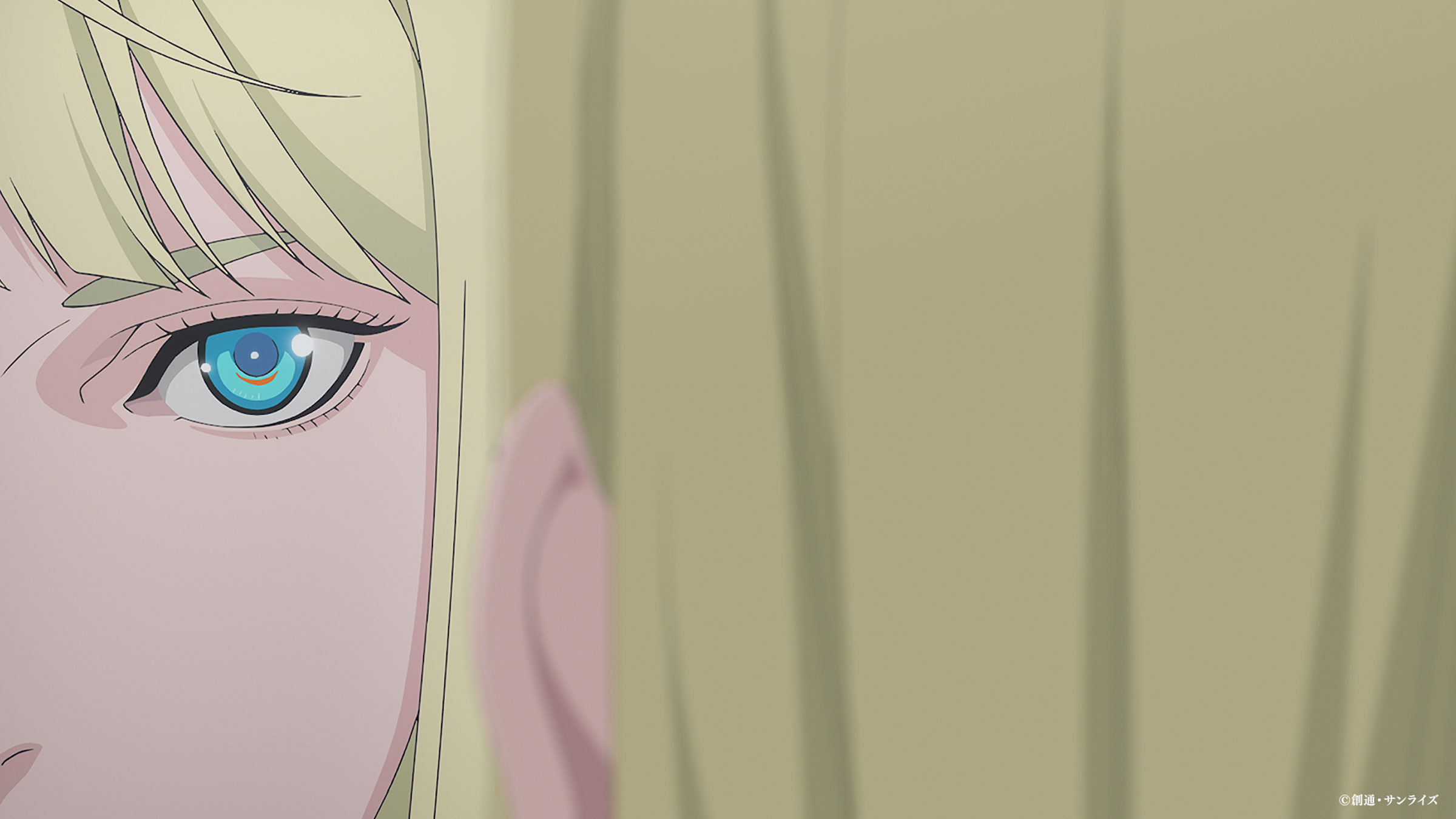アムロ・レイとの出会いは生き甲斐とのめぐりあい
――アムロ・レイを演じるということについて、これほど根掘り葉掘り聞かれることもなかったと思いますが、この連載を通じてあらためて「アムロ・レイの演じかた」についてどう思いましたか?
古谷 たしかにここまでひとつのテーマで掘り下げたことはないかもしれない。でも、やっぱり富野由悠季監督のお話(第10回)が印象に残っています。あらためて奥の深いキャラクターであると感じたし、自分にとっても大好きで大切なキャラクターなんだと再認識しましたね。
――アムロ・レイを演じることで古谷さんが得たものとは何ですか?
古谷 それまでの熱血キャラのイメージを払拭できたこと、またそれによって演技の幅が広がったことでしょう。そしてそれが、自分はプロの声優としてやっていけるという自信にもつながった。それらはアムロを演じたことで得られたものと言えるでしょう。もちろん、作品がヒットしたことで業界内での「古谷徹」の知名度が上がったこともそうですね。
ただ、自分の中でもっとも大きな変化は、声優が天職だと思えるようになったことです。あの当時、僕はまだ顔出しの仕事もやっていて声優一本には絞っていなかったんですね。それがアムロを演じたことで「アニメの声優は面白い」とか「ずっとこういう仕事をやっていきたい」と思えたし、これが天職なのかもしれないと感じるきっかけになったと思います。
その後、『幻魔大戦』(1983年)で東丈(あずまじょう)を演じることになったときに、アニメ中心で仕事をしていた青二プロに移籍する決心がついた。だから、大げさに言うとアムロとの出会いというのは「生き甲斐とのめぐりあい」であるとも言えるんじゃないかな。……これは、もちろん「めぐりあい宇宙」に引っかけているんだけど(笑)。アムロ・レイがなかったら今の『名探偵コナン』の安室透もなかったわけだし、今でも第一線で仕事をやらせてもらえていることにもつながるわけだから、自分の人生にとって大きな影響があったキャラクターであることは間違いないですよね。
――かつて『巨人の星』の星飛雄馬が古谷さんの演技の幅を縛ったように、アムロを演じたことで演技の幅に制限ができたと感じたことはありますか?
古谷 アムロを演じたからといってその後、熱血キャラの仕事がなくなったわけではないし、何か仕事に制限が生じたことはありません。むしろ演技の幅が広がったことでいろいろな役をやらせてもらう機会も増えたし、『聖闘士星矢』のような王道の熱血キャラをやらせてもらうこともありましたからね。
ただ、あるとすれば、アムロ以降の僕は、アニメ声優であるというレッテルがさらに濃くなってしまったかもしれない。それはつまり洋画の吹き替えだったり、アニメ声優ならではの芝居が求められない作品……たとえば、スタジオジブリ系の作品からは遠のいたということかな。それともうひとつ、大人の役への移行も少し遅れたかもしれない。少年役という印象が強くなってしまったから、どうしてもそういう役は回ってこなくなりますね。
――大人の役というと『機動戦士Ζガンダム(以降、Zガンダム)』や『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア(以降、逆襲のシャア)』でのアムロが思い出されますが。
古谷 そうだね……たしかにそれと同じくらいの時期から増え始めたかな。僕が意識し始めたのは『宇宙皇子』(1989年)と『美少女戦士セーラームーン』(1992年)のタキシード仮面からで、そのあたりから青年の演技について自信が持てるようになりましたね。どちらも大人の男性というよりは青年で、とくに宇宙皇子は高貴で清廉なキャラクターだったから、これがなければタキシード仮面はできなかったと思う。そうやって役を積み重ねることで、次第に大人の演技ができるようになっていったというのはありますね。『逆襲のシャア』でのアムロは年齢的には十分大人なんだけれど、それでもまだ「熱い男」じゃない? だから、ここで言う大人の男性のクールな声とはちょっと違う。自分の中でそれができたと思えたのは、宇宙皇子からなんです。

――洋画の吹き替えとアニメで、声優にも向き不向きがあるのでしょうか?
古谷 最近はそうではない作品も増えましたが、アニメでは演技がオーバーになりがちですよね。効果音や音楽が派手だから、そういう音に負けないように声を張らなければならない。一方で洋画の場合はリアリティが第一にあって、もとの俳優もそう演じているから、こちらもそれに合わせる必要がある。アニメほど感情過多になってはいけないし、声優にもそういう演技が求められます。ジブリ作品も同じで、求められる演技は作品の世界観やストーリーに依るところが大きいわけだから、僕のようにヒーローばかり演じていた、ある意味での「強い個性」は需要と合わなかったかもしれないですね。