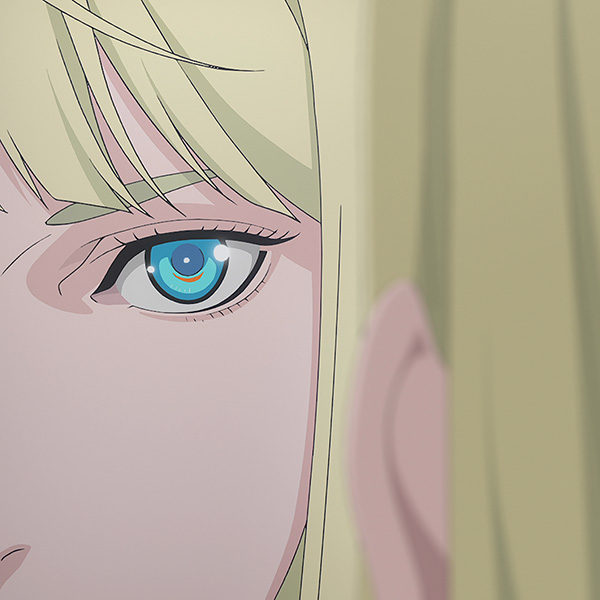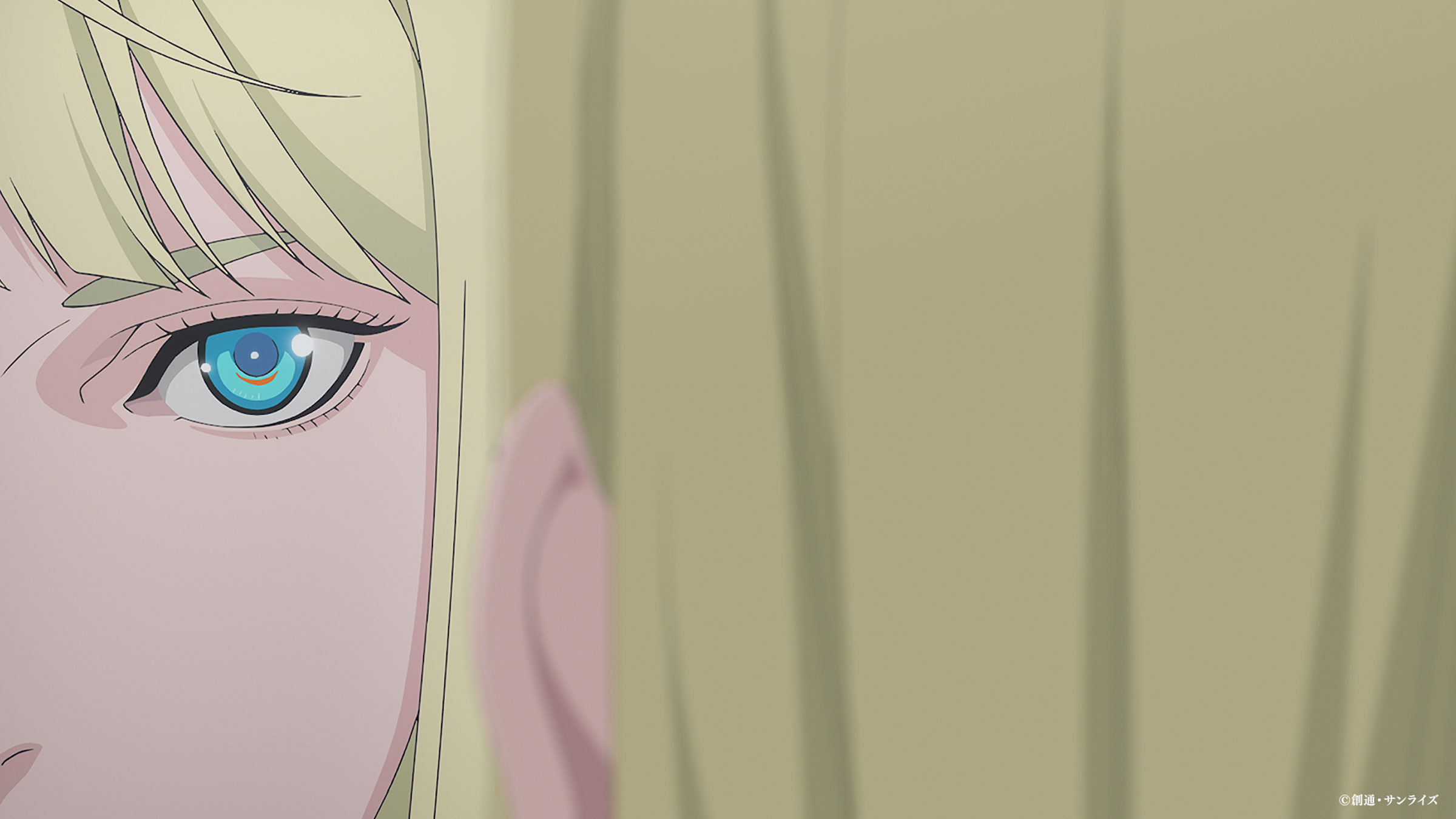今の声優に要求される演技の変化
――舞台での演技と声優としての演技では、具体的にどういう違いがあるのでしょう?
古川 根本的には同じでしょうが、声優は限定された空間である録音スタジオでの収録という制約がありますね。「声優演技」などというものは基本的にはないと思いますが、録音機材の問題で、舞台と一緒の発声をしているとうまく録れないということはあるでしょう。アナログ的な表現で言えば針が振り切れてしまうという。
古谷 音が割れてしまうこともありますね。
古川 でも、今は収録機材がものすごく進化していて、声を張らなくても音が拾えてしまうんです。昔だったら「針が振れないよ」と言われたようなボソボソした声量でも、今はきちんと録音できます。

古谷 コンプレッサーを使って音量を自動制御できるようですね。小さい音は増幅するし、大きすぎる音は抑えるように自動で調整してくれる。ただ、それを多用されてしまうと僕らが意図した芝居のニュアンスが出なくなってしまうこともありますから、そういう部分での危険性は感じますよね。
古川 それはそうかもしれない。若い声優さんたちが小さい声でボソボソしゃべるのを聞いていて、これはリハーサルだからああいう声なのかなと思っていたら本番でもそのままだったので驚いたことがあったんです。それで音響監督さんにあの声で拾えるのか聞きに行ったら「古川さんもあれに合わせてください」って言われて(笑)。僕と共演していた緒方恵美さんはもっと声を抑えてください、という演技指導でした。それは『たまゆら』(2010年)という佐藤順一監督の作品で、写真好きな女子高生のお話です。監督はそれを「幽(かそ)けき演技」と言っていて、ちょっとした風でも揺らいでしまう蝋燭(ろうそく)の炎のような繊細な少女たちの心の動きを表現しているというお話でした。もちろん、オンエアを見ると、そのかすかな声もちゃんと音が乗っている。だから、これが良い悪いという話ではないんです。機材の進化によって、そういう演技も要求されるように変化しているということなんですよね。

古谷 ちゃんと発声ができる声優がダメみたいな話になりかねないですね(笑)。でも、そういう演技もできなければこれからは通用しないということでもあるんでしょうね。
古川 もちろん、作品によるというのは前提としてありますよ。音響監督さんによって違ってくることもあるでしょう。でも、それを見た新人の方たちはそれを良しとして真似をするでしょうし、でもだからと言って基本的な発声を疎かにするようでは本末転倒ですから。
古谷 いろいろな意味で、要求される演技の幅が広がっているとも言えますね。
『ククルス・ドアンの島』で再確認したお互いの絆
――収録現場の変化といえば、劇場アニメ『機動戦士ガンダム ククルス・ドアンの島』では個別での収録だったとうかがいましたが、古谷さんと古川さんの収録日は同じだったんですよね。
古谷 午前中が古川さんで、僕は午後からでした。入れ替わりのときちょっとご挨拶をして、記念にふたりで写真を撮ったりして(笑)。でも、カイやアムロはこれだけ長く演じているから、ひとりでの収録でもとくに問題はなかったですよね。
古川 もうわかっているキャラクターですからね。収録時間が短くなる分、労働としてはかえって楽になるくらいです(笑)。たしかに会話のキャッチボールとか、そういう演技についての問題点も指摘されることはありますが、僕としてはそんなに気にならなかった。
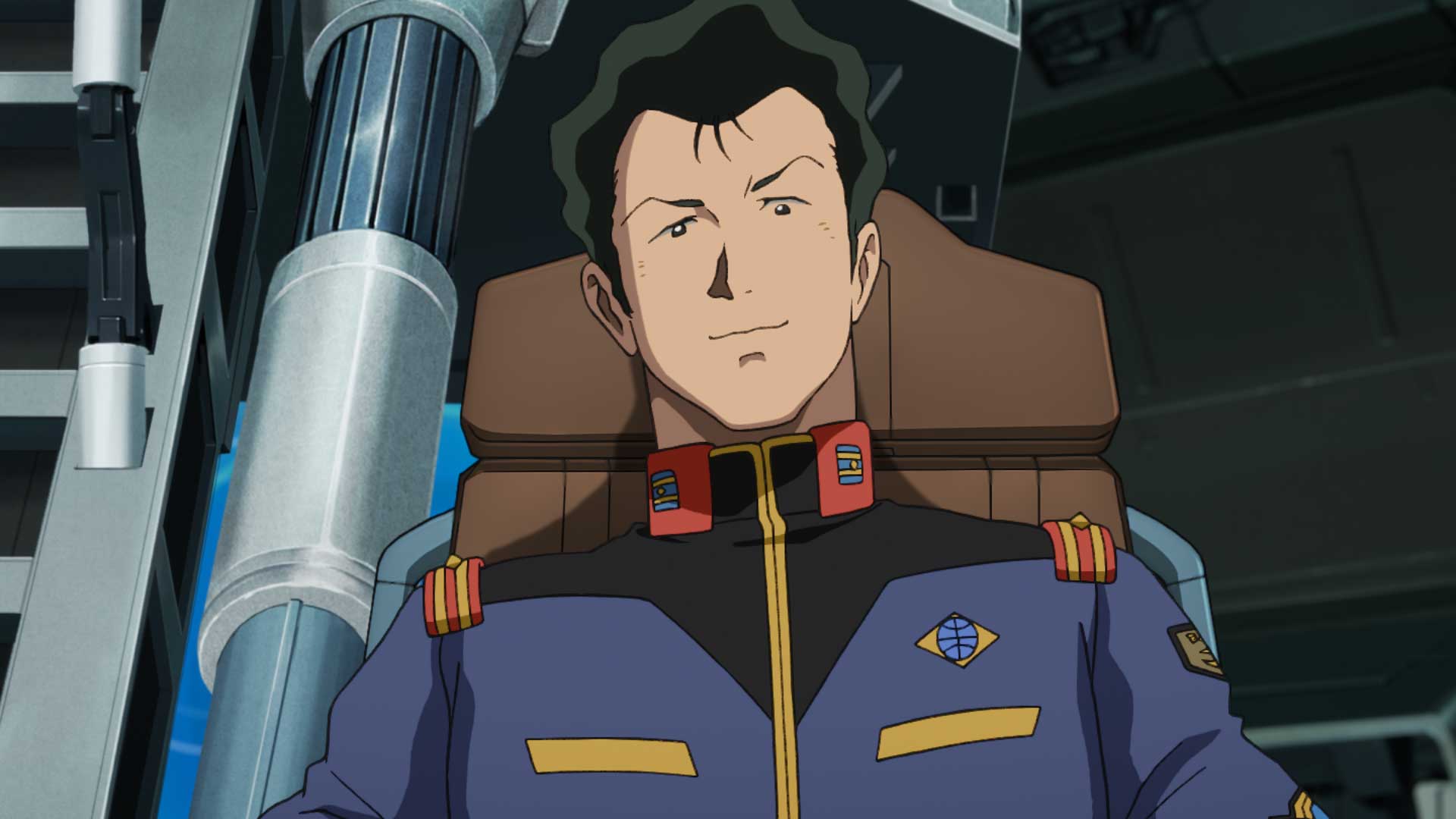
古谷 だいたい想像できますよね。ドアン以外はキャストが誰かもわかっていたし、それこそ『機動戦士ガンダム THE ORIGIN』でも共演していたから、こういう声でこういう反応が返ってくるだろうなという想像はしやすかった。でも、コロナ禍もあって仕方ないとはいえ、やっぱり皆で一緒に収録したいですよね。休憩時間に皆で食事に行ったりとか、世間話をしたりすることで雑誌の取材なんかで披露できるエピソードにもなるじゃないですか(笑)。
古川 たしかに、そういうことはあるね(笑)。