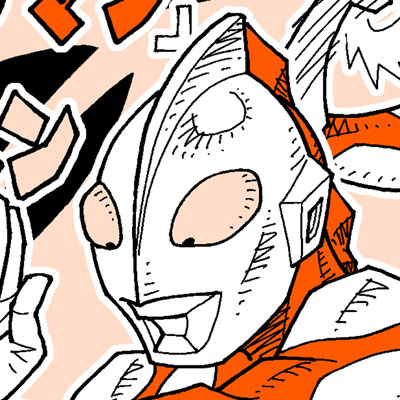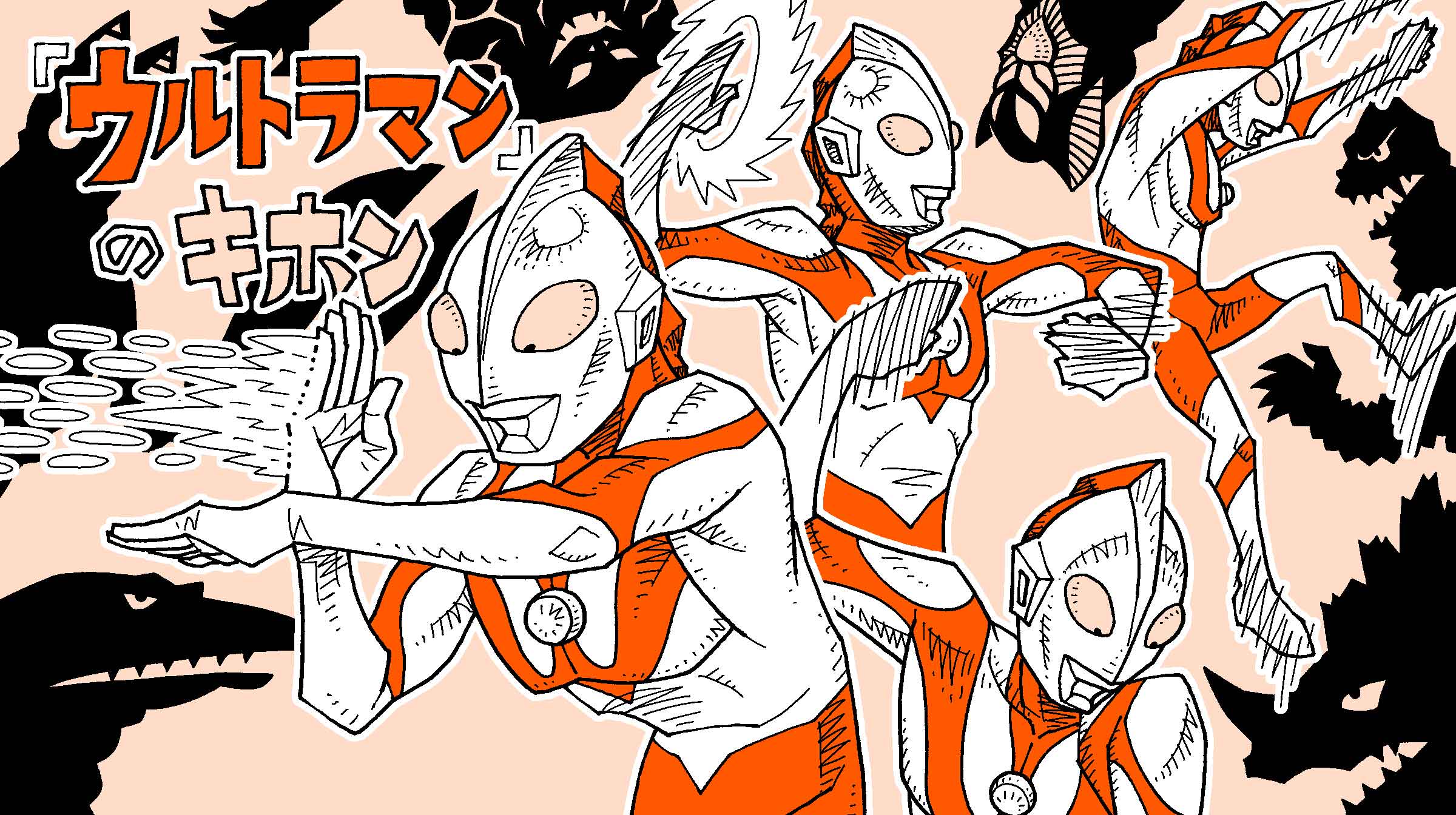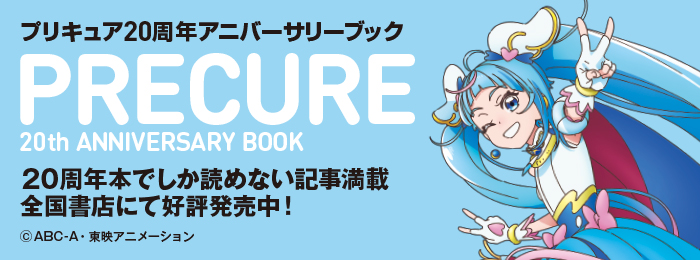初めて触れたキャラクター論と「お仕事もの」アニメ
――2作目は『機動警察パトレイバー the Movie』を選んでいますが、これは実質「押井守作品全部」という意味だと。
古川 僕は幾原(邦彦)さんの直弟子だとネットで書かれているし、僕自身もそれを認めてはいます。それから庵野(秀明)さんが好きだってこともインタビューで話していますが、でも、じつはそれよりも先にめちゃくちゃ押井さんの洗礼を受けているので、そのことをこの機会に話しておきたかったんです。『聖闘士星矢』の次にハマったアニメが『機動警察パトレイバー』で、TVシリーズだけじゃなくOVAや映画もひっくるめて追いかけるなかで、明らかに違う濃密さの作品がある。その理由を考えていて「ああ、押井守という人が特別なんだ」と気づいた瞬間があったんです。
――名前を意識したきっかけは何だったんですか?
古川 最初は脚本のクレジットでしたね。そのあと『GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊』が公開されたときに「押井守」という名前が一気に世間に押し上げられたじゃないですか。それでインタビューや押井さん自身が書いた文章が大量に世に出たとき、「俺たちの押井守が世界で大ヒットか……」みたいな謎の高揚感とともに読みあさりました。今では紙の媒体だけじゃなく、インターネット上にあるものもページ保存して残すレベルで。
――それはスゴい。
古川 そうして触れていた押井さんのアニメの演出論が、自分が演出にあれこれと口を出せるようになったあと……『ユリ熊嵐』の副監督になったあたりで初めて高い解像度で自分なりに理解できたんですよ。それまではあくまで特別な人が言っている特別な言葉だと思っていたんですけど。たとえば、有名な「(アニメの)情報量のコントロール」という話も、それまではオタク的な知識として持っているだけだった。
――庵野さんもする話ですね。
古川 じつは幾原さんも、現場でほぼ同じことを言っていたんです。つまり、レベルの高いアニメーション監督はみんなやっていることなんですよね。僕の解釈としては、自分が実現したい表現に対して、どのマテリアル(素材)を選択するかということなんです。ある現象を映像で表現するときにセリフでやるか、音楽でやるか、3DCGでやるか、背景美術でやるか、作画でやるか。その最適な選択を、押井さんも幾原さんも徹頭徹尾、自作でやりきっているんですよ。ふたりの演出のスタイルは全然違いますけどね。だから僕、幾原邦彦を語るときに、すぐに「テーマ性」みたいな方向に話を持っていく人が多いのは問題だと思っています。「耽美」とかね。「耽美」なんていうのは、結局は『少女革命ウテナ』の印象でしょう。
アニメのオリジナル企画を
作るときには
お客さんの楽しみ方を
どう設計するかをまず考えるべき
――耳が痛いです。
古川 絵コンテを描いているとき、幾原さんはとにかくマテリアルを気にしていたんですよ。「脚本のト書きにはキャラクターの動作として書いてあるけど、同じことを美術で表現したほうがいいと思う」みたいな話ばかりしていた。僕はそうした言葉のすべてがカルチャーショックだったんです。幾原邦彦というアニメ監督は、決して余裕があるわけではない制作現場で、マテリアルを常に取捨選択して、そのときの状況でできる最適なフィルムを作り続けてきた人なんだなと。選べるマテリアルに合わせて、自分の中にあるテーマすら変化させてきた。そうして変えたテーマですら、特別な推進力を持ってお客さんの中に入っていくのが幾原さんの作家としての強さなんです。そして、それはアニメ業界で押井さんをはじめとする偉大な先人たちがやってきたことなんですよね。マテリアルの選び方が、その監督の作家性を決めるといってもいい。冷静に考えると当たり前のことなんですが、実際にやりきるのは本当に難しいことなんです。……で、話を『パトレイバー』の劇場版の1作目に戻すと、まず濃厚な特効が入ったセルのスライドで始まるオープニングが、映画の入りとして完璧。『聖闘士星矢 真紅の少年伝説』もそうですけど、僕はそういう映画に弱い(笑)。そして僕はこの映画で「キャラクター論」を初めて映像として見せてもらった感じがしたんですよ。
――どういうことでしょう?
古川 「キャラクターって絵で描く必要がないんだ」ということです。誰かがそのキャラの話をすればいい。つまり『ゴドーを待ちながら』のスタイルがキャラクターを描くときに使えると知った。で、この作品は中学生が大好きな感じの聖書の要素で作品が彩られていて、最後には痛快な崩壊シーンとロボット同士のアクションが置かれている点もいいんですよね。ハイディテールなメカ作画もたまらないです。
――エンタメとしてのバランスがいいですよね。
古川 で、もう少し違う意味合いでも話すと、『パトレイバー』は僕にとって初めて触れた「お仕事もの」なんです。初めて大人の大変さを描いた作品があることを知った。要するに、場所と役割が人に与える影響があって、でもそこにはたまに後藤隊長みたいな人がいる。「正義の味方でありたい」みたいな自分の気持ちと社会通念との間で、大人は常に揺れ動いている。その振れ幅を、「警察」という特殊な環境下でロボットの要素も組み合わせたうえで描ききっているのが『パトレイバー』というシリーズだと僕は思っています。この作品に限らず、じつは押井さんは自分の作品で、特殊な職業の人ばかりを描いているんですよね。「職業好き」なのもあるでしょうけど、押井さんは『うる星やつら』以降、キャラクターの役割によって作劇をしているからでしょう。『うる星やつら』はラムちゃんという宇宙人が作品の中心にいることで、どんな無茶苦茶なことも許される世界観になっている。つまり、ラムちゃんは舞台装置なんですが、それ以降、押井さんは「警察官」以外にも「探偵」「パイロット」みたいな特殊な状況にキャラクターを追い込む。そして、その状況の中で「役割通りに動かなきゃいけない」と思う基本パターンの人間と、そこからズレた思考をする人間をバディとして組ませることで物語を動かす。そうした舞台設定によって、キャラクターの感情の振れ幅が、僕らの想像できる範囲とそれを超える範囲のふたつセットで用意できる。みんなが想像できる部分がちゃんとあることで、ズレている部分が強調されるんですよね。押井さんはそういった仕掛けをいつも意識的にやっていて、これはオリジナル作品を手がける監督にはとても重要なことなんです。だから僕、今言ったようなことを踏まえて、いつもオリジナル作品の企画会議で言うことがあるんですよ。
――何ですか?
古川 「アニメのオリジナル企画を作るときには『お客さんの楽しみ方をどう設計するか』をまず考えるべき」ということですね。押井さんや幾原さんがこれまでやってきたのって、そういうことだと僕は理解しています。楽しみ方の工夫を、監督がプロデュースレベルから意識して作る。自作を例にするなら「舞台をやるといっているけど、その要素をどうアニメとつなげるの?」とか「Twitterの実況文化や同時性を楽しんでもらうにはどうしたらいいのか?」とか。それは監督がプロデュースを意識しないとダメなんですよ。なぜかというと、映像にするのは脚本家でもプロデューサーでもなくて、実際に絵コンテを描く監督だから。絵コンテで広げられる要素をどうやって脚本段階、企画段階から仕込むか。監督がそこまで考えて動くことが「オリジナルアニメを作ること」なのかなと。見たこともないような凄まじいイメージボードを描いて、どんでん返しのエピソードを考えて、あとは作画をがんばればスゴいオリジナルアニメは「納品」はできます。ですが「楽しんで見てもらえるか」は別だと学びました。![]()
KATARIBE Profile

古川知宏
アニメ監督
ふるかわともひろ 1981年生まれ。大阪府出身。アニメーション監督。スタジオグラフィティでアニメーターとしてキャリアをスタート。現在はフリー。アニメ『少女☆歌劇 レヴュースタァライト』の監督として大きな注目を集める。