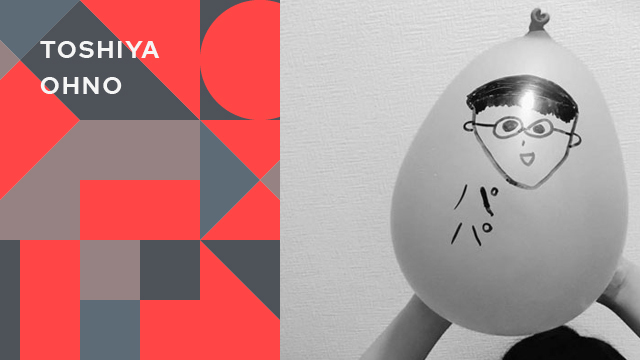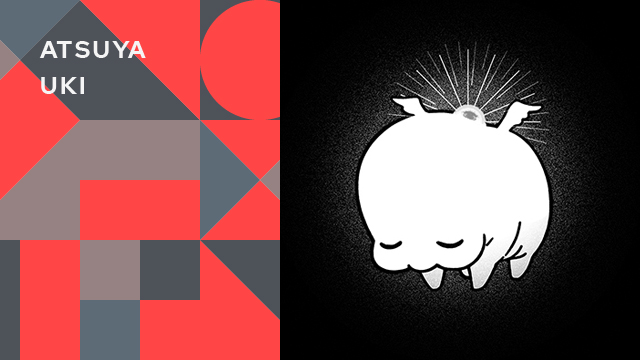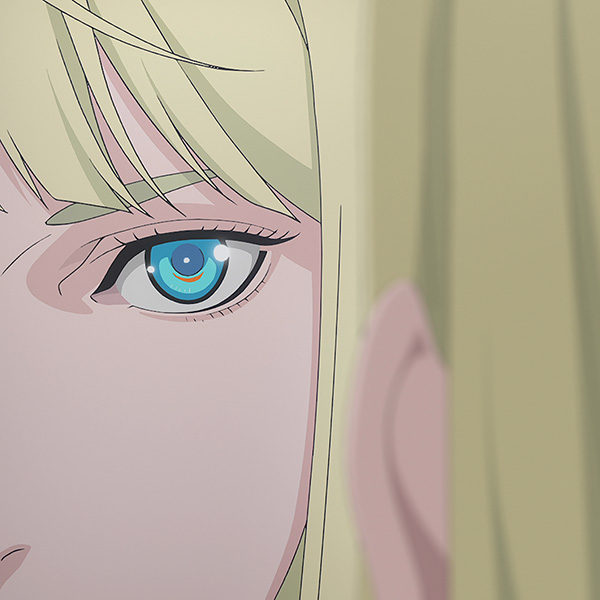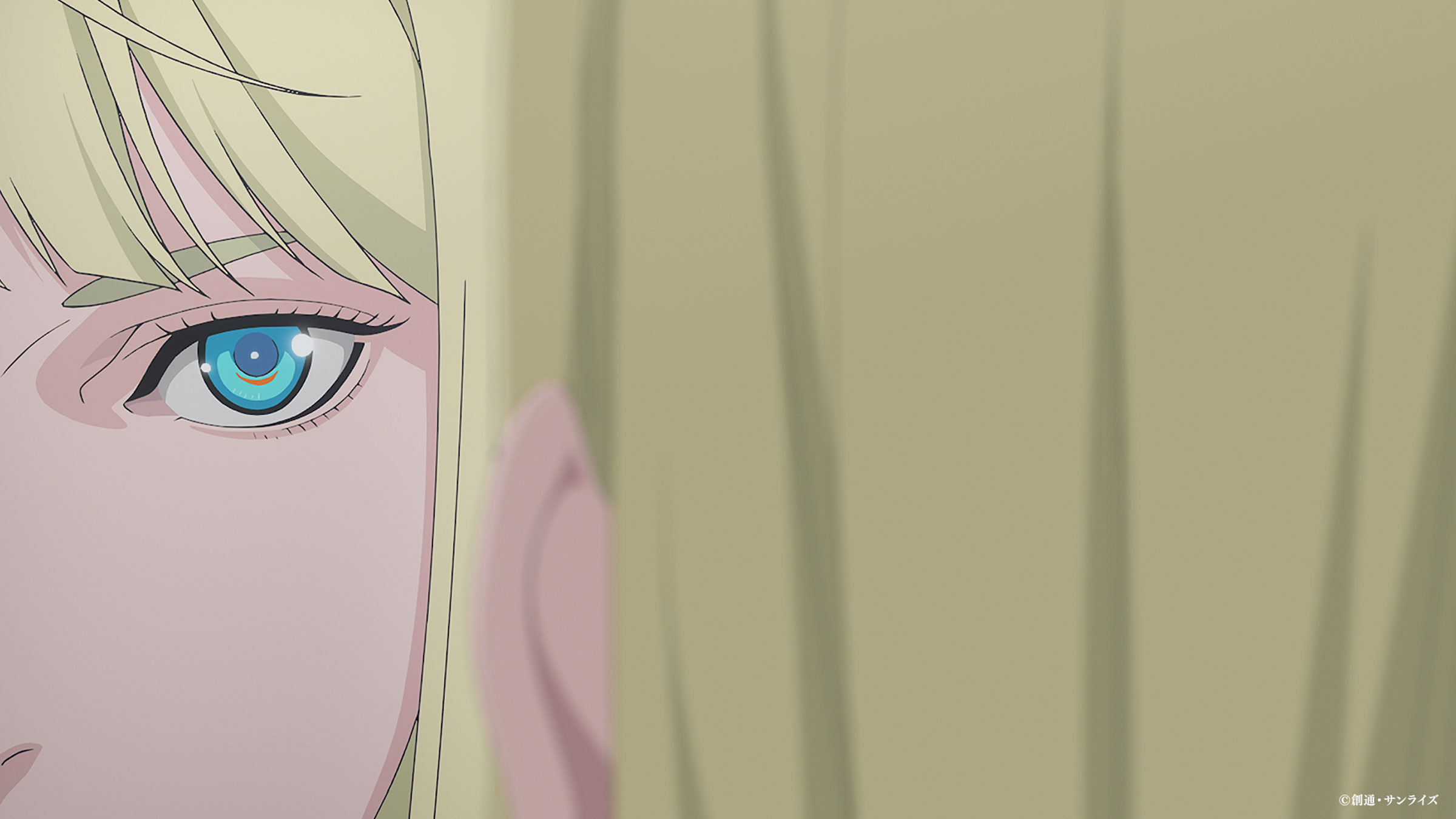独特のスタイルだった初のアニメ現場
――第1回では、劇団に応募した作品がきっかけで脚本家デビューを果たしたと聞きましたが、そのあとも劇団での仕事が続いたのでしょうか?
大野 その劇団に脚本家として所属することになって、若手公演に2本、脚本を提供させてもらったんですが、僕自身が未熟だったこともあって、そのあとは上演してもらえない日々が続いたんです。そうこうしているうちに、なんとなく劇団からフェードアウトしてしまったんですが……。ただ、その劇団に所属していたときに、テレビの仕事を紹介してもらったんですね。最初は深夜ドラマの脚本を書かせていただいて、そのあとは『世にも奇妙な物語』などもたくさん書かせてもらいました。すべてはそこから始まっているので、劇団にはすごく感謝しています。
――アニメの仕事を始めるきっかけは、何だったのでしょうか?
大野 しばらくは実写のドラマや映画の仕事が続いたんですが、きっかけは2010年に公開された山本寛監督の映画『私の優しくない先輩』ですね。この作品はアニプレックスさんが製作で入っていて、プロデューサーだった南成江さんから映画が終わったタイミングで「こういう企画があるんですが、書いてみませんか?」と声をかけてもらったんです。それが『つり球』でした。
――そういえば、『私の優しくない先輩』と『つり球』は、どちらも南プロデューサーが手がけた作品ですね。
大野 とはいえ、こちらはアニメといえば『トムとジェリー』で止まっている男ですからね。右も左もわからない状態で、まず中村健治監督と引き合わされました。企画書も一緒にいただいたんですが、青春と釣り、そして宇宙人の要素を入れることが決まっていて、あとはラフの絵が1枚くらいあったかな。アニメの監督として初めて出会ったのは中村監督なんですが、中村監督から教わったことは大きかったと思います。
――まさに企画の初期段階から参加していたわけですね。中村監督は大野さんにどんなものを要求していたのでしょうか?
大野 最初に「アニメだと思って書かなくてもいいですよ」とおっしゃったんですよね。とにかくアニメに対して、自由な教育を受けたと思います。中村監督は、自分の中にイメージはあるんだけど、それを論理立てて話す人ではないんです。何かセリフを言ってみたり、あとは顔を合わせて打ち合わせをするなかで、だんだんと固まってくる。僕は今でも脚本を書くときは、作品の主体となる方を憑依させて書くような感じなのですが、中村監督との作業は、まさしくそういう感覚でした。中村監督が話していることをメモして、それをかたちにするのが僕、みたいな感じですね。
コミュニケーションのなかから
生まれたものをかたちにしたから
妙にリアルなものが生まれた
――それはまた独特なスタイルですね。
大野 無駄話でもなんでも、とにかくたくさん話して、オモチャ箱をひっくり返したなかからひとつのものを作っていく、というか。まわりから見ると「無駄が多い」と思われるかもしれないですが、まったく無駄ではないんです。『つり球』のときは、制作スタッフの青春時代の話を聞き出して、それをもとにリアルなものを作っていこうとしていて、言わば、コミュニケーションのなかから生まれたものをかたちにしていました。だからこそ、妙にリアルなものが生まれたんだろうなと思います。のちに他のアニメ監督の方とも一緒にお仕事をすることになるんですが、中村監督のようなスタイルの方は、なかなか他にはいないですね。
――実体験をもとに、作品を立ち上げていくようなスタイルだったんですね。
大野 たとえば、中村監督は「キャラクター」という言葉を使わないんです。あくまでも「人物」として、ちゃんとそこに生きているものとして扱う。実写でもアニメでも基本的なアプローチは――人物がリアルに生き生きとしている様を描くという点は、みんな一緒だと思うんですが、中村監督の場合はそのやり方が極端というか……。それこそ、まったく格好をつけずに、突然思い出したことを会議中に話し出したりして、会議自体がどんどん長くなる(笑)。でも、あとから振り返ると、あのときの話があったからかたちになったんだなと思えるんです。まわりのスタッフは大変だったと思いますが、僕としてはすごく楽しく書かせてもらえました。
――大野さんがやっている仕事に『つり球』からの影響はありますか?
大野 今は「長い会議は避けよう」という傾向があったりして、なかなか『つり球』のような作り方ができないんですが……。でも、モノを作るというのは、すべてをさらけ出す行為なんだな、と感じました。『つり球』は青春ものでもあったので、自分たちの青春を投影して作っていたところがある。そういうものであっても、情熱を込めて作れば、見た人からちゃんと反応が返ってくるんだな、と。今でも『つり球』を愛してくれている人の話を聞くと、とても幸福な経験だったなと思います。あとはチームの大切さですね。もちろん、意見がぶつかることもあるんですけど、それは情熱をもって取り組んでいるからこそ、で。スタッフ全員が一丸となって作った思い出がありますし、「あのときみたいなものが作れたら」と、その幻影をいまだに追いかけている感じはありますね。![]()
KATARIBE Profile

大野敏哉
脚本家
おおのとしや 1969年生まれ。愛知県出身。実写ドラマ・映画の脚本家としてキャリアをスタートさせ、2011年に放送された『スイートプリキュア♪』以降はアニメにも進出。最近の参加作に『約束のネバーランド』『86-エイティシックス-』など。