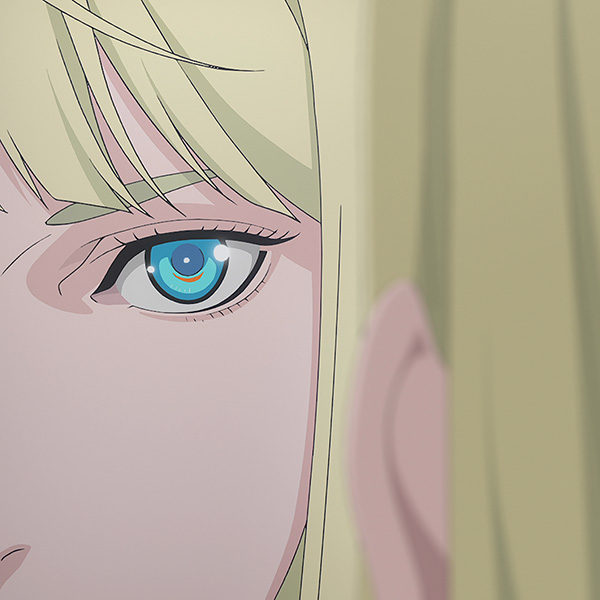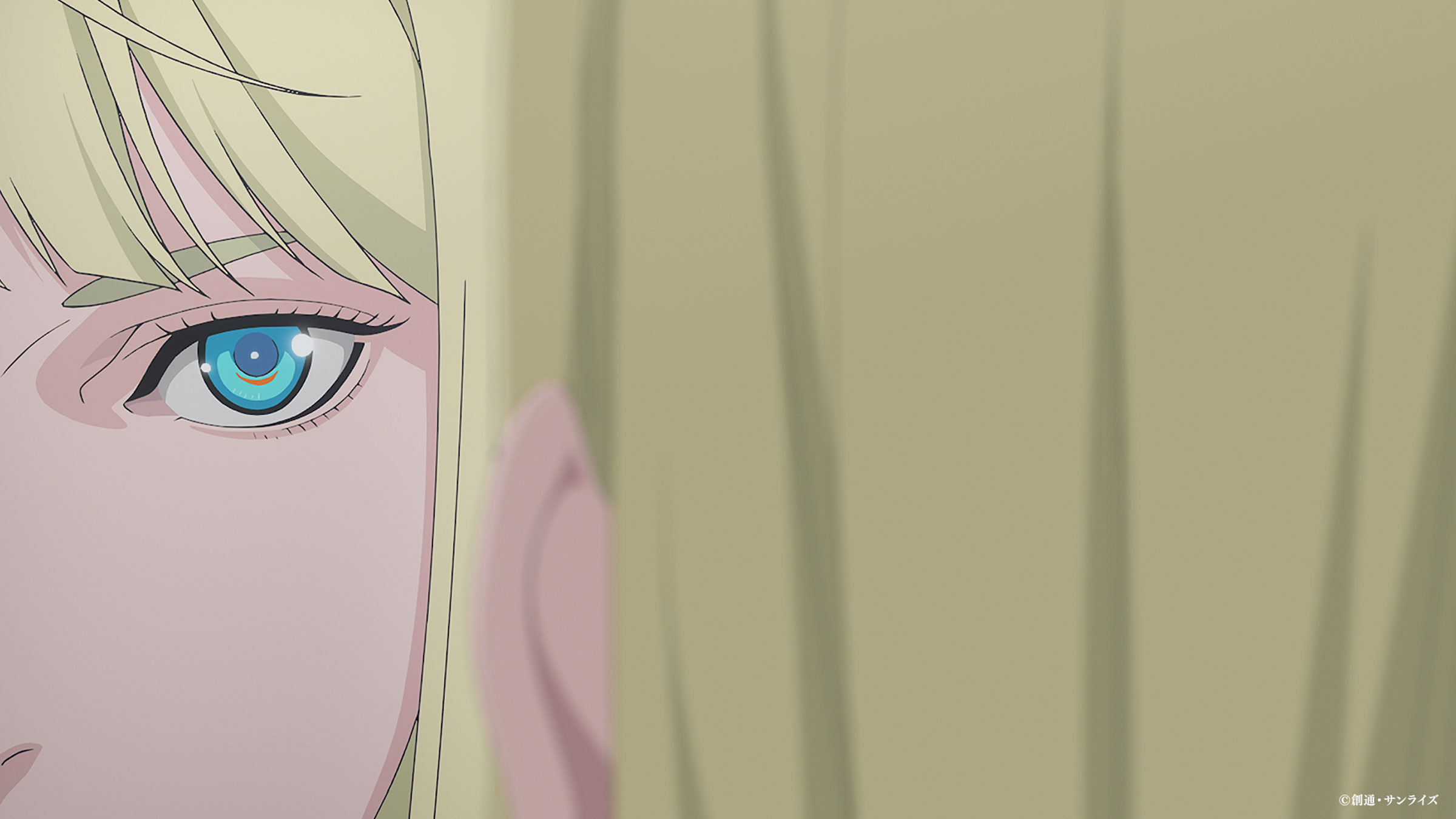- 子役時代を経て演技者の道を歩み始めた古谷徹は、星飛雄馬との出会いによって声優という職業を意識し始めていく。声だけで演じるとは、どういうことなのか。少年から青年へと成長する過程と、『機動戦士ガンダム』の主人公アムロ・レイとの出会いまでを聞いた。
子役から声優への第一歩
- 古谷徹の役者人生は、5歳のときから始まる。児童劇団に入団し、顔出しの子役としてテレビ番組や映画などに出演した。劇団ひまわりへと移籍したあとも、その生活は続いたという。
古谷 劇団みつばという児童劇団に入ったのは5歳のときでした。まだ小学生にもなっていない頃で、幼稚園に併設されている劇団だったと記憶しています。お遊戯の延長線上でバレエやダンス、また習い事として日舞(日本舞踊)をやっていたのですが、演技をするという意識はなくて発表会のような感覚でした。そもそも児童劇団に入ったのは母の意思でした。母は長野県の出身ですが、若い頃にラジオドラマの収録を見学したことがあったらしいのです。そこで俳優さんたちが生き生きと活躍しているのを見て、いつか自分もこういう世界に入りたいと思ったと聞いています。しかし、実際は横浜の豆腐屋、つまり父の実家に嫁ぐことになったわけで、芸能の世界への夢をあきらめざるを得なかった。だから僕が生まれたときに、そんな自分の夢を託したいという気持ちもあったのでしょう。
――日本舞踊を習うのは、子役だけでなく役者の必須科目のように言われますが、古谷さんも習っていたんですね。
古谷 日舞を習うことは、所作や礼儀作法を学ぶという意味が強かったと思います。僕は小柄だったから女形ばかりやらされて、それが嫌で小学5年生くらいで日舞は辞めてしまった。俳優の仕事に役立つということだったけれど、一方で単純に母が好きだったのだろうとも思います。自分の息子が日舞を踊るのが見たかったんじゃないかな(笑)。最初に所属した劇団みつばが解散してしまったあとは劇団ひまわりに入団して、顔出しの子役としての活動を続けることになりました。両親は自営業で、土日とはいえ送迎できる状況ではなかったので、実家のある横浜から劇団がある恵比寿までひとりで通いました。子役としてのデビューは、テレビ番組の戦争ドラマだったと思います。自分の記憶は薄いのですが、空襲を受けて地面に伏せるという役で、付き添いで来ていただけの母もついでに出演してしまった(笑)。親子としてそのまま出演しているので、母もある意味では夢がかなったと言えますね。

――声優としての初出演もこの頃ですか?
古谷 海外ドラマの吹き替えがデビューになります。当時は子役が多くて、自分と同じように子役から声優デビューした人も多かったと思います。でも、そのまま継続できた人は少なくて、それは子役から俳優へと移行することの難しさを如実に表しているとも言えます。つまり、子役としての演技を要求されることに慣れすぎて、スタッフからいつまでも子役として見られてしまうという点がひとつ。それとこれは現実問題として、成長するにつれて容姿も変化していくということです。子供の頃はかわいかったけど、誰もがイケメンになれるわけじゃない(笑)。あと、演技の問題もあります。子役というのは実年齢よりも下の年齢の人物を演じることが多い。子供の頃は自分自身の経験がないと演じることが難しいからですが、それはつまり、実年齢以上のキャラクターを演じることは難しいということでもあります。でも、当時は実年齢に近い中学生や高校生がドラマに登場することは稀でした。子供か、大人のどちらかなんですよ。その時期に躓(つまづ)いて辞めていく仲間も多かった。だから顔出しの役者を目指すなら、子役から始めても途中で一度辞めて、大人になってから再デビューするほうが継続できる場合が多かったように思います。もちろん、人それぞれですから一概に全員がそうだとは言いきれませんが、それだけ子役から大人の俳優へと継続していくのは難しいと思います。
――では、逆に子役から役者を続けているほうが有利ということはあるのでしょうか。
古谷 もちろん、あります。スポーツでもそうですが、幼少時から継続しているほうが経験値も圧倒的に多いですし、それだけ演技というものに対して緊張をしなくなる。演じるということが生活の一部になっているわけですから、自然体で演技に入れるというメリットがあります。演技そのものに集中しすぎることがなく、それ以外の事柄にも気を配れるようになるのは、自身の演技の幅を広げることにもつながるし、仕事として考えても有利だと思います。僕の時代のテレビ番組は生放送か、あるいは撮影所やロケでの収録でした。当時の録音技術では映像と音声を同時に収録することができなかったため、放送用に編集された映像にアフレコをする必要がありました。生放送のテレビ番組は音声も同時に放送されますが、ドラマや映画はほとんどがアフレコです。でも、自分のセリフは撮影時に完璧におぼえていたから、編集された映像を見ながら声だけの演技をすることは難しくなかった。要するに、僕は子役の頃からアフレコという作業に慣れていたということです。それが声優の仕事に役立ったのは言うまでもないことですが、当時は声優という職業はまだ確立されていませんでした。役者として顔を出して演技をするわけではないし、子供向けの番組ばかりということで俳優よりも地位が低いものとされていた。売れていない俳優がやればいいという意識もあったし、声優という呼び方もなくて単に「吹き替え」と呼ばれていた、そういう時代です。
- 声優という職業が俳優よりも格下とされていたのは有名な話である。顔出しで演技をするわけではないから出演料は安くてもいい、洋画の吹き替えなどで収録した音声の再放送使用にも権利がないなどの不遇は、1970年代に多くの吹き替え俳優たちの努力によって次第に改善されていくことになる。古谷徹が子役時代から声優へとキャリアを重ねたタイミングは、声優業にとってはまさに激動の時代だったとも言える。