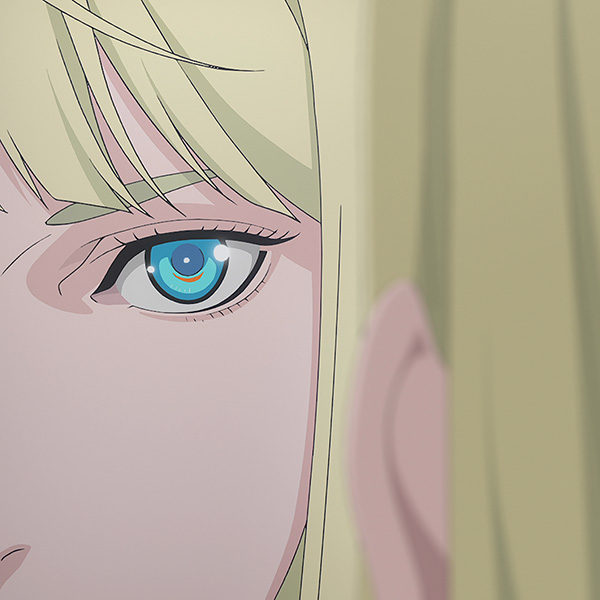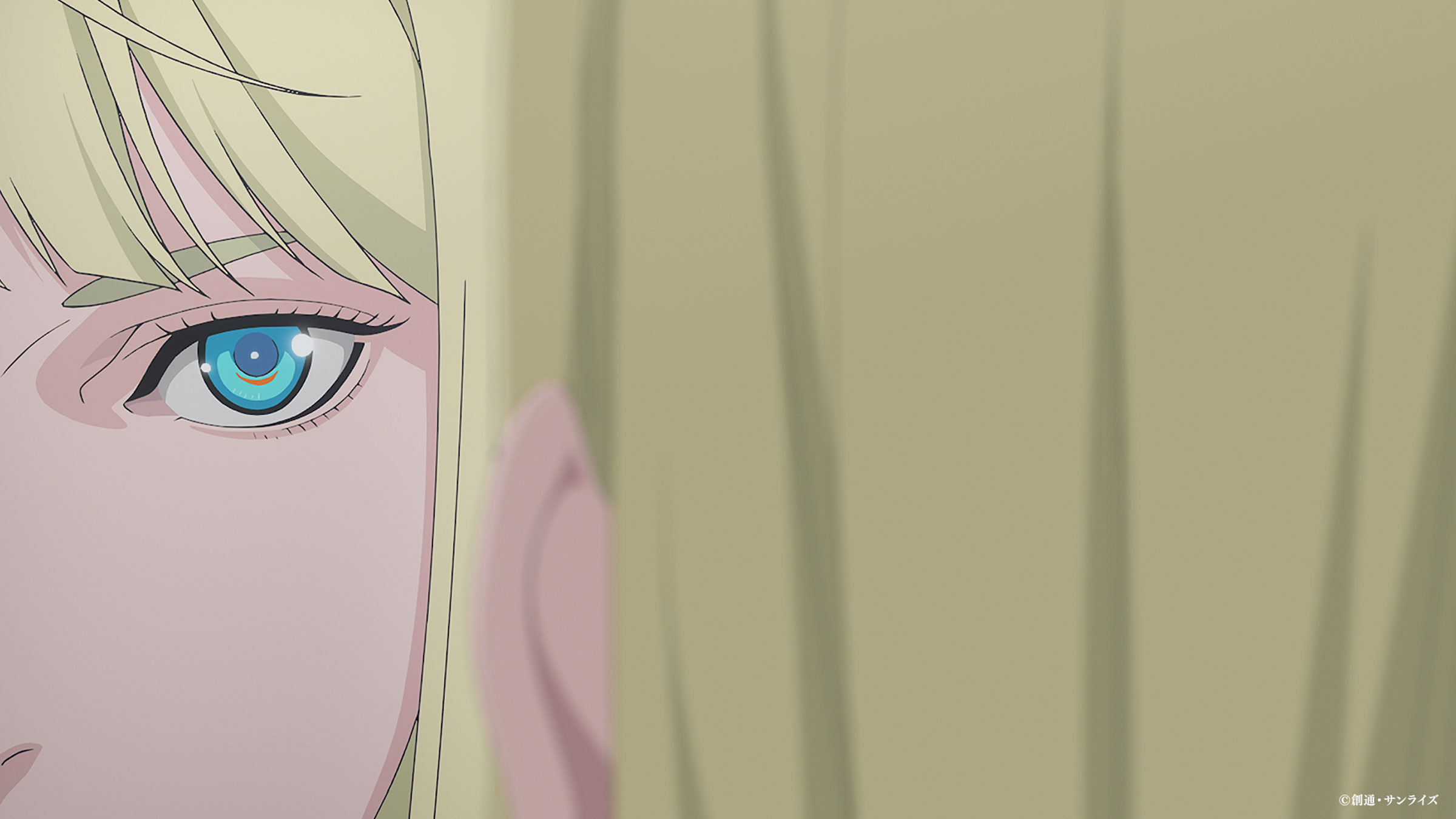自分をさらけ出した、ラストの俳句ラップシーン
――本作では、誰しもが持つコンプレックスと向き合いながらも、そこから一歩踏み出す勇気にフォーカスがあたっています。ラストシーンもそうですが、素直な感情表現がこの作品の魅力というか、カッコつけたくなってしまいそうなところも、ものすごくストレートに描いていますよね。
イシグロ ラストシーンに関しては、キャラクターと一緒に自分をさらけ出したところはありますね。やはり自己を確立していく物語へのこだわりがあったので、気持ちをきちんと声に出して伝えられないというチェリーのコンプレックス、嫌いな前歯を他人に見せられないスマイルのコンプレックスに触れながら、いかにしてその殻を破っていけるか――その原点には、僕が思春期に抱えていた悶々とした気持ちがまずあります。僕自身はそのモヤモヤを、創作することや、何かで表現することでしか解消できなくて。

――クリエイティブに転換していたと。
イシグロ そういうチャンスやツールがあることが重要なので、物語としては、チェリーがあの祭り会場に行くまでの導線をスタッフたちと丁寧に引いていきました。ただ、そこからチェリーが本音を俳句ラップとして叫ぶ、となったときに、やっぱりにじみ出るのはどこまでいっても自分なんですよ(笑)。もちろん、画面に映っているのはチェリーなのですが、あそこで叫んでいるのは自分だなっていう感覚はあります。今でもあのシーンは、恥ずかしいです。
――自己を確立する物語を突き詰めるためには、その恥ずかしさが必要だったんですね。
イシグロ 絶対に必要でした。僕が言うのもアレですが、新海(誠)さんも同じような感覚があるのかどうか聞いてみたいですね。主人公に、どれくらい新海さん本人が入っているのか。イシグロは100%入れました(笑)。
――もし、ラストシーンのシチュエーションになったら、イシグロ監督はチェリーと同じ行動を取るだろうと。
イシグロ そうですね。絵コンテを描いた時点で「覚悟しなきゃ」と思いました。あのパートは、前半をアニメーターのエロール・セドリックさんに、後半を金田尚美さんに原画を描いてもらったのですが、ふたりともデジタル作画なんです。その利点を生かすべく、自分でガイド動画を作っています。シナリオ段階でも、俳句ラップを自分で歌ったものを参考用に作ったのですが、実際に絵に起こしてもらう段階ではさらに一歩踏み出して、自分で俳句ラップを歌っているところを撮影し、Vコンテに編集してセドリックさんと金田さんに渡しました。


――あのシーンのモデルがそもそも監督なんですね。
イシグロ その映像も世の中に出ているタイミングかもしれないですが(笑)、練馬のコミュニティーセンターに機材を持ち込んで、ひとりで撮影してきたものがあるんです。俳句ラップシーン、超恥ずかしいんですけど、それくらいさらけ出さないと、物語が成立しないだろうと。
ミュージシャンとしての矜持を示せました
――僕もその映像は見ましたが、あれはなかなかできることではないですよね。
イシグロ ただ、僕もミュージシャンだったので、その矜持は示すことができたかなと思うんです。僕はボーカルではなかったですけど、曲を作るし歌を歌うこともできたので、ステージや舞台の上に立ったとき、マイクを持つ手がどうなるかとか、僕のミュージシャン的な視点を生かすことができたわけです。
――ラストシーンの裏側ですね。
イシグロ だから、1回目はこの情報なしで見てもらいたいですね。2回目からは「あれは監督がやっているのか……」と思っていただければ、また違った印象が得られるかもしれません(笑)。

――それくらいイシグロ監督のピュアな感情が閉じ込められているわけですけど、スタッフとして参加している奥様の愛敬さんからは、何か感想をもらうことはありましたか?
イシグロ 助かったというか、そのあたりは作品を通してフラットに見てもらいましたね。俳句ラップの映像を奥さんも見ているのですが、何か恥ずかしいものとしては捉えていなかったように思います。ちゃんとチェリーを通して見ていてくれたので。
――必要な要素だとわかっていたからこそ。
イシグロ キャラクターデザインや総作画監督の立場からは「すごくいいことだと思う」と言ってくれました。それはうれしかったですね。
いちばん難しい「踏み出すこと」の大切さを伝えたい
――基本的には若者に向けた作品だと思いますが、作品を見終わったときに背中を押せるようなもの、という意識はありましたか?
イシグロ それはもちろんありました。恋愛映画のテイストですが、内容はキャラクターたちが自己確立をしていく青春ムービーですから。僕自身は創作を通してでしかコンプレックスや心のなかにあるモヤモヤを解消できなかった、と先ほど言いましたが、チェリーは、俳句という創作活動を通して自分の感情を表現していく。自分を表現するって若ければ若いほど怖いことだと思うのですが、ダイレクトに気持ちを届けるには一歩踏み出すこと、そしてちゃんと届けたい対象の人の目の前で声を発することが重要で。僕自身、青春時代にそれができた部分とできなかった部分があって、できなかった部分のモヤモヤは40歳を過ぎてもある(笑)。若い時代のことは若い時代に解決したほうがいいし、解決する方法はたくさんあるんだぞというメッセージを伝えたくて作った作品ではあります。

――コンプレックスというものが解消できるか否かは別としても、それと向き合っていくことでしか生きていけない側面はありますよね。
イシグロ そこが重要だと思います。建設的に考えて一歩踏み出すことが大事。たしかに結果も大事ですが、まず踏み出すっていう行動ですよね。それが難しいのは重々承知ですけど、自分のペースでそれができればいい、と思っています。
――若者向けとは言いましたが、レコードショップでいろいろな世代の人たちが集まりますし、ショッピングモールのなかにデイサービス施設があって、そこでチェリーが働いていたりと、現代社会の実情みたいなものもうまく反映されています。そういう意味では、さまざまな世代とその交わり方を捉えた作品でもあります。
イシグロ チェリーを含めた3世代が登場する物語ですし、脚本の佐藤大さんとも話していたのですが、遠くない未来にはこういうデイサービスがもっと身近になるだろうし、一方でフジヤマのおじいさんを通して、僕たちが経験していない数十年前の世界を描いています。そういう現在、過去、未来の流れは感じてもらいたかったもののひとつですね。核家族が多いと思いますけど、おじいちゃんおばあちゃんと暮らしている人はデイサービスも身近でしょうし、ショッピングモールって、そういうあらゆる世代が違和感なく集まる場所だから舞台にしたというのもあります。

――作品のサブテーマとしてしっかり組み込まれているわけですね。
イシグロ 世代だけじゃなくて、いろいろな国の人が移住して一緒に暮らしているのが数十年先には普通になる。そういう時代の流れを反映させることが、物語の奥行きになると思っていました。
――そのなかでもレコードというメディア、カルチャーを核にしたのは、ミュージシャンであったイシグロさんらしいアイデアだと思いました。
イシグロ そう言っていただけるとありがたいですね。