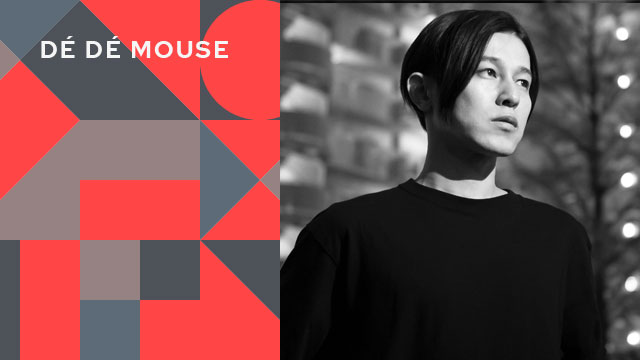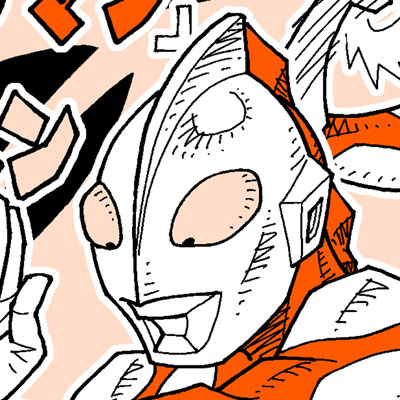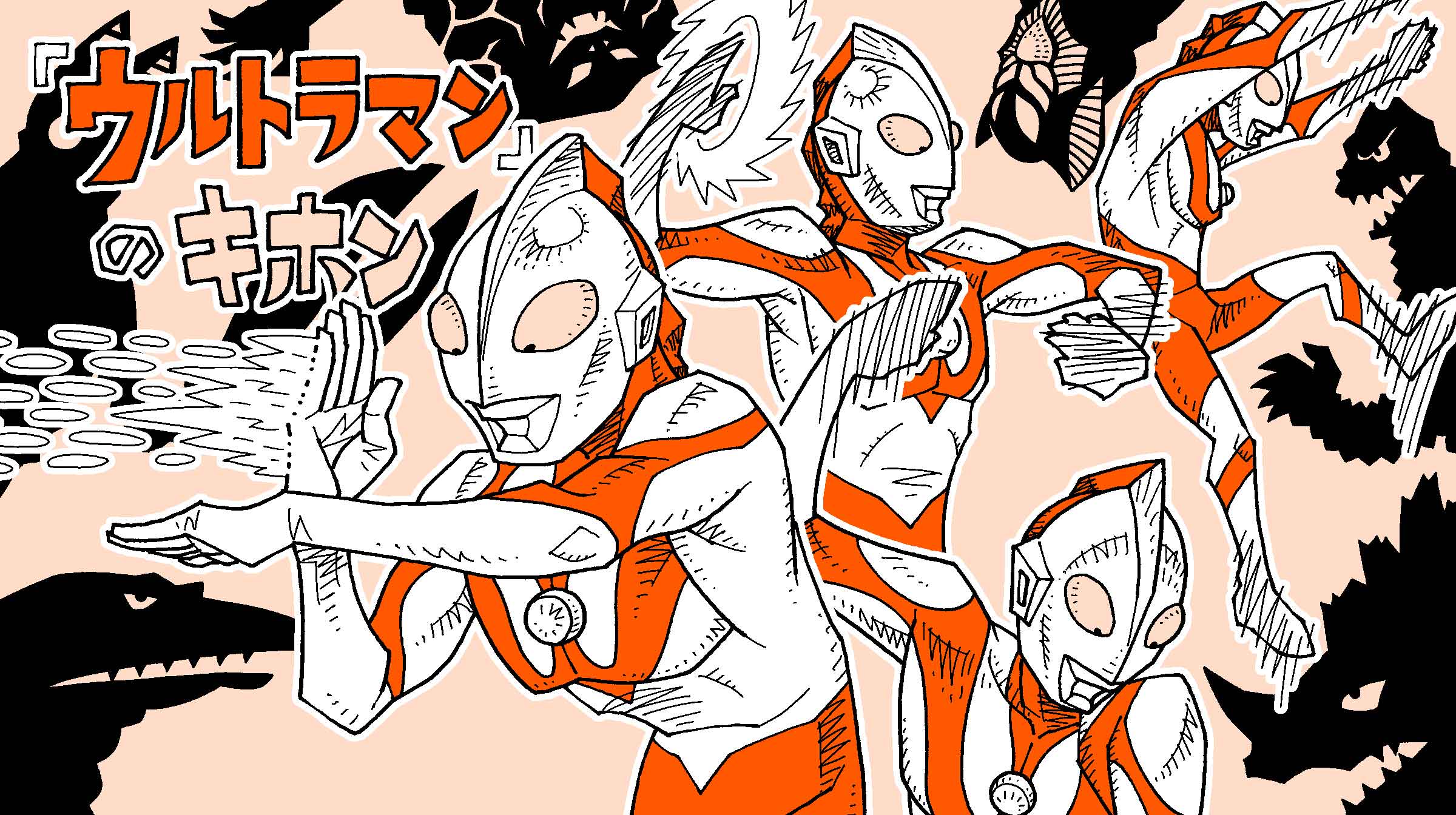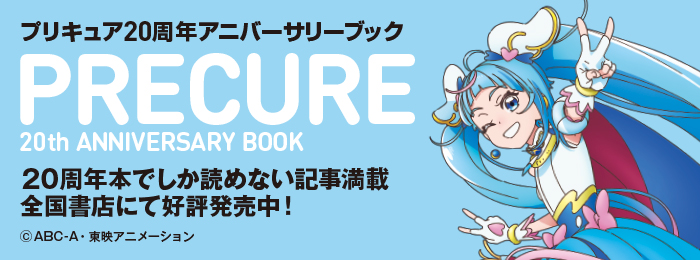作った人の影響力によって作品が大きく変わる
――事前に、村田監督にとって特別なアニメ作品を3本挙げていただきましたが、1本目が『未来少年コナン』。宮崎駿監督の名作TVシリーズですね。
村田 僕は1964年生まれなので『未来少年コナン(以下、コナン)』の本放送のときは中学2年生でした。前情報で、NHKで初めて放送される30分枠のアニメシリーズということは耳にしていたので、気になって見始めたんですよね。
――そのときの印象というと?
村田 当時、フジテレビでやっていた「世界名作劇場」の一連の作品に、映像の印象がすごく似ているなと思いました。『コナン』の2年前に『母をたずねて三千里』が放映されて見ていたんですけど、この作品にも衝撃を受けたんですね。「世界名作劇場」なので、小さい子供が見るものだと思っていたら、作品内の世界の実在感だったり、空間の表現のリアルさに驚いたんです。線はシンプルだし、キャラクターは丸っこくて、絵柄自体はリアルとは言いがたいんですが、まるで世界がそこに存在しているように感じる。『コナン』が始まったときにも、それと同じような感覚を受けたんです。ただ、『コナン』のほうはSFで、「世界名作劇場」とジャンルはぜんぜん違うんですが。第1話の冒頭と各話のアバンで使われている、ギガントの大群が飛んでくる場面とか、世界が超磁力兵器で破壊され、大陸がみんな沈んでしまう……みたいな大仕掛け感は「世界名作劇場」にはない要素です。人類文明が崩壊したあとの世界、いわゆるポストアポカリプス的な世界を舞台に、崩壊した世界のなかで生きていく人々を描いた日本のアニメで、初めて触れた作品が『コナン』でした。
――SF的な世界観も魅力のひとつですね。
村田 初めて見たのに、古典というか、娯楽としての王道を感じたのも印象的でした。『コナン』は、次の話が絶対に見たくなる作りになっていて、「次はどうなるんだ?」とすごく気になってしまう。続きものってこうだよねっていう作り。そして30分がとても短い。引き込まれている証拠ですね……。とはいえ、途中までは「面白く」はあったけど、自分のなかではスペシャルな作品ではなかったんです。後半、話がどんどん深刻になっていくにしたがって、物語のスケールも大きくなっていく。そしてギガントが出てきたあたりで「なんだこれは!」と。「これはちょっとスゴい作品なんじゃないか」と思いながら一気にのめり込んで、そして最終回を見終わったときには、自分のなかでとてつもなく大きな存在になっていたんです。

――なるほど。
村田 出来事のひとつひとつがとても重要な意味を持っていて、物語のなかで大事な役割を果たしている。そして、それらが全部つながっている。場所やアイテム、キャラの持つ意味や関係性が、話数を追うごとにどんどん変化していく。そういったことがとても新鮮でした。ジムシィやダイスやモンスリーなど、登場したときは敵だったキャラが、対立を重ねるなかで仲間になっていく。その関係性を変えていくのが主人公であるコナンの行動とパワーで、それを引き出すのがラナの存在。キャラの関係性がとても有機的かつ立体的、そして動的に組み上げられています。メカにおいても、第1話から出てくるファルコという飛行艇は、シリーズを通じて活躍しますが、次々にその役割が変わっていく。ダイス船長のバラクーダ号(帆船)もそう。場所に関しても同様で、のこされ島もインダストリアも、一度目と二度目で違う意味を持つ。出来事そのものも有機的につながっていて、さらにその「見せ方」がうまい。たとえば、ガンボートの回(第18話)。コナンたちが火薬を仕掛けてガンボートを爆破するんですけど、このことでインダストリア側の目論見が一気に崩れ、流れが変わる。圧倒的な工業力の象徴であるガンボートに対して、手作りのタル爆弾ひとつで挑むコナンたち。その話数でたった一度の爆発なんですが、そこに至るまでの過程がとても丁寧に描かれていて、事の重要さが際立っている。次の大津波の回もそうですよね(第19話)。壊れたバラクーダ号をモンスリーたちが島民を使って引き上げさせる作業のさなか、浜では波が引き始める。異変を察知し、テレパシーでコナンに伝えるラナ。モンスリーを説き伏せるコナン。迫る津波。人間側の対立と津波の接近という自然現象が並行して進んでいく。そして津波が来てバラクーダ号が丘の上に打ち上げられ、モンスリーたちの計画が頓挫するまでを、まるまる1話かけて描く。しかも、その津波はたまたま来たものではなく、のちに起きる大地殻変動の一連の前フリとしても機能している、という。シリーズ全体を通して、すべての出来事が緊密につながっているということを、最終回を見終わったあとに強烈に感じたんです。そして、それを支える映像の美しさと動きのダイナミックさ。で、「これを作った人はスゴいに違いない!」と(笑)。
――制作者に興味が向いたわけですね。
村田 そうなんです。もちろん、それまでもアニメは人間が作っていることはわかって見ていたんですけど、作った人の力によって出来上がった作品が大きく違うものになるというのを、初めて感じたのが『コナン』でした。「すごいものを見たんだ」という印象がずっと尾を引いて、その後の自分の人生にも影響を及ぼしていますね。
――当時、熱気を共有する友達はまわりにいたのでしょうか?
村田 全然いなかったです。一度だけ、誰かに「『コナン』っていうのが面白いよ」と話したんですけど「ふぅん……」みたいなリアクションで(笑)。『コナン』が放送された1978年って、夏に『さらば宇宙戦艦ヤマト』が公開されて、世間的にはアニメの大ブームが巻き起こるんです。とはいえ、一緒に『コナン』に注目が集まるわけでもなく……。そのときに『コナン』の特集を組んだのが、のちにスタジオジブリのプロデューサーになる鈴木敏夫さんが編集に関わっていた雑誌『アニメージュ』なんですよね。宮崎さんのイメージボードを掲載したり、登場メカを取り上げたりして、「あっ、ここにわかっている人がいる!」と(笑)。あとマイナーなんですが、ブロンズ社というところから出ていた『月刊アニメーション』という雑誌。ここには宮崎さん自身の文章や、ラピュタの元になるイメージボードなんかが載っていたりして。そこで初めて、自分が「すごい」と思っていたものが本当にすごいんだと確信を持てたんです。
――村田さんはその後、宮崎さんたちが立ち上げたスタジオジブリに入りますよね。『コナン』の影響もあったんでしょうか?
村田 そうですね。ジブリに入ったのもそうですし、僕が監督した『翠星のガルガンティア』もある意味、『コナン』に対する自分なりのオマージュでありアンサーみたいなところがあるんです。
――ああ、なるほど。『コナン』と同様、文明が滅んだあとの世界が舞台だったり。
村田 僕としては、ポストアポカリプスの世界を明るいものとして描きたかったんです。いろいろあるけれども、人々が力強く生きていける場所として崩壊後の世界を描く。そこは『コナン』からの影響があると思います。海の底から遺物を引き上げて再利用する、という発想もそうですし。『コナン』の冒頭、海の底にビルが沈んでいるんですけど、上半分がニョキっと海から突き出していて、木が茂っていて。そういう風景自体、すごく新鮮だったんですよね。パッと一枚、絵を見るだけで、その景色がそこに生まれるまでの出来事の積み重ねや時の流れを感じさせてくれる。そんなアニメは『コナン』が初めてでした。![]()
KATARIBE Profile
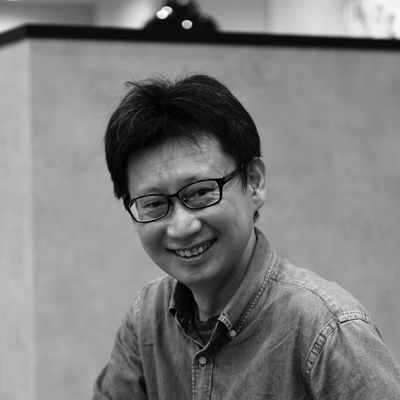
村田和也
監督
むらたかずや 1964年生まれ。大阪府出身。一般企業に就職したのち、スタジオジブリに研修生として入社。その後、OLMの設立に参加し、フリーに。主な監督作品に『鋼の錬金術師 嘆きの丘(ミロス)の聖なる星』『翠星のガルガンティア』『A.I.C.O. -Incarnation-』『正解するカド』(総監督)など。