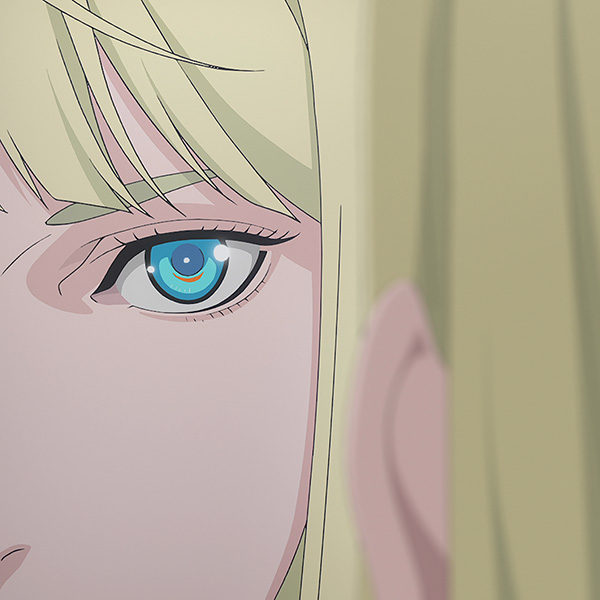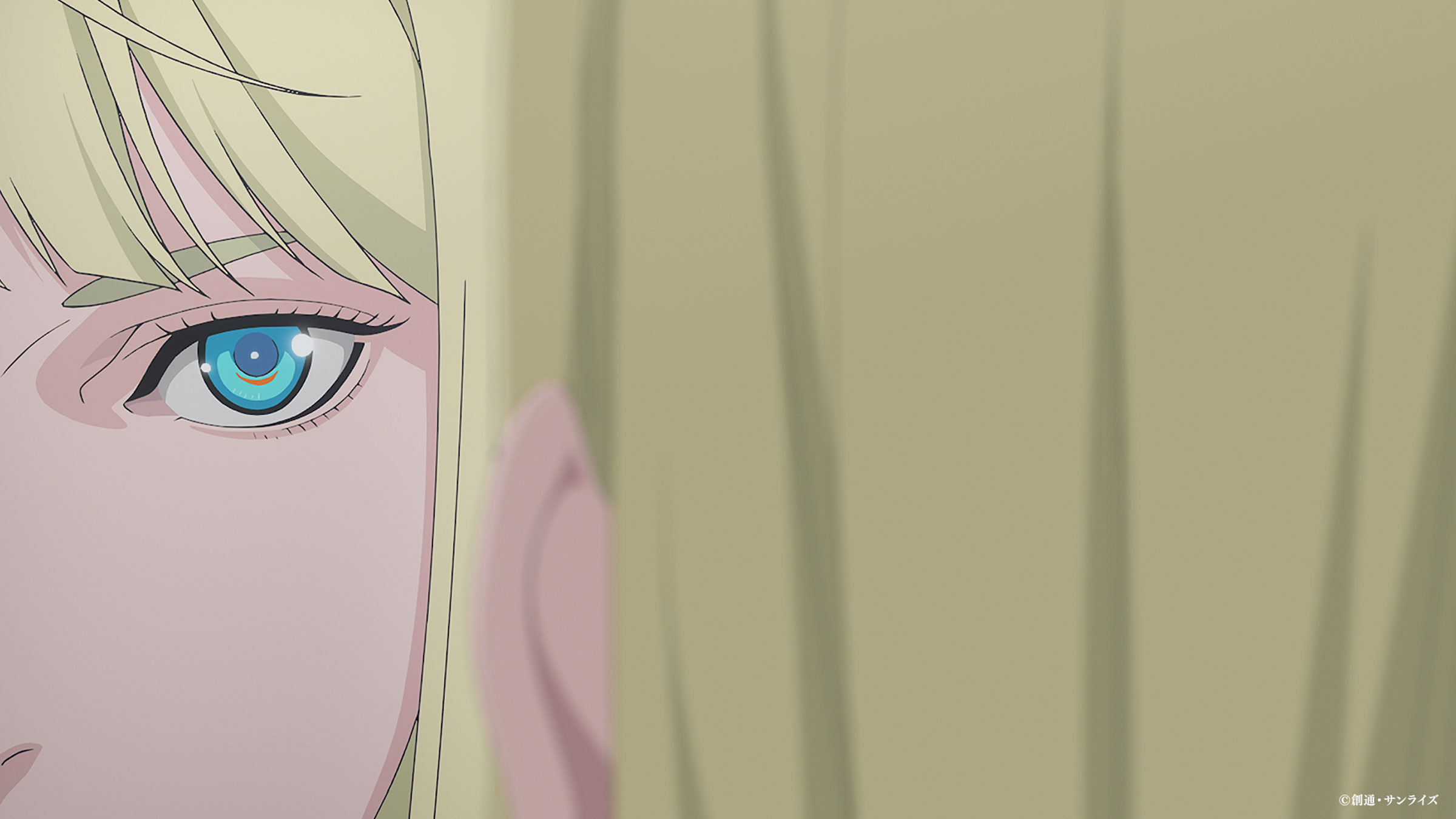『うる星』の作り方からは、いまだに影響を受けています
――3本目は『うる星やつら(以下、うる星)』ですが、これは『重戦機エルガイム』よりも前になりますよね。
佐藤 そうですね。『うる星』が本当に最初の入口というか。当時は『宇宙戦艦ヤマト』も『機動戦士ガンダム』も『ルパン三世』も――それこそ空気みたいなモノというか、何か特別なものではなくて、オタクじゃなくてもみんな見るモノだったんです。で、『うる星』もその中のひとつで。
――アニメを先に見た感じですか?
佐藤 いや、『週刊少年サンデー』を読んでいたから、原作が先ですね。当時はちょっとエッチな少年マンガ、みたいなイメージでした。で、第1話の最後、ラムちゃんの水着が取れるシーンが見たくて、アニメを見始めるんです。
――あはは。
佐藤 ただ、そうやって続けて見ているうちに、だんだんと様子がおかしくなっていくんですよ。急に爆撃機とか戦闘機の話になったり、突然、舞台みたいなことをやり出したり。3~4回に1回くらい、頭のおかしいエピソードが入り始める。決定的だったのは第1シーズン後半かな。面堂終太郎のエピソードがあって……。
――第27話「面堂はトラブルとともに!」ですね(笑)。
佐藤 そうそう! そこで、脚本の伊藤和典さんと押井守監督のことを知るわけです。どうやら監督と脚本家というものがいて、この人たちが何かやるとヘンなことが起こるっぽいぞ、と。アニメと並行して『オレたちひょうきん族』みたいなバラエティ番組も大好きだったし、あとYMOはYMOで「スネークマンショー」みたいなアルバム(『増殖』)を出していたんですけど、『うる星』は「アニメでコントみたいなことをやっているぞ」という。
――メタフィクションというか、メタっぽいギャグのノリが濃厚に漂っていますよね。
佐藤 いきなりオチをブン投げて終わって、翌週はまた全然違う話をやるとか。そういうのが好きなんだなって自覚するようになっていくんです。……まあ、今考えるとたぶん、かわいい女の子の水着姿を見るための言いわけだった気がしないでもないんですよ(笑)。ただ、親から「またアンタ、そんなアニメばっかり見て」って言われるのに対して「いや、これ、すごいんだよ」と。そういうエクスキューズが『うる星』にはあって。しかも、それが『(うる星やつら2)ビューティフル・ドリーマー』で大爆発するんですよ。

――1984年に公開された、押井監督の初期の代表作ですね。
佐藤 「ほら、言ってた通りでしょ?」と。とにかく『うる星』には幕の内弁当みたいな感じがあって、作画的にも見どころがたくさんあるし、たとえストーリーが破綻していても、翌週になればリセットされて、また次に面白いことができればいい、みたいな感覚がある。そこがすごくフィットしたんです。それこそ、僕らのあとの世代が『涼宮ハルヒの憂鬱』を見て感じているようなことだったり、あるいは『進撃の巨人』を見ながら、その裏にあるものを勝手に想像しているのに近い感じで、『うる星』の裏には何か、いろいろなものがいっぱい渦巻いているんだな、と。そういう熱量みたいなものを感じていたんですよね。
――押井監督も脚本の伊藤和典さんも20代後半から30代頭。いちばん脂が乗っている時期の仕事ではありますよね。
佐藤 自分と同じ世代の人たちが作っているっていう感覚も強かったですね。あと、こういうものを作るスタッフに対して憧れを抱くようになったのは、間違いなく『うる星』の影響で。もちろん、その前にも『ガンバの冒険』とか『あしたのジョー』みたいな、自分の精神的支柱になった作品はあるんですけど、でも、スタッフに興味を持つようになったのは『うる星』と『重戦機エルガイム』が大きい気がします。
――今でも『うる星』からの影響を感じることってありますか?
佐藤 あります、あります。渡辺信一郎監督の『スペース☆ダンディ』をやっていたときとか、ずっとそういう話ばっかりしていましたね。自分たちが見ていたレジェンドと現役のレジェンドと、これからレジェンドになっていく人たちがいっぱいいて、みんなでアイデアを出して作っていく、みたいな作品でしたから。しかも『うる星』と同じように、どれだけぶっ壊れたエピソードになっても、話数ごとにリセットすればOKっていう。そういう作り方の影響みたいなものは、今でもあると思います。![]()
KATARIBE Profile

佐藤大
脚本家
さとうだい 1969年生まれ、埼玉県出身。専門学校在学中から放送作家として活動をスタートし、1997年に放映された『永久家族』で初めてアニメ脚本を手がける。主な代表作に『交響詩篇エウレカセブン』『怪盗ジョーカー』など。2021年7月22日公開の『サイダーのように言葉が湧き上がる』に脚本として参加。