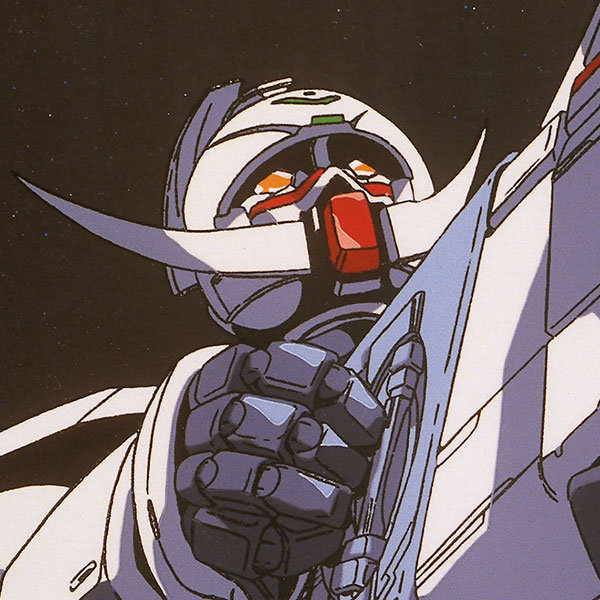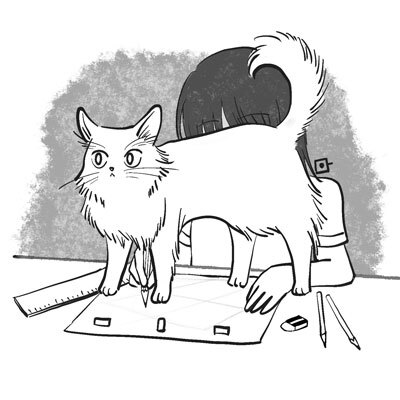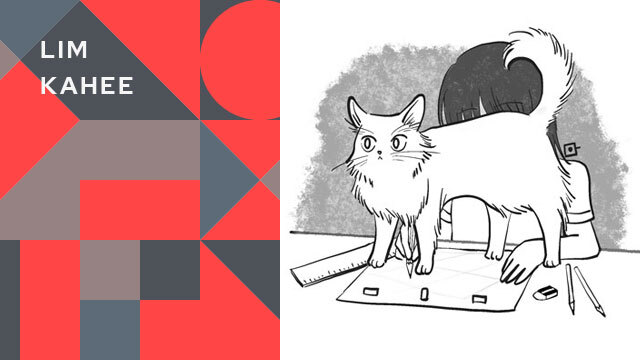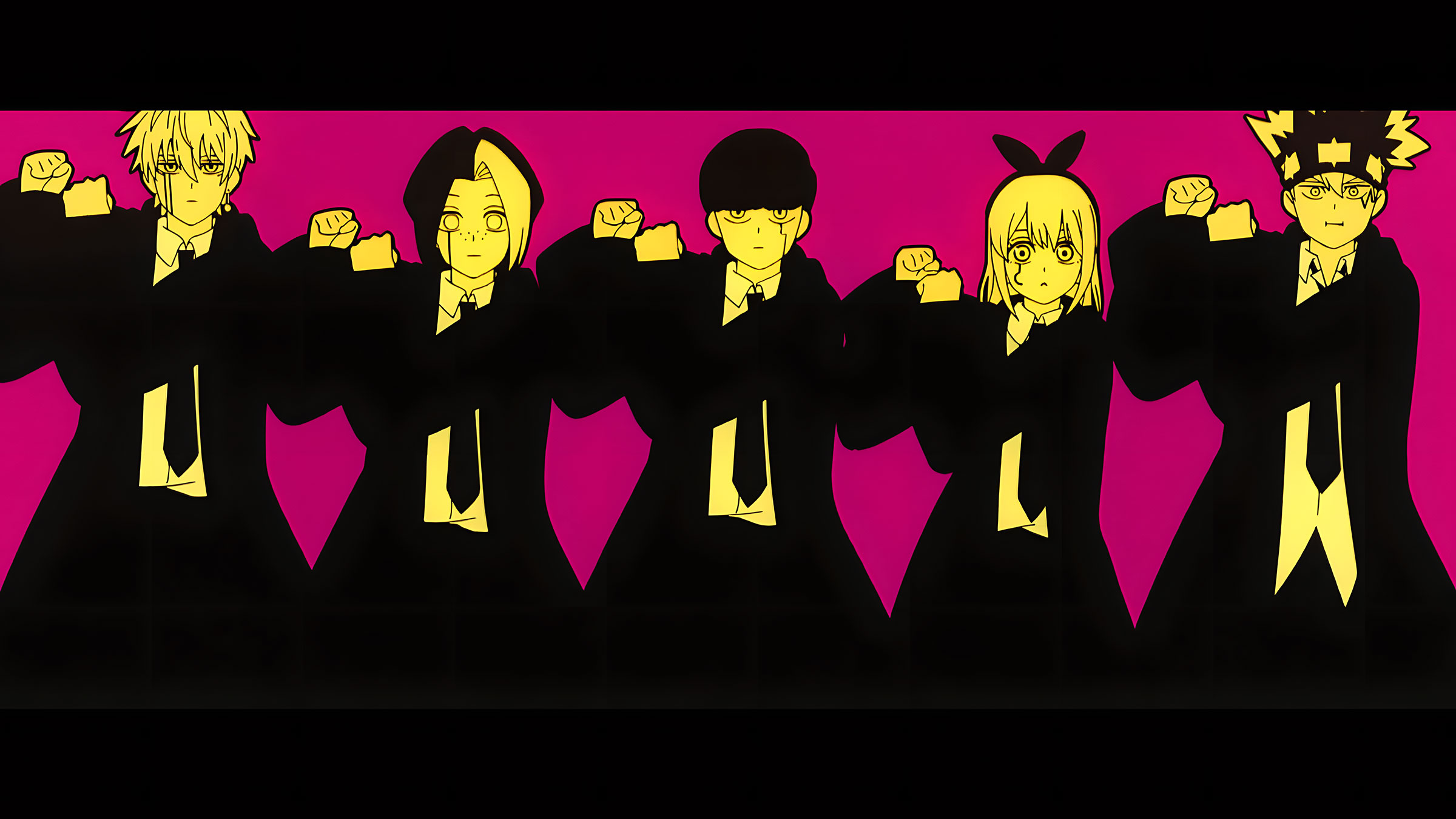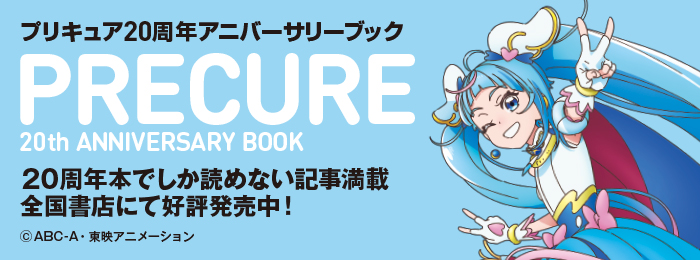小学生の頃、友人とマンガ雑誌ごっこをして遊んでいた
――子供時代はどんな絵を描いていましたか?
さいとう 幼稚園の頃は『鉄人28号』など、主にロボットの絵をたくさん描いていました。ふにゃっとした生き物の線より、シャキーンとしたシャープな線を描くのが楽しかったんだと思います。姉も絵がうまかったので、小学生になると、姉と私と友達の3人でマンガ雑誌を作って遊んでいました。それぞれが好きなマンガを描いて、それをホッチキスで止めて製本して。「新連載続々!」なんて煽りも書いて(笑)、裏表紙には手描きの広告を載せて。
――当時のさいとう先生はどんなマンガを連載していたんですか?
さいとう 『アタックNo.1』や『サインはV』などのスポ根ものが全盛だったので、その影響を受けてバレーボールマンガを描いていました。皆でテヘランオリンピックを目指そう!みたいな。なぜテヘランだったのか、今考えると謎なんですけど(笑)。
――そのマンガ雑誌作りはいつまで続いたんですか?
さいとう 小学生の間は続きましたが、中学生になると解散してしまって、私自身もそれからしばらくはマンガから離れていました。
――その時期はどんなことを?
さいとう 入学してすぐにテニス部に入ったんですけど、部員が多すぎて全然球を打たせてもらえなくて、頭にきて1ヵ月で辞めました(笑)。それから漫研に入ったんですが、マンガはほとんど読まず、映画を見たり音楽を聞いたりしていて。でも、あるとき友達から「ちほちゃんって絵がうまいんでしょ? これ描いてよ」と『ベルサイユのばら』を渡されたんです。それで、そっくりの絵柄を一枚描いたらすごく喜んでくれて。すると、その話が広まり、いろいろな人がマンガを携えては「これを描いて」と私を訪ねてくるようになって。竹宮惠子先生の『空がすき!』とか萩尾望都先生の『ポーの一族』などの絵柄をそっくりに描くのが中学生時代の日課でした。皆から絵がうまいと褒められたことでいい気になり(笑)、いつの間にか「私はマンガ家になるんだ!」と思うようになっていました。
――それで再びマンガを描くようになったんですね。
さいとう そうです。高校で漫研に入り、夏休みには漫研の部員全員で『ベツコミ』の編集部を見学させてもらったこともあります。ただ、そのときは竹宮先生や萩尾先生の生原稿が見てみたいというミーハーな気持ちで見学していたので、自分の作品の持ち込みはオマケみたいな感覚でした。本格的に投稿を始めて担当さんがついたのは20歳前後だったと思います。
――そこからデビューまでの経緯は?
さいとう 担当さんの異動にくっついて『ベツコミ』から『少女コミック(現・Sho-Comi)』に移った途端、好きなものを描いていいと言われ、『三銃士』マニアだったので三銃士をモチーフにした『剣とマドモアゼル』を描いたら、それがそのままデビュー作になりました。しかも、「次号から4週の連載枠を確保したから」と言われて。わけもわからないうちに、急に忙しくなりました。
――一気に連載デビューまで漕ぎ着けたんですね。順風満帆じゃないですか。
さいとう でも、その連載が大コケしたんです(笑)。私はこれまで西洋ものばかりを描いてきたんですが、当時の『少女コミック』に載っている作品は現代日本を舞台にした学園ものがメインで、そこは避けては通れなかったんです。それで私も挑戦してみたんですが、案の定まったく人気が出ず……。そのときは、けっこうへこみましたね。
私、基本的に悪いことをする人が好きなんです(笑)
――それが『とんでるみたい』ですね。これは単行本化もされず?
さいとう されていません。というか、してほしくない(笑)。ありがたいことに、その後もコンスタントに読み切りマンガを描かせてもらえたのですが、学園ものは最後まで自分になじまず、そこで何年も足踏みしました。
――たしかに、この時期のさいとう先生は膨大な数の短編を描いていますね。
さいとう 毎週のようにゼロからキャラクターや設定、物語を作らないといけないので苦労しました。そんな中でようやく少し手応えを感じたのが『ウエディングtoゆう』というラブラブな新婚カップルを描いた作品でした。すでに結婚していたこともあり、担当さんから「描いてみたら?」とすすめられたんです。内心では「新婚なんてそんなに甘いもんじゃない」と毒づいていたんですが、新婚を描いた作品がレアだったのか、ちょっとだけウケたんです。ラブラブな恋愛作品って、映画などで見るのは好きでも、自分が描くとなるとすごく恥ずかしくて躊躇していたんですが、この道しかないのならと自意識をなんとか砕きました(笑)。こういう恥ずかしい路線で勝負しようと決心してからは、積極的にラブラブな恋愛を描くようになりました。
――そんな葛藤があったんですね。では、そのときの手応えが「いける」という確信に変わった作品は何ですか?
さいとう 『円舞曲は白いドレスで』や『もう一人のマリオネット』の時期だったと思います。とくに『もう一人のマリオネット』は印象深くて、担当さんが自分でシナリオも書けるような方だったので、とにかく引きのある物語を作ろうとふたりで試行錯誤しました。読者を驚かせることが最優先事項だったので、荒唐無稽な設定をぶち込んでは「続きは来週考えよう」の繰り返しで(笑)。
――神真之が二重人格だったというのも、もしかして……?
さいとう 後付けです。新しい設定を加えながら、どう収束させようかといつも頭を抱えていました。力技の限りを尽くした作品でしたが、不思議とそれらがカタカタと音を立てて組み合わさって、然るべきところに収まる感覚があり、どうにかなるものだなと(笑)。
――一方の『円舞曲は白いドレスで』ですが、これは初の歴史もの作品ですね。
さいとう そうなんですが、主な舞台は1930年代の日本ですから、私がずっと描きたいと思っていた中世ヨーロッパの歴史ものとは少し違いますね。これは、あの時代の軍人たちを描きたくて作りました。
――ということは、中〜近世の西洋を舞台とした『花冠のマドンナ』こそが念願の歴史ものだったんですね。
さいとう これは、もう念願が叶った気持ちでした。馬とマントが好きすぎて、とにかく馬に乗ったマントの男を描かせてくださいとお願いして(笑)。美術巡りの旅でイタリアにはよく行っていたので、舞台も描きやすかったです。
――チェーザレは歴史上の人物ですが、なぜ彼を描こうと思ったんですか?
さいとう チェーザレについて書かれた塩野七生さんの本(『チェーザレ・ボルジアあるいは優雅なる冷酷』)が好きだったんです。私、基本的に悪いことをする人が好きなんです(笑)。それも、ただの悪人ではなく、必要ならばどんな手段も厭わない、悪のカリスマ的な雰囲気が好きで。
――昔からワルい男が好みのタイプなんですか?(笑)
さいとう そうですね。幼稚園の頃から大河ドラマを見ていて、少年が兄弟や親にいじめられ、でも、その復讐心を糧にのし上がって逆襲するみたいな展開が大好きでした! 宝塚歌劇でも強くてたくましい立役(男性役)のほうが好きですし、きっとそれが私の萌えの原点にあるんだと思います。
『少女革命ウテナ』からセクシーで肉感的な絵に変化した
――それが、さいとう先生が描く魅力的な男性キャラにつながっているんですね。さらにその後、アニメ作品としても有名な『少女革命ウテナ』に携わることになります。
さいとう もともと「さいとうちほの世界をアニメ化して少女向け作品を作ろう」という企画だったのが、作るうちにどんどん濃いものになり、最終的には私の作風とはかけ離れた作品になりました(笑)。だから、自分の子供ではあるけれど、どこか継子のような存在ですね。
――制作中はどんな気持ちだったんですか?
さいとう すごく楽しかったですよ。スタッフのひとりとして「何でも描きますよ〜」という気持ちでいましたし、合宿してシナリオを練るなど、チームで創作していくスタイルも新鮮でした。なにより作品の全責任は幾原(邦彦)監督が被ってくれますから、とにかく気楽(笑)。
――アニメスタッフから刺激を受けたことなどはありましたか?
さいとう いろいろありましたが、とくにキャラクターデザインってここまで時間をかけるものなのかと驚きました。胸やお尻、足など、女性のパーツに関するこだわりと要求がスゴくて(笑)。最初は「こんなに胸を強調しないとダメですか?」と抵抗していたんですが、だんだんと男性視点を意識するようになりました。それまで積み上げてきた私の「少女マンガ像」が少し壊されましたね。『少女革命ウテナ』以降の私のヒロインは、ちょっとセクシーで肉感的な絵に変化したと思います。
――出来上がった作品にはどのような感想を持ちましたか?
さいとう 私のアイデアやキャラクター、世界観が使われていても、料理の仕方が違うだけでこんなにも雰囲気の違う作品になるんだと驚きました。同時に、幾原監督をはじめとしたスタッフの皆さんが私の作品をとことん分析してくださり、自分でも気づかなかった特徴や個性を教えてもらったような気もします。自分の作品についてそこまで深い話をするのって編集者以外にはいませんから。![]()