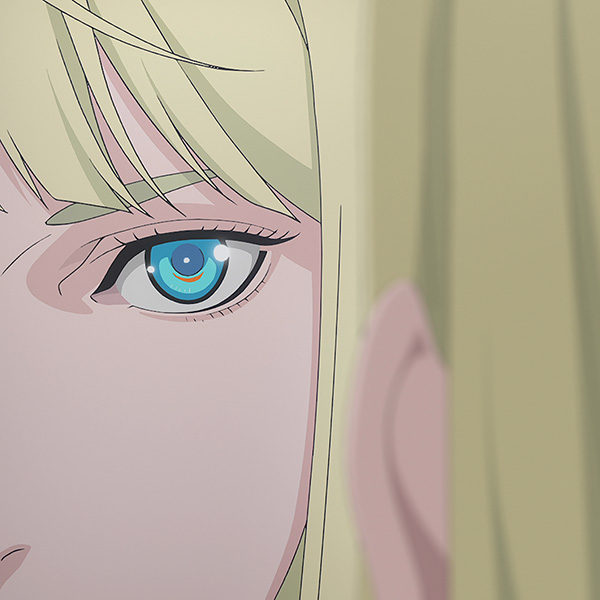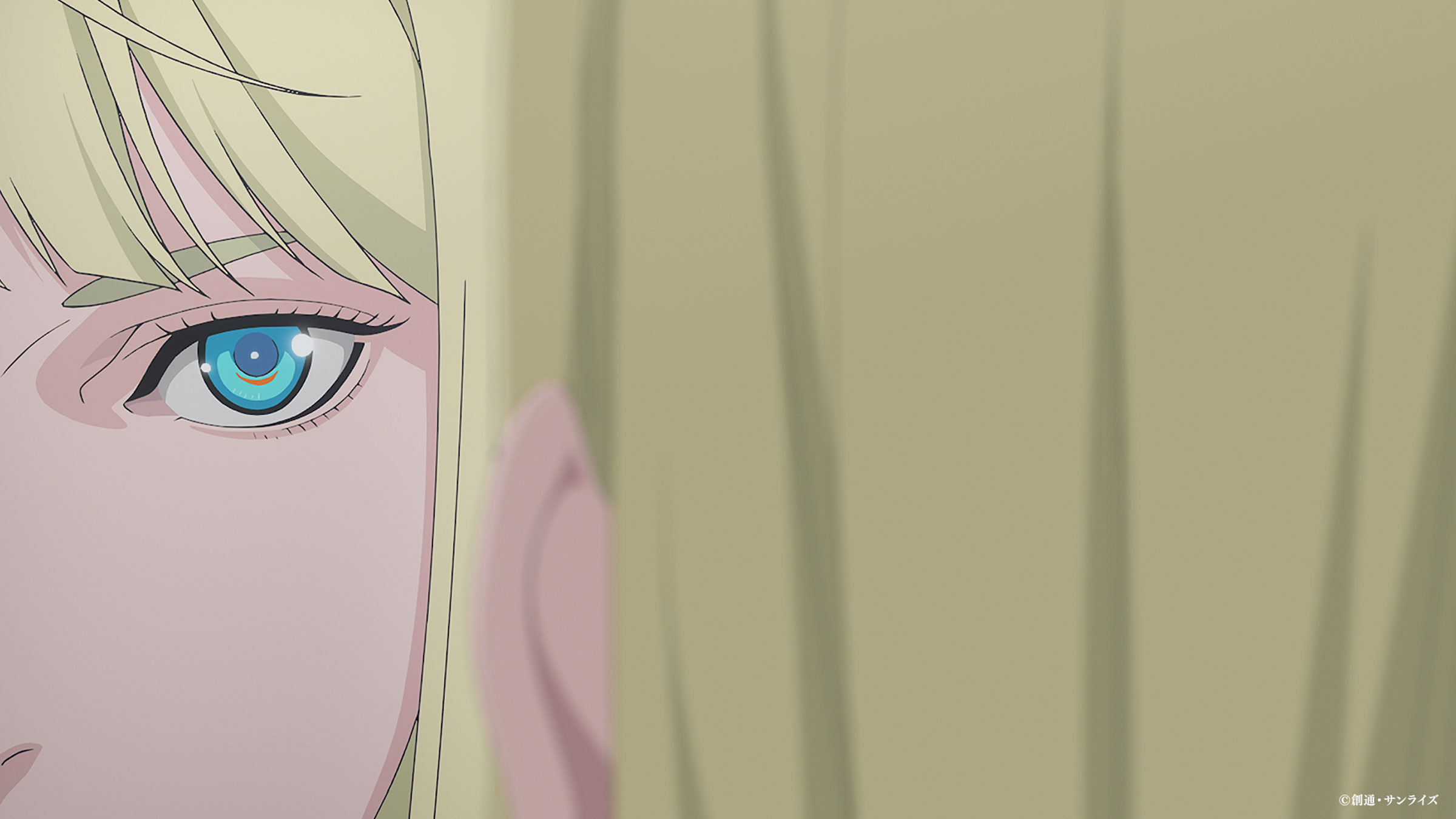「共通体験」が失われる前に
コロナ禍の期間に進行していた『すずめの戸締まり』の企画。新海監督によると、閉じ込められたような窮屈な感覚が、椅子の姿になってしまう草太に託されているところがあるのだという。その一方で、物語にコロナ禍そのものが描かれているわけではない。むしろ、旅に出ること、旅先で知らない誰かと縁が結ばれること……コロナ禍によって制限されているものがいきいきと描かれることで、かえって失われていると思い出すような描き方になっている。
新海監督とコロナ禍といえば、私たちがコロナ禍を経て「世界が一変する」という感覚に強いリアリティを感じるようになったことで、『天気の子』が「予言的作品」と称されるようにもなっている(帆高の選択により、世界は大きく変わってしまうため)。この評価を監督はどう感じていたのだろうか。

「『天気の子』が予言的な作品だったというよりは、僕も含めた誰もが、世界がいずれ変わってしまうのではという感覚がずっと植え付けられていたような気がするんです。『天気の子』の小説版で、須賀圭介というキャラクターの心情として『このままで済むわけがない』『このまま逃げ切れるわけがない』と語らせています。須賀は東京に豪雨が降り始めた前後に、自分たちの生活が変わってしまうという予兆を感じているわけですが……この感覚はずっと前からみんなの中に存在していただろうけど、僕にとっての起点は2011年でした」
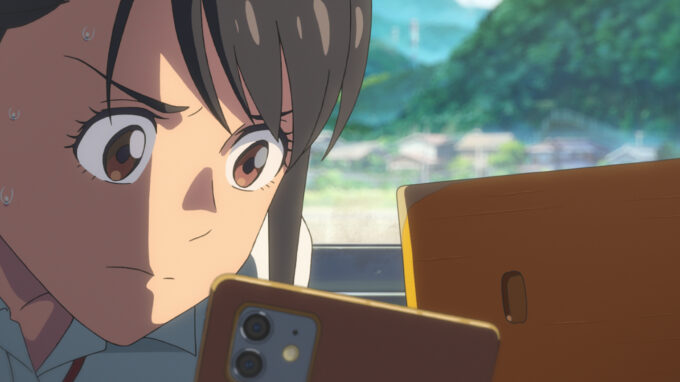
『君の名は。』は彗星落下、『天気の子』は異常気象、そして『すずめの戸締まり』は地震を扱う。災害をめぐる物語として「三部作」と称されることは、今後ますます増えていくだろう。
「2011年に東日本大震災を経験して、自分も世界も書き変わってしまうような衝撃を受けました。日本社会そのものが変わってしまうような、自分が今立っているこの場所は容易に失われてしまう、いつ失われてしまうかわからないんだという感覚。その気持ちをずっと抱えていて、『君の名は。』では地震を1000年に一度到来する彗星が落下するというメタファーとして描き、『天気の子』でも人があらがうことのできない自然災害の描写になっていった。ずっと同じことを考えながら、形を変えながら映画を作り続けてきたように思いますね」
新海監督のこれまでの作品群を(多少乱暴に)ふたつに分けるとしたら、大きな変換点となるのはやはり『君の名は。』だろう。『言の葉の庭』(2013年)までの新海作品は「大人になってしまった人たちに刺さるエンターテインメント」的側面があった。それが『君の名は。』で観客の幅が一気に広がり、文字通り老若男女が映画館に足を運んだ。

「今年の10月28日に金曜ロードショーで『君の名は。』が放送されたのですが、12歳の娘からの感想がLINEで届いたんです。『すごくいい映画だね、泣いたよ』と(笑)。成長して、入れ替わりや3年の時間のズレという仕組みを理解できるようになって泣いてくれたわけですが、12歳で震災当時の記憶がほとんどない彼女は、これが震災をきっかけに作った映画だということはわからないんです。僕の映画は小学生や10代の若い観客にもたくさん見てもらえるようになって、それはとてもうれしいことではあるけれど、娘と同じように当時の記憶がほとんどない方も多く、あれほど巨大な経験だった3・11が僕たちの共通体験じゃなくなっている、という感覚もありました。その一方で、鈴芽と同じような年頃で、11年前の記憶を生々しいものとして今も持っている人も存在しています」
東日本大震災以降、さまざまなエンタメで震災を下敷きにした物語が作られてきた(たとえば『君の名は。』と同年に公開された『シン・ゴジラ』なども、ポスト震災のエンタメ作品としてよく名前が挙がる作品のひとつだ)。ただ、震災直後のエンタメでは、モチーフは「彗星」や「怪獣」などに置き換えられた。震災から11年経った11月11日に公開される『すずめの戸締まり』という作品は、地震そのものをより正面から扱っている。
「震災という巨大な災害体験が、コロナというある種の災害体験によって、ひとつ『過去』になってしまうのではないかと感じました。だからこそ、今作らなければ、という気持ちがありましたね。震災は社会みんなが感じた大きな悲劇で、今も続いている悲劇なわけです。けれど、今より3年後に出したら、もう共通体験として感じてもらえないのではないか。今出せば、『こういうことがあったんだ』と記憶を保てるのではないかと」

新海作品の魅力のひとつ、美しい背景は本作でもこれでもかと力をふるう。九州から出発し、北へ北へと進む鈴芽の旅は、風景が美しく描き込まれることで、“いま”の日本を描き残すドキュメンタリー的側面も獲得している。とくに物語後半、鈴芽・環・芹澤のアンバランスな三人組によるドライブは、キャラクター以上に観客のほうがはっとするような光景をそのまま描く。それは数十年後の観客にとってはきっと、2020年代の日本はこうだったのだと知るきっかけにもなるだろう。そういう力を持っている映画だ。
「いま」を描く映画が大きな規模で公開されると、想定される批判もある。まだ癒えない傷やトラウマを抱いた観客にも届いてしまう可能性が、これだけの公開規模となると当然ありうる。新海監督はそのことについてどのように思っているのだろう。
「悲劇的な出来事をエンターテインメントのメジャー作品で語ってはいけないと思われてしまうこと、当事者でなければ語る資格がないと思われること、そう自分を律したり、自分で思ったりしてしまうこと――それこそが恐ろしいと思いました。ワクワクドキドキ楽しめるエンターテインメントのアニメーション映画の中で、災害を根底に大きく引いていければ、もしかしたら多くの人にとって『こういう形もありだ』と思ってもらえるのではないか。そう思ってもらえたらいいなと、希望を持ちながら作りました」

鈴芽が閉じることになる“扉”は「人がいなくなってしまった寂しい場所で開く」というもの。かつては存在していた楽しい時間の声を聞きながら、鈴芽は扉を閉じていく。劇場パンフレットのプロダクションノーツでは〈ふたりがバディとなりアクション満載の冒険を繰り広げながら、その解放と成長を楽しく描く、軽やかな娯楽映画でもある〉とねらいが綴られている。その言葉どおり、鈴芽の冒険はたしかにワクワクして、同時にせつなくてまっすぐなものだ。
「鈴芽というキャラクターの言葉に、『嘘がない』と思ってもらえたらいいですね。クライマックスの彼女の言葉に『うん、そうかもしれないね』と思ってもらえるんだったら、アニメーション映画を作るという仕事にもっと誇りを持てるかなと、そんなことを考えています」![]()
- 新海 誠
- しんかいまこと 1973年生まれ、長野県出身。2002年、個人制作の短編作品『ほしのこえ』で商業デビュー。その後、『雲のむこう、約束の場所』(04年)『秒速5センチメートル』(07年)『星を追う子ども』(11年)『言の葉の庭』(13年)を発表。2016年公開の『君の名は。』は社会現象を巻き起こす大ヒットとなり、2019年公開の『天気の子』も同年の国内興行収入1位を記録するなど、国内外から高い評価と注目を集めている。